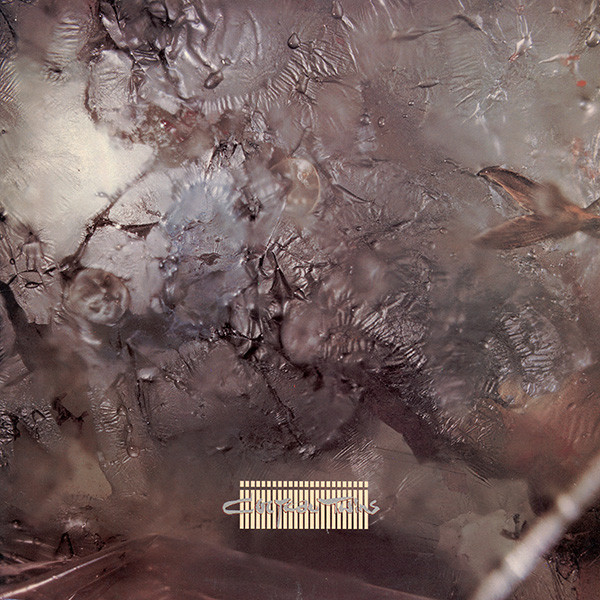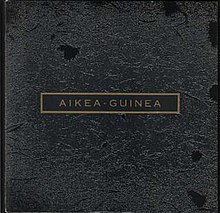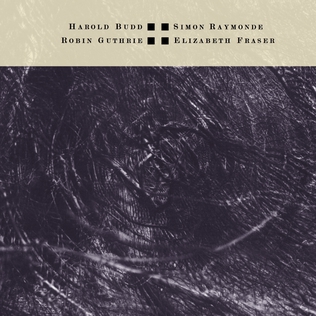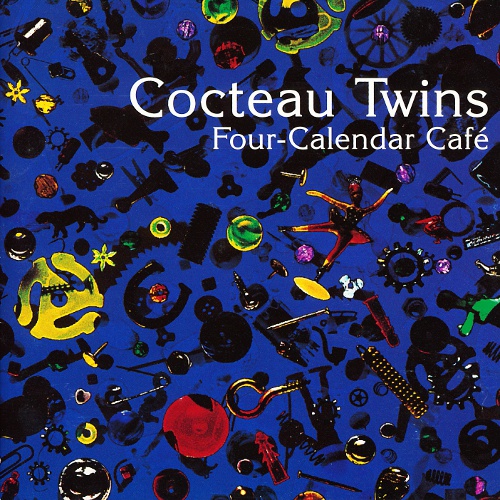成り行きで突如Cocteau Twinsにハマったので、連続して記事にします。今度は、彼女たちの全スタジオアルバム(8枚)及び意外と色々と出しているシングル・EPの類もそこそこ触れながら、1982年の最初のアルバム『Garlands』で始まり、1996年の最後のアルバム『Milk & Kisses』で終わってしまうその歴史を、割とサラッと概観できればと思います。最後には自分の好きな曲で作ったほぼオールタイムのプレイリストも付けておきます。
前回と今回の記事の発端となった、このバンドも所属した名門レーベル4ADに関する記事前半は以下のとおり。後半はこの記事を書き終わった後速やかに書くのを再開します。
- Cocteau Twinsというバンドについて
- 本編:全アルバム+シングル・EP
- 終わりに
Cocteau Twinsというバンドについて
それはもう以下の前回の記事冒頭で書いたのでそっちを読んでください。
本編:全アルバム+シングル・EP
各作品のジャケットをクリックしたらSongwhipに飛ぶので、すぐ聴きたい人はそこから各サブスクに飛ぶなりして聴いてください。
1. 『Garlands』(1982年7月リリース)
なかなか雰囲気のあるもの寂しげな光景の中、どうして脇全開のおじさんみたいなのが写っているのか謎なジャケットではあるけども、4ADお抱えのデザイン事務所である23 Envelopeの作品。耽美といえば耽美か。
ともかく、記念すべき最初の作品で、なおかつオリジナルメンバーだったベーシストのWill Heggie在籍時唯一のアルバムだけど、2枚目のアルバム以降に広がる“圧倒的にCocteau Twinsな雰囲気”を思うと、正直まだ作風を確立できていない、Joy DivisionやSiouxsie and the Bansheesと類似した、ダークで無機質なポストパンク作品、といった趣。正式ドラムがいないことによる、TR-808を使用した硬いリズムが個性といえば個性だけども、攻撃的にエコーの羽根を伸ばすギターも、怪しく躍動するベースも、この時点でのElizabeth Fraserの漆黒に突き動かされたような呪詛めいたボーカルも、どれも「典型的なポストパンク」のイメージを逸脱することはあまりない。ここに自作以降で展開される「明らかに何か狂ってるのに不思議に安らぐ感覚」みたいなのは存在しない。ひたすらポストパンク的な緊張感と不安が支配し続ける。
楽曲の中では、冒頭からヒステリックなギターが鳴り続け、ベースが怪しい躍動を繰り返し続けるアルバムタイトル曲が頭ひとつ抜けている印象。延々とノイズ的に鳴り続けるギターには、後にこのバンドの命綱ともなるギターのレイヤー的・エフェクト的使用方法の萌芽がもしかしたら見出せるかもしれない。三の倍数のリズムでポストパンクしてみせる最終曲『Grail Overfloweth』ももしかしたらこの後のワルツのリズム吹き荒れる彼女らの進路を予見していたかもしれないしそうでないかもしれない。
それにしても、このバンドにしてもDead Can DanceにしてもModern Englishにしてもそれらの1stを聴くと、当時の“Joy Division的なもの”の呪縛というのは核も支配的なものだったんだなあと思わされる。もうその中心だったIan Curtisはとっくにこの世にいないのに。いや、だからなのか…。
EP1. 『Lullabies』(1982年10月リリース)
アルバムから3ヶ月後という早いスパンで出されたシングル。基本的なサウンドはアルバムとそんなに変わっていないけど、冒頭の『Feather Oar-Blades』の疾走感ある感じは中々だし、それにボーカルがより眼の据わったような歌い方をしていて、サビ的な箇所でのボーカルの重ね方にも後の作風につながりうる余地が見える。ドラムのフィルインもいい具合に騒がしいけどこれはむしろJoy Divisionっぽさが増してる感じも。
よりイカれた方向をギターサウンドは目指していたらしい。冒頭曲ではそれがファニーな方向に発露し、そして3曲目の8分を超える大曲『It's All But an Ark Lark』では1分弱のノイズイントロを用いるなど、色々と実験的なことに意欲を出し始めている。3分過ぎくらいでアンニュイ気味なボーカルやナンセンスなコーラスも現れ、これはこれで中々妙なムードがあっていいのかもしれない。
EP2. 『Peppermint Pig』(1983年4月リリース)
裏打ちのハットがアクティブな表題曲はポストパンク的な野蛮なダンサブルさがそこそこよく出ている。『Laughlines』の間奏ではややポストパンク的世界観を逸脱したエキゾチックなギターラインが登場している。それでも、次に来る2枚目のアルバムでの飛躍に比べれば、まだ最初のアルバムのサウンドの延長、という感じもする。
どうやらCocteau Twins全音源で外部プロデューサーを雇った唯一の作品らしく、その出来栄えのパッとしなさについてメンバーのRobin Guthrieはかなりボロクソ言っている。まあ、曲も正直前のEPの方がいい気がするし…。
そして、このEPはオリジナルメンバーWill Heggie在籍中最後に出た音源でもある。悲しいことに、彼が去って2人組になって以降のCocteau Twinsこそが、まさに前人未到で摩訶不思議な楽曲とサウンドと歌を作り上げていくことになる。
2. 『Head Over Heels』(1983年10月リリース)
何がどう作用したのか、このアルバムから彼女らは急に“Cocteau Twins”になる。より極端で大袈裟になったエコー、グチャグチャとノイズをばら撒くのではなく、多重に重ねられて「奇妙な別文明」めいたサウンドを作り上げていくギターサウンド、そしてやはり別文明に呪われたかのような“神懸かり”が始まっているボーカル。ポストパンク的なダークさを名残惜しそうにいくつかの楽曲に封じ込めつつ、しかし一方では「ドリームポップの始まりかもしれない」楽曲も含む、彼女たちの最初の傑作だろう。
儀式めいた冒頭曲が終わって始まる『Five Ten Fiftyfold』でいきなり浴びせられるボーカルの冷厳なメロディの様と、その霊元さを増すようにコーラスエフェクトとエコーでキンキンに冷却され聖化されたギターの鳴り方が、これまでとあまりに異質なバンドが生まれ出ていたことに気づかせる。
そして、本当にドリームポップの始まりの曲かもしれない『Sugar Hiccup』だ。ゆったりしたリズムの中を、まだ硬いけども存分に冷たいギターは奇妙に心地よい冷却具合を見せ、そして何よりもボーカルのメロディが十分にポップに聴こえうる伸びとしなやかさを持ち得ている。まさに「不思議のくにのCocteau Twins」の産声そのものだ。
このアルバムは前半がなんか凄すぎる。4曲目『In Our Angelhood』は一転、直線的なリズムの上を鋭角ながら壮絶なエコーの広がり方も持ったギターが突き抜けていく、まさかのポストパンク式疾走ギターロックナンバーで、このバンドは2度と同じタイプの曲を作らなかったが、それにしてもこの曲の格好良さも大概おかしい。もうこれ、完全にずっと後年のCaptured Tracksレーベルの音楽の世界で、これをもっと現代的なソリッドさで演奏すればBeach Fossilsになるかな、といった具合。ある意味、クールに徹したそれらよりもこの曲の方が色々剥き出しの破壊力があって、いやなんで本当に同系統の曲を作らなかったんだろう、と不思議になってしまう。
異文化的ないかがわしさを存分に放つ『The Tinderbox(of a Heart)』など次作アルバムの前振り的な曲もあり、またポストパンク版・Cocteau Twins版ロカビリー(?)みたいな奇妙な『Multifoiled』もあり、ともかく何でも新しいことをやろうとしている感じが見え隠れする。ポストパンクとして聴いてもこれまでの作品より面白い仕掛けを曲にはめ込めているし、むしろポストパンク的にはこれが最終作になってしまうかもしれない。過渡期のエネルギッシュさを怪しく放つ、十分に名作。
EP3. 『Sunburst and Snowblind』(1983年11月リリース)

アルバムから僅か1ヶ月後にリリースされたEP。ポップ性のある『Sugar Hiccup』を冒頭に置いて、あとはアルバム未収録となった曲の蔵出しか。
しかしその蔵出しも中々のラインナップになっている。不思議な穏やかさがあやしいまま続いていきダラダラと終わっていく『From the Flagstone』には中々に代え難いだらしなくも魅力的な退廃美が感じられるし、6/8拍子のポストパンク『Hitherto』にてボーカルは縦横無尽に不思議な節回しを重ねていく。『Because of Whirl-Jack』の予想外にハイテンポなまま対してキャッチーでもないメロディがそんなに轟音でもない奇妙なギターサウンドをバックに疾走していくのはこれまた妙な魅力がある。
ある意味、この辺の時期がもしかしたら最も“Cocteau Twinsらしさ”みたいなものを気にせず、様々なことに自由に手を伸ばすことができた時期なのかもしれない。しかし彼女たちの更なる覚醒はそんな自由さえ超えていく。
EP4. 『The Spangle Maker』(1984年4月リリース)
実にゴシックなジャケットに来るアルバムの予感を思わせるEP。
ポストパンク的な香りを残しながらギターのフィードバックノイズなのかシンセなのか不明なものが霊的に飛び交っていくタイトル曲の怪しさは、しかし思いのほか戦場的なメロディを有するサビに回収される。ポストパンク的なもののCocteau Twins的拡張方法といった感じ。というかこんな畳み掛けるようなサビメロディも書けるんだ。終盤の爆発的な展開にも驚かされて、確実に何かのステップが進んでいることが実感できるゾクゾクするようなものがある。
そして、そのゾクゾクをそのままに摩訶不思議の世界に誘ってしまう6/8拍子の楽曲『Pearly-Dewdrops' Drops』によって、いよいよ唯一無二のCocteau Twins節が完成したことが告げられる。変な声の張り上げ方や意味不明な語の連呼を極めて楽器的に使用するボーカルの有無を言わせぬ勢いと、冷たくも時に安らげるアルペジオを差し込むギター。この曲こそまさに異常な名作『Treasure』の前触れとでも言うべきナンバーだ。本人たちおかレーベルのどちらかにもその自覚があったのか、ビデオクリップもこの曲で作られている。
もう1曲の『Pepper-Tree』も異様な音に変質したギターと妙なサウンドエフェクトが怪しげにこだまする不穏な“異文化の闇”を覗き込んだような楽曲で、バンドのポテンシャルが最初のピークに達しようとしていたことが如実に伝わってくる。
ちなみに、This Mortal Coilでの接点を経てメンバーに加入したSimon Raymondeが最初にクレジットに登場する作品でもある。
3. 『Treasure』(1984年11月リリース)
4AD記事でも触れたけどもう一度書きましょう。
こうやって順番を追って聴いていくと、最高にポテンシャルが高まった彼らがこのアルバムでどれだけ自在にやりたい放題しているかがよく分かる。挙句メンバーからこれだけの完成度と訳分からなさを有しているに関わらず「未完成」だの「中絶」だの言われて、いよいよ訳がわからなくなる。全部謎めいた1単語の曲タイトルで統一され、かなりコンセプチュアルな感じがするのに、本人たちはさらに作り込む気だったのか。ジャケットのゴスさ加減も含めて、何もかも完璧に見えるのに。
4AD創始者Ivo Watts Russellの名を冠し、しかもその名前で変なコーラスさえしてしまう冒頭の『Ivo』からしてテンションがおかしいし、そしてこの曲によって遂に、このバンドの奇妙さを決定づけるElizabeth Fraserのファルセットボーカルが登場する。全てのパーツは揃ってしまった。あとはもう、なすがままに彷徨うままだ。
2曲目『Lorelei』の、何もかもが奇妙なはずなのに不思議に夢見心地になってしまうこのポップさは何なのか。頭のネジが全部溶けてしまったんじゃなかろうかと思わされるこの夢見心地の拷問のような楽曲の、何もかも調子がおかしい様、そしてなのに圧倒的にポップでドリーミーな様は、ドリームポップの歴史を通して見てもとりわけ奇妙なバランスが保たれたもののひとつだろう。
もはや何の楽器なのかさえ分からない、どこかの辺境の地の伝統楽曲で奏でられたその地の民謡じみた『Beatrix』は、これは次作『Victorialand』の不気味な伏線めいている。前作的な攻撃性を残しつつリズムのハードさが強烈な『Persephone』から、急にジャズをCocteau Twins液に浸してグズグズにしてしまったような『Pandora (for Cindy)』と続き、そして不思議の国にすっかり連れて行かれて、そこの妖精の奏でる音楽みたいに聞こえる(しかも妙にポップな)『Aloysius』*1に至る頃には、もうポストパンクだった頃の姿など遠くに消えてしまって、ただただ"Cocteau Twinsなるもの"がひたすら幻惑し続ける。
くぐもった音響がどこかアンビエント音楽的なインスト『Otterley』を経て、最後には6分超える尺で賛美歌を壮大に捏造してしまったかのような『Domino』が控えている。もはやここまで来るともうプログレの領域だろう。ドローン音に降りかかる鈴の音もおかしいし、リズムが入って以降のワンコードで延々と進行し続ける場面の変なテンションとそこからの解放の様など、見事な構成で異様さを上手くまとめ切っている。最初のフレーズの演奏への被せ方がとても大胆で上手い。何が一体未完成なんだ…。
おそらくはちゃんと全曲レビューすべきなくらい、各曲の特徴が際立っていて、どれも素晴らしい。どれもことごとくポップミュージック的には異様であるために、より広くリスペクトしようがある『Heaven or Las Vegas』の方が広く聴かれている印象もあるけども、一番イってしまっている作品ということならば、文句なくこの作品を選べるだろう*2。
EP5. 『Aikea-Guinea』(1985年3月リリース)
バンド最初の絶頂期が続く。前作で完全に掌握した「別文化圏の音楽を完全に捏造してしまう能力」をポップ方面に援用したタイトル曲を含むこの4曲入りEPによってバンドの名声はさらに高まった。
タイトル曲のじっくりとポップな曲構成がまた見事で、夢見心地なボーカルはそのままにどっしりとしたリズムの中を不思議に覚醒して飛び回る様は、『Lorelei』のずっと狂った夢の中で浮かんでる感じと心地よい対称性を有する。パッド的に響くサウンドや冷たいピアノの音色も効果的で、こんなにふわふわしたボーカルなのに、何だか妙にエモい感じがするのは何でだろう。“力強いドリームポップ”という、なんか矛盾してそうな形容が浮かぶ。
2曲目の『Kookaburra』もこの時期の異様なサウンドのまま実にポップに作られていて、『Lorelei』をもっと軽やかに弾ませたかのようなテンポの良さが心地よく通り過ぎていく。高音をプルプルと響かせて楽曲をドライブさせていくベースラインが楽しい。この時期の、サウンドは正直かなりささくれ立っているのだけど、なのに問答無用に夢見心地にさせてくる「強制ドリームポップ」みたいな矛盾した感覚の奇妙さと絶妙さが本当に唯一無二で楽しい。
3曲目、4曲目はダークな側面もしっかり見せて、どこの地方の人?とばかりに不可思議に喚き倒す『Quisquose』、チープなリズムボックスから始まる割に突如凶暴で厳格なサウンドに切り替わってビックリするインストの『Rococo』と、実に充実し切っていて4者4様な4曲が揃っている。
ちなみに2枚目のEPくらいからここまで「春頃にEP→秋頃にアルバム」の流れを繰り返してる。『Treasure』が未完成でどうこうとメンバーが愚痴っているのはこのサイクルの遵守がこの時期まではあったからなのか。
EP6. 『Tiny Dynamine』(1985年11月リリース)※画像右
EP7. 『Echoes in a Shallow Bay』(1985年11月リリース)※画像左
1985年の秋はアルバムの代わりに2枚のEPが2週間おきにリリースされた。2枚揃えると1枚の絵になるジャケットなど、作品の連続性の煽り方がいかにもコレクション欲を煽っている。実際、双子の作品と言えるだろう。
ただ、2枚合わせて合計8曲とそれなりにアルバムサイズになりそうなマテリアルをどうして2枚のEPに分ける必要があったのか、と思って聴くと、正直、作り手の行き詰まりが感じられる作品群の様にも聴こえなくもない。8曲の中から突出してポップな1曲というのが見つからず、今までやってきたことをよりマイナーな調子で極端にやろうとしてるだけの様に感じられてしまう。芸術性は増しているかもしれないが、ポップ感はこれより前3枚に大きく遅れを取る。
『Tiny Dynamitne』冒頭の『Pink Orange Red』は『Treasure』の路線をより深いエコーのヴェールとよりヨーロピアンなマイナー調で再現したトラック。エコーの向こうにえも言えない憂鬱を漂わせる様は確かにアーティスティックな度合いが更新されていて、人懐っこさが消えた代わりに不思議な雄大さがある。他に、憂鬱なリゾート地に迷い込んでしまったかのようなインスト『Ribbed and Veined』に、『Treasure』と同じくどこかの部族の祭壇に迷い込んだような『Plain Tiger』、ややシャッフルめいたリズムの中にポップなメロディを結ばずに妙に唸り喚いてしまう感じの歌が乗る『Sultitan Itan』が収録されている。
『Echoes in a Shallow Bay』の方は、冒頭から奇妙なエフェクトで幕を開け、延々と氷のようなギターの中を不思議に喚き続ける『Great Spangled Fritillary』の時点でポップさは全然ない。どこか実験音楽めいてきている。他に、ボーカルのエコーが少なくはっきりメロディがある『Melonella』でハッとするけど、この曲はドラマチックな展開を雑に野蛮なフックでちょっと台無しにしてる感じがするのが勿体無い。よりマイナー調の効いたエコーの中をピアノの連弾を軸に蠢く『Pale Clouded White』に、厳しい残響を不穏に響かせて、気持ち悪い「後継と天使の歌声が交錯するような倒錯した光景を描き出す『Eggs and Their Shells』が収録されている。個人的には『Eggs〜』には何かシューゲイザーの前触れめいた音響を感じて、ボーカルラインもこの曲がこの2枚で一番冴えている様に思える。
Compilation『The Pink Opaque』(1986年1月リリース)
タイトルと裏腹に真っ黒なジャケットのこれは、アメリカのRelativity Recordsというレーベルが4ADからのライセンス生産でCocteau Twinsの作品をアメリカで出すとなった際に、アルバム等をそのまま出すのではなく、1985年のEP『Aikea-Guinea』までのバンドのサンプラー的なものとして作ったコンピレーションアルバム。日本でも日本のアーティストが海外進出するときにリリース第1弾が代表曲をまとめたコンピだったりすることがあるけど、そういうやつか。
選曲した人が「折角だから…」と思ったのか知らないけど選曲はシングルが中心で、実際力作だった『The Spangle Maker』から実質全曲収録されてたり、『Lorelei』をちゃんと収録してたりと見所もあるが、しかし2枚目の時期の最もポップどころであろう『Sugar Hiccup』が未収録だったり、不思議なところも多い。目玉は音楽誌NMEのコンピレーションに付属していた『Millimillenary』が収録されていることか。気怠げなアルペジオの割にメロディが妙にしゃくり上げてくるし中々理不尽な節回しの展開をして見せる、1984年のCocteau Twinsのやりたい放題な感じがいい具合にはみ出してきている隠れた良曲。
4. 『Victorialand』(1986年4月リリース)
深いエコーと憂愁の果ての逃避行。誰かの歌にある「誰も触れない/二人だけの国」っていうのはこういうことなのか。そりゃ誰も触れねーわ。制作時This Mortal Coilの方の活動で忙しかったらしいSimon Raymonde抜きの、後に夫婦となる2人だけで完全に制作されたこともまた逃避行の感じを強める。
しかして、その「どこか別の、ファンタジーの国への静かな逃避行」そのものなサウンドと歌がひたすら展開される。使用されている楽器の多くはギターなんだろうけども、本来の音なんてもう分からなくなるほど深くかけられた幻惑的なエフェクトがアルバム中を覆っていて、そして物語の中に出てくる妖精のように舞うElizabeth Fraserのボーカルもまた、全て架空の民謡じみた、ポップソングの世界と遠く隔てた場所でひたすら歌われ続ける。完璧な世界には必要ないとばかりに、それまで神経質に響いていたマシンドラムは排され、空間をエコーと物語めいた歌が包み込んでいく。
どれかの楽曲を取り出してどうこう言うようなアルバムじゃない。全ての楽曲がひとつのコンセプトのもと徹底して同質に形作られた、このバンド最大の“コンセプトアルバム”的な何かであって、ホラー的な意味を排した、本来の“ゴシック”なものがここに繰り広げられているのかもしれない。抽象的な音の重なりがあったり、どこか牧歌的な光景を思わせる響きや囁きがあったり。1曲だけ取り出すなら、イントロの“神々しく降りてくる感じ”で全て承知させられる『Fluffy Tufts』を挙げておこう。このアルバムはこういう作品なんだと、この曲のイントロと完全にイってしまったボーカルが雄弁に教えてくれるだろう。
このアルバムにおいてはもう、ポップフィールドなんて気にしていないのだ。もはやロックの要素も微塵も無く、ひたすら「Victorialandの物語」に9曲32分の間付き合わされるのだ。本当に極北の作品で、もしかしたらこのバンドで一番凄い作品はこれなのかもしれない。だけどそれはひどく悪く言えば、隠者の戯れのようでもある。この音楽に積極的に耳を傾けることができなければ、リスナーは置いてけぼりを喰らい続けるだろう。
1986年の彼らのリリースした楽曲は全体的にそんな、ポップさよりもアーティスティックさに全振りしたような楽曲が多い。そこから1988年の次作アルバムで急にポップになるのはまた、どんな心変わりだったのか。
EP7. 『Love's Easy Tears』(1986年9月リリース)
神秘主義者になったバンドがようやく“バンド”な音に復帰した4曲入りEP。とはいえ、不可逆的な変化に色々と晒された楽曲たち、という感じもあり、『Lorelei』や『Aikea-Guinea』のように強引に人の耳を引っ張ってこれるようなポップさはあまり見当たらない。初期のハードさもアルバム同様消え失せていて、アルバムの神秘性をバンドサウンドで展開させてみるとどうなるかの実践にも思える。
セブンスなコード感が意外に感じるアルペジオに導かれたタイトル曲は、しかしボーカルの取り留めなくどこか遠くの国の音楽のように何かを唱え続ける感覚に、ポップシーンへの目配せは存在しない。『Those Eyes, That Mouth』には『Treasure』の頃の冷たさが戻ってくるけどもメロディは煮え切らない。『Sigh's Smell of Farewell』が一番理想的に『Victorialand』の世界観をバンドに反映させたものになっているかも。どこまでも気のおかしくなりそうな平穏が広がっていくようなギターの鳴り方は“極北”まで行ってしまった後の残り香を十分に感じさせる。後半で思いもよらない覚醒をして少しばかり荘厳になるのには意外なキャッチーさがあるけども。最後の『Orange Appled』は演奏に平穏なポップさが感じられるけど、歌の調子は『Victorialand』してる。けどその雰囲気のまま突如早口に吹き出してくる展開も、思いのほかフックとして機能していて、もしかして『Vicorialand』方式の楽曲でもポップソングは作れるのだろうか…という可能性を少しばかり感じさせる。
このシングル、後半の曲の方がポップじゃね?
Collaborative album『The Moon and the Melodies』(1986年11月リリース)
実はアルバムのどこにも“Cocteau Twins”とは書かれていないけども*3、1986年のオブスキュアなバンドの活動を締め括る、ミニマルミュージックの作曲者Harold Buddとのコラボレーションアルバム。オブスキュアな1年の最後にミニマル音楽家とのコラボ、実に筋が通っている。
全曲共作ではあるけども、Cocteau Twinsとしての楽曲が感じられるのはうち半数の歌がちゃんとある曲だろう。
冒頭の『See, Swallow Me』はお得意の6/8拍子のリズムと幻想的に浮遊するギターサウンドと美しいピアノの調べ、そして“Victorialand”しまくったボーカルで構成される、ここまで幻想的な感じを突き詰めた結果、もしかしたらこの年で一番キャッチーな曲になったのかもしれない楽曲。歌が完全にサウンドの一部になっているけども、確かに同じ様な繰り返しの中に演奏のダイナミズムによる展開がはっきりあり、その展開の圧倒的な様に心奪われる。ポップソングとは違った心奪われ方はやはりクラシック的なそれなのか。なぜかサブスクやYouTubeで最も再生回数が多いのがこの曲になっている。ま、まさかクラシック的な聞かれ方を本当にしているのか…?
4曲目『Eyes of Mosaics』や5曲目『She Will Destroy You』、最終曲『Ooze Out and Away, Onehow』が歌入の楽曲。4曲目は静かになるセクションの透明感が美しい。5曲目はタイトルの物騒な割にロマンチックな楽曲。いやむしろこのタイトルこそロマンチックなのか。最終曲はリズムなしでささやきの様な微かな歌とギターが消え入る様になっていたかと思うと突如アンサンブルに劇的に切り替わる楽曲。知らないと最後の最後でビックリする仕組みになっている。
歌のある4曲とも全て6/8拍子という、実に潔くCocteau Twinsしたスタイルになっている。後のインストの曲もまあ幻想的なのは間違いなく、アルバムタイトルに偽りなしって感じの作風は、実はもしかして『Victorialand』よりも聴きやすいのでは…?とも思ったり。
5. 『Blue Bell Knoll』(1988年9月リリース)
1986年まで作品をコンスタントにリリースしてきたけれど、1987年はシングル1枚のリリースすらなく、そんな状況から1988年7月にポンと、このアルバムのリードトラックで、そしてかつて無くポップソングのルールに沿って軽やかにポップソングしてみせる『Carolyn's Fingers』が先行リリースされたとき、ファンはどんな風に感じたんだろう。ボーカルのオペラめいて異様なファルセットにバンドの同一性を保ちつつ、それ以外は思いっきりギターポップ的な開放感を有して、The Cureのシングル曲みたく軽やかに舞い上がっていくこのトラックをもって「後期Cocteau Twins」と呼んでもいい時期に入ったのではないかと思ったり。
そしてシングルのすぐ後にリリースされたこのアルバムで、その方向性は確定された。冒頭のタイトル曲こそ旧来的なゴスな別世界音楽の様相ではあるけども、それもバンドアンサンブルがしっかり入り始めると、それまでよりも歯切れのいいバンドアンサンブルに爽やかさが感じられる。ここの終盤の緊迫感ある盛り上がり方はいよいよThe Cureじみてもいる。それを過ぎるともう、ポップさがあちこちから漏れ出してくる。
2曲目『Athol-brose』はボーカルに"Victorialand"な不思議さは残しつつも、でも楽曲自体は明らかにもっと分かりやすく躍動感に富んでいて、トレードマークの冷たいギターサウンドもこう雑然としたエネルギーの中で鳴るとまた聞こえ方が違うものだなって思える。3曲目に『Carolyn's Fingers』が収められ、もう圧倒的にポップ。続く『For Phoebe Still a Baby』もまた、柔らかな穏やかさにポップで自然な安らぎが感じられ、バンドの指向性そのものの変質がかなり分かりやすく示される。異郷感がどこかリゾート的に響き歌の調子ものんびりとオリエンタルな『Cico Buff』のしっとりした上品さもとても滑らかだ。民族音楽っぽい『Suckling the Mender』にもキャッチーなサビが用意され、またシーケンサーに導かれて浮遊感に満ちたポップさを発揮する『A Kisses Out Red Floatboat』もまた爽やかで雄大だ。ラストの『Ella Megalast Burls Forever』もまた、かつてなくフォーキーなポップさを発揮したしっとりしたナンバーで、その泰然としたメロウさや変なボーカルにはどこか中華的な舞い方も感じられる。
バンドがアメリカでの契約先が超大手レーベルであるキャピタルになって最初の作品がこれということで、そういう事情から“売れる作品”を志向し制作されたのかもしれない。だけど、1986年のスタイルでやっていくのにも限界があっただろうし、この変わり方はとても良かったんじゃないかと思う。一方で、バンドが独自に税理士を雇って4AD側と摩擦が出てきたり、Robin Guthrieのドラッグ中毒がこの辺りから加速したりと、次作で4ADと袂を分つことになるその伏線も用意され始めている。
何はともあれ、ジャケットが地味だからかどこか地味な感じもするアルバムだけど、そのポップポテンシャルは高く、特に秋冬の空めいた程よい潤み方と渇き方をしたギターポップのアルバムとして愛好できるのでは、と思う。
6. 『Heaven or Las Vegas』(1990年9月リリース)
前回の記事を参照。流石にアルバムについてこれ以上書くことはもうない。
なお、アルバム先行リリースとなったシングル『Iceblink Luck』にはアルバム未収録の2曲が含まれていて、『Mizake the Mizan』はアルバムで最も穏やかな『Wolf in the Breast』と並ぶくらい穏やかな楽曲。ギターの音は相変わらずの不穏なコーラスのかかり具合なのにこのまったり感はなかなか凄い。ドリーミーだ。もう1曲の『Watchlar』は冒頭から露骨にシンセベースがうねうねし、かなり思い切った16ビート気味のリズムが躍動する、ヒップホップ的なものをアルバム本編以上により露骨に志向したっぽい相当な冒険作。流石に冒険すぎと判断したのかここに置かれてる。こういう方面の楽曲は割と本当にこの時期だけなので、その事実も込みでなかなか興味深い。
リカットシングル『Heaven or Las Vegas』にもアルバム未収録曲『Dials』がある。鈴のような響きに包まれた神聖で優しげな歌に、途中からフィードバックノイズがまとわり付いてくる、これもまたドリームポップ的なものに対する天然の挑戦めいた手法が色々と見られて面白い出来になっている。
7. 『Four-Calendar Café』(1993年10月リリース)
遂に4ADを放逐されたCocteau Twins*4、途端にこんな幻想性も何もないヘンテコなジャケットのアルバムを出してしまう。別にレーベルは関係ないかもだけども、でもどうしてこんなジャケットになったの…?これまでと流石に雰囲気が違いすぎるかなと。
「途端に」とは言うものの、結構リリースの間が開いたことにバンドの混乱した内情が透けて見える気もする。メインメンバー二人の離婚も同じ年で、なんかいろいろ大変だったんだろうなあ。1993年にもなると、シューゲイザーのブームさえ収束して、イギリスではブリットポップの時期に入ろうとしてる頃。
4AD追放後メジャーレーベルに活動の場を移したため、本作はよりメインストリームに迎合した作風としばしば言われ、というか多くの場合、4AD追放後の2枚のアルバムはその一言で片付けられ、あまり省みられないことが多い。でもはっきり言って、全然悪くない作品で、『Carolyn's Fingers』があって『Heaven or Las Vegas』があったんなら次はこんくらいの作品じゃないか、と思えくるらいの妥当性はあると思う。
確かに冒頭の『Know Who You Are at Every Age』のギターの感じはそれまでにあったエッジ的なのは剥がれてもっとアダルトにまどろんだ音色で、もっと言えば楽曲からAORの匂いさえ感じないわけでもない。でも、“あの超然としたCocteau Twins”と思って聴かなければ、Cocteau TwinsとAORの相性はそんなに悪いものでもないんじゃないか。リードトラックの2曲目『Evangeline』はよりギターの響かせ方がAOR的なムーディーさを感じさせるけど、実に丁寧に作られたトラックで悪くない。『Bluebeard』は今度はカントリーミュージック的だけど、これもボーカルのコントロールの仕方と奇妙なコーラスの挿入の仕方が堂に入ってて、というかこんなカントリーテイストのギターのスキルもあったのか、というのもあって中々良い。丁寧に歌うElizabeth Fraserの低音は少しKaren Carpenterみたいだ。よりはっきりとフォーキーな『Squeeze-Wax』でも、ややミスマッチそうなAORなカッティングやドリームポップ的なトレモロギターを上手いこと盛り込んで気の利いたアレンジになっている。
アルバムは終盤、2つの静かでスピリチュアルな曲『My Truth』と『Essence』を経て、特に『Essence』の深いエコーを超えた先で、これまで隠してきたロックバンド的な突破力とシリアスなコード感の『Summerhead』で一気に引き締まる。この曲は本当に素晴らしい曲で、『Victorialand』めいた不思議ギターも『Heaven or Las Vegas』じみたシューゲイザーギターも現れ、程よい緊張感とファルセット気味のボーカル等も相まった陶酔感とで、1曲の中で饒舌なドラマ性を感じさせる、ひょうっとして4AD追放後でも1番いい楽曲かも。こう、ART-SCHOOLとかにも通じれそうな切迫感と切なさなんだよなあ。最後は子供への想いを優しげにドリーミーにそして壮大に歌った『Pur』で締め。これも良いドリームポップだ。
4AD追放後のCocteau Twinsを聴いたことない人は、まずは『Summerhead』だけでも聴いてみてほしい。アルバムの最後の方にあるから先頭から順に聴くと辿り着く前に再生を止めてしまうかもだけど。そういう人のために下に動画も貼っておくから…。
EP8. 『Snow』(1993年12月リリース)

アルバムからそんなに間を置かずにリリースされた、冬に関するスタンダードナンバーのカバー2曲で構成されるEP。EPって4曲くらいのイメージだが…*5。
ジャケットは、ここまで来ると可愛らしさが前に出て鼻につかず素直に良く感じれる。カバーも、おそらく4ADではあり得なかった緊張感のなさではあるけども、でもこれはこれで、バンドのファンシーで可愛らしい側面が出てて悪くはない。本当にこのElizabeth Fraserって人は案外なんでも歌える。
EP9. 『Twinlights』(1995年9月リリース)
EP10. 『Otherness』(1995年10月リリース)


この2枚は翌年に出るアルバムの先行シングル的な性質も有することになった。これら2枚に収録された曲のいくつかはその“バンドバージョン”が次のアルバムに収録されることとなった。
そしてこの2枚のEPはバンドにとっても挑戦的な作品で、『Twinlights』の方はピアノと歌メインで形作られたしっとりした作品で、『Otherness』の方はエレクトロなアレンジで仕上げられている。こんなのも出してたんだな。
『Twinlights』の方はその性質上、実に優しさに満ちた楽曲たちになっている。のちにアルバムに収録される『Rilean Heart』の有給の感じのするメロディはこのピアノスタイルで聴くことでよりダイレクトに原風景めいたものが見えてきそう。唯一アコギメインな『Golden-Vein』も背景に今でいうシマーリバーブめいたエフェクトが飛び交い、ファルセットメインの歌を神聖に包む。『Pink Orange Red』のピアノセルフカバーは、緊張感のあるピアノと風のようなボーカルで、まるで全然違う曲のようなムードを聴かせる。こうやって聴くと実は相当いい曲じゃないかこれ…。最後の『Half-Gifts』もシマーエフェクトが神々しく、良いアレンジだ。
『Otherness』の方は、まあ、1990年代の普通のエレクトロトラックの方によくある耐用年数切れを感じさせる部分もあるけども、『Feet Like Fins』の延々と何をしたいのか分からないシュールさは昔とはまた別の形でCocteau Twins的な不可思議さを放っているような感じもある。別に踊れる感じでもないのが本当に“エレクトロ”って感じ。のちにアルバムに収録される『Seekers Who are Lovers』『Violaine』についても全然アレンジが違っていて、これはこれで良い。『Violaine』はこっちの方がいいかも。こっちのセルフカバー枠は『Cherry-coloured Funk』で、これはリミックスになっていて、曲のうちのワンセクションを延々と繰り返す後世になっているから全然違う曲のような感じ。っていうか、The Weekndがサンプリングしたのはもしかしてこっちのバージョンじゃんか…?
ちなみにこの辺のEPとかその前のEPとかはサブスク上で単独では置いてないかもだけど、4AD追放後=フォンタナレーベル時代のボックスセットがサブスクにあって、その中で聴けます。
8. 『Milk & Kisses』(1996年3月リリース)
1997年、9枚目のアルバムのレコーディング中にバンドは解散してしまい、なのでこの8枚目のアルバムが結果として最終作になった。1996年、もうKurt Cobainはとっくに死んでて、ブリットポップももうガス欠になりつつある頃のこと。前のEP2枚で全然別アレンジで取り上げた楽曲をバンドアレンジに直して再収録し、穏やかで丁寧な作品集といった趣がなんとなくある。
とはいえ冒頭は、どこか1990年代前半を感じさせるハードさにリアレンジされた『Violaine』で幕開ける。『Heaven or Las Vegas』的アレンジの最新版だろうけどもしかしこっちの方が帰って時代を感じさせるのは何故だ。2曲目『Serpentskirt』も少しばかりゴスでファンタジックなCocteau Twinsへの回帰が図られていて、冷然とした雰囲気は結構昔のスタイルを当代的にエミュレートできている。最後に置かれたリアレンジされた『Seekers Who are Lovers』もかつてのCocteau Twinsサウンドと年月を経てスケールの広がった歌い方の交わった地点みたいな風情がある。
でも、本作ではやっぱり穏やかな楽曲の輝きの方が素敵かなと思う。3曲目の、シングルも切られた『Tishbite』の、実にCocteau Twinsな音色のはずなのに非常に穏やかなまま通り過ぎていく、このボーッとなる感覚がとても良い。オルガンが入ってちょっと可愛らしくリアレンジされた『Half-Gifts』も、そして堂々たるバンドアレンジを施されて悠然とした雰囲気にスケール感が備わった『Rikean Heart』も実に、Cocteau Twinsの黄昏を快く彩る程よく掠れた艶かしさを有している。Faye Wongとの交流がこの辺の時期であったこともなんとなく分かる感じがある。
謎文化圏の音楽のテイストも今作では前作より増えており、『Ups』はややシューゲイザー気味なサウンドの中でエスニックにメロディを伸ばしまくり、そして巻き舌をパーカッションの如く多用するボーカルが何気にすげえ特殊。サイケなアルペジオにどこかの田舎の聖歌隊みたいなのが纏わりつく『Eperdu』も変だし、またエコーの向こうの静寂の中を厳粛に宗教的に歌われる『Treasure Hiding』は後のフォンタナ時代のボックスセットのタイトルになった。
このアルバムが1996年という時代において先進的なアルバムだとはまあ言わない。けれども、別に時代遅れのアルバムでもないだろうし、別に彼女たちだってそんなのをそこまで気にしすぎずに制作していたはずだ。本作でわざわざ取り返してきた、かつてと同じくエフェクトで原音がかけらも残らずグジュグジュになったギターサウンドは楽曲を冷凍保存しているかのようで、不思議な揺らぎと穏やかさに満ちた楽曲たち、数あるCocteau Twinsの名作等を聴いた後に誰かがここにやってくることを待っている。
・・・・・・・・・・・・・・・
終わりに
以上、駆け足で大体の作品を見ていきました。こうやって初めから見ていくと、ポストパンクの虚無的なダークネスから生まれ出たバンドが、奇怪なファンタジーを手に入れて、その奥に潜み込んでしまうかと思ったら、やっぱりポップフィールドに戻ってきて、そしてレーベルを追放され、最後はなんか穏やかな歌心に目覚める、といった一連の流れが、実に人間的なドラマじみたものに見えてしまいます。もしかしたらこの記事はむしろバイオグラフィーの方を味わって書いてた記事なのかもしれません。
何にせよ、『Treasure』『Heaven or Las Vegas』以外にも色々と狂乱だったり爽快だったり壮絶だったりのCocteau Twinsサウンドと作品があることが、今回本格的にこのバンドにどハマりしたことによって分かりました。また長くしっかり付き合っていけるバンドのディスコグラフィーを(とっくに解散済みとはいえ)見つけることができて、今とても嬉しいです。
ここまで延々と書き殴ってきたとるに足りないレビューが、しかしもしこのバンドの作品を聴いていく上で何か役に立つことがあったならとても幸いで幸福です。
プレイリスト
最後に、この記事を一気に書き上げる原動力となった、全20曲のプレイリストを貼ってこの記事を終えます。最初のアルバム以外の全アルバム+αから選曲しています。割とポップ寄りの選曲だろうとは思いますが、なので聴きやすいと思います。
それではまた。次の記事こそきっと4AD後編だろう…。
*1:この曲聴くときいっつも「酸素収入〜」って空耳が聞こえてきて笑ってしまいそうになる。
*2:『Victorialand』の方がある意味イってしまい度は高いけど、あそこまでイカれてしまうと中々聴きづらい…。
*3:代わりにメンバー全員の名前とコラボ先の名前が書かれている。日本盤の帯にはどうも普通にコクトー・ツインズって書いてあったっぽいけども…。
*4:多分これは放逐した側の創始者Ivo Watts-Russellにも相当のダメージが入っていたと思う。レーベルのムードをまさに体現していたバンドの追放がどれほど辛く、彼の理想を挫き、1994年の神経衰弱に陥れてしまったことだろうか。
*5:なんとなくこの記事に出てくるEPは「アルバム未収録曲で構成されてたらEP」みたいな感じがする。