
サムネ画像は今回は熱海です。2回ほど行ったことあるけど1回は車で行って大変な渋滞で死にそうになりました…。
年代ごとに夏の楽曲に触れていくシリーズを長々とやってきましたが、今回は個人的にはクライマックス感のある2000年代です。この一連の記事を書く端緒になった作品の楽曲を含んでいますし、筆者が個人的にとりわけ思い入れのある感じがする2000年代初頭の時期を含んでいます。なんだかんだで思い出には左右されてしまうもの。書く身にも力が余計に入ったのか、えらく書き終わるまで時間がかかってしまいました。
前の年代である1990年代の記事は以下のとおり。
また、寄り道的に書いたスピッツとサニーデイ・サービスの夏特集は以下のとおりです。
- はじめに
- 本編
- 1. Summer Crane / The Avalanches(2000年)
- 2. The Last Day of Summer / The Cure(2000年)
- 3. Our Way to Fall / Yo La Tengo(2000年)
- 4. All / BOaT(2001年)
- 5. Endless Summer / Fennesz(2001年)
- 6. サマースナイパー / くるり(2001年)
- 7. Summer Turns Too High / R. E. M.(2001年)
- 8. Sea of Teeth / Sparklehorse(2001年)
- 9. Re-残暑 / クラムボン(2002年)
- 10. The New Cobweb Summer / Lambchop(2002年)
- 11. 野いちご / 野本かりあ(2002年)※
- 12. Heavy Metal Drummer / Wilco(2002年)
- 13. Summer Gypsy / Nujabes(2003年)
- 14. 通りすぎただけの夏 / ゆらゆら帝国(2003年)
- 15. Will the Summer Make Good for All of Our Sins? / múm(2004年)
- 16. Fortress / Pinback(2004年)
- 17. 朱い夏 / advantage Lucy(2005年)※
- 18. Summer Skin / Death Cab for Cutie(2005年)
- 19. Evening Sun / The Strokes(2006年)
- 20. Long Forgotten Song / The Thrills(2007年)
- 21. All The Years / Beach House(2008年)
- 22. Sailing Round The Room / Emmylou Harris(2008年)
- 23. 若者のすべて / フジファブリック(2008年)
- 24. Graveyard Girl / M83(2008年)
- 25. Summertime Clothes / Animal Collective(2009年)
- 26. Let's Go Surfing / The Drums(2009年)
- 27. Summertime / Girls(2009年)
- 28. 小宇宙 / GRAPEVINE(2009年)
- 29. Pursuit of Happiness (Nightmare) / Kid Cudi feat MGMT(2009年)
- 30. Come Saturday / The Pains of Being Pure at Heart(2009年)
- あとがき
はじめに
今回はここのコーナーを、この後の30曲分を全て書き終わってから書いてるので、多少はまとまったことを言ってるかもしれませんしそうでないかもしれません。
どんどん抽象的になっていく“夏”のうたの世界
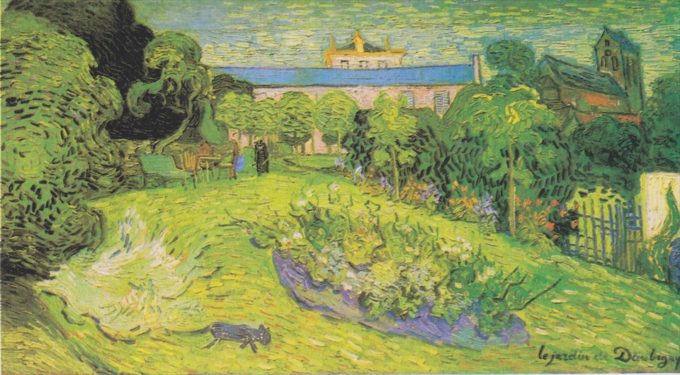
今回のリストを見てて思うのは、古典的な「ビーチ、女の子、楽しい!」はもはやそんなに出てこないな…ということで、それは単に筆者がそういうのを避けてるだけな気もするけども、いやでもそれにしても夏、海、女の子、みたいなのはどんどん減ってる気はします。夏の曲が大好きな日本の音楽を見ても、夏がテーマでも花火とかそっちに移行してたり。なんなんでしょうねなんで減ったんでしょうね。まあそれはここの項目の主題ではないので…。
とはいえ夏の曲を書くというのは、何かしら夏について書きたいと思ったからであろうけども、その動機付けとしての夏に求める魅力が、この10年間にはグッと抽象化・ファンタジー化した、という印象をやはり受けます。なんでなんだろう。
考えられるのは、エレクトロやポストロックといった1990年代に確立された手法が、ぼんやりしたものを表現するのに実に適した手法であり、それによって表現することができるようになった類の音としての“夏”が確かに存在していた、ということです。今回、実際エレクトロニカ系アーティストの夏の曲や、ポストロックに影響を受けたと思しきテイストの夏の曲が結構登場します。共通するのが、どこか遠くに美しい夏を見ているみたいなぼんやりとした感覚です。これはなんかもう、夏の中にいて楽しい、とかじゃなくて、もう完全に、何かの美しい対象として夏を眺めているような視点で、そういう意味で夏というのは「なんか尊くて美しい、もうそこには戻れない季節」のような形で、人によってはもうある意味神格化までなされたような感じさえあります。夏の宗教化、と言ったら流石に言い過ぎなのか。
これは筆者が歳を取ったからなのかもしれませんが、なんとなく生きていても、夏が終わった感じがすると不思議に寂しさを覚えるような気がします。その寂しさの落差の分でこそ、夏というものの尊さ・美しさ・どうしようもなく求めたくなる感じが測れるのかもしれません。実際の夏は暑くて不快感が高くて嫌らしいのに、何かそれだけでなくもっと尊いものを夏に見出そうとしてしまう。そんな価値観をいったいどこで見出したんだろうな、と思いますし、もしかしてこういう価値観はたとえばアメリカでヒップホップをしてる黒人アーティストの間ではどうだろう、そんなの感じたりすることあるのかなあ、なんてことも思ってしまいます。夏の尊さというのは文化的なものの結果なんだろうか。
ともかく、この年代にそのようなオブスキュアーなサウンドによってこれより前の年代には無かったような「美しい夏の曲」を得られたことは、割とそう言ってもいいのかもしれないなと思います。
夏にいじける、夏をクソみたいに扱う流れ

一方で、それまでもあったとは思うけどもこの年代に増えた気がするのが、「夏なんてクソ」みたいな表現をする事例です。実際夏に接すると暑くて動けなくて辛くてクソやなあ、とは思うんですけども、そうじゃなくてもっとこう「どうせ自分は陽と陰なら陰側のキャラだよクソがよ」的なスタンスが表現されるようになった向きがあるのかなと。こういういじけた風なひねくれ方はまさにインディロックの領分で、このブログがそういうのばかり集めてしまうから夏の曲でもそういうひねくれ方をしたものが自ずと集まってしまうけど、この年間は目立つな、と思いました。特にUSインディ。何でなんだ…ジョックとギークみたいな関係性って割とガチなもんでそのせいなのか?
本編
前回の1990年代は40曲あったのに今回は10曲減ってしまいました。その分、割とベクトルは揃えられたと思います。今回も2曲ほどサブスクにない曲が混じっているのでそれらにはタイトルのところの右端に「※」が付きます。そしてやはり最後にSpotifyプレイリストもあるのでぜひ。
1. Summer Crane / The Avalanches(2000年)
全編ツギハギ感も恐れずにいい塩梅にスッキリした混沌じみたサン
その点でこの曲は、サマーパーティー的なアッパーな賑やかさより
2. The Last Day of Summer / The Cure(2000年)
The Cure - The Last Day of Summer - YouTube
ぼくは何も無く 何も夢見ず 何も新鮮で無くて
考えも信じるものも言うことも何も無く 真実も何も無い
かつてはとても容易かった でもぼくは未だ試みてない
ああ それはかつて とても容易かったんだ
でもあの夏の最後の日 全然冷たく感じなかった
あの夏の最後の日 全然冷たさを感じなかった
The Cureの典型的なサウンドであるところの「コーラスで彩られた
このバンドのポップに徹していない時の楽曲は往々にして、何かに
3. Our Way to Fall / Yo La Tengo(2000年)
ある夏の日のことを覚えてる きみのとこまで歩いたことを
赤面してたのを覚えてる 自分の足元を見つめてたことを
ぼくらが出会う前のことを覚えてる きみの横に座って
別に見てないよって誤魔化してたのを覚えてる
だから たとえ1時間だけでも 試しに試してみよう
全力で ものにできるよう挑んでみよう
だってぼくら途上に 途上にいるのさ 恋に落ちるところの
“チルアウト”という概念はいつしか夏ソングに求められる重要な要素のひとつになっていたように思われるけど、ロックバンドで早くからそのような感覚をよく表現していたのはYo La Tengoだろう。彼らにはより直接的なタイトルの『Summer Sun』というアルバムもあるけども、その1枚前の『And Then Nothing Turned Itself Inside-Out』はジャケットまで含めて、まさにこのバンドのチルアウトな一面の決定版みたいなところのある作品だった。探してみると、案の定、夏に関する曲があったので見つけたときはホッとした。
ある夏の夜長に、チルアウトな夜長に、ちょっと昔のたわいない、けど尊い出来事を思い出してちょっとはにかむような、そんなビタースウィートな程よく枯れた大人の光景が思い浮かぶ楽曲だ。少しジャズめいたリズムを打ちつつ、シンプルなコードの反復を曖昧な出力のキーボードで広げていく。その静かに透き通った雰囲気を壊さないようにするかのようにソフトにつぶやく調子の歌は、しかし同じコード展開のまま、彼らのルーツのひとつであろうThe Velvet Underground印な絶妙に甘いメロディをそっと挟み込んでくる。この辺の絶妙な塩梅がまさにこの曲のビタースウィートさの根源なんだと思う。まるで個人的な経験の仄かに優しい質感がチルアウトな夏の夜の空気を通じて他者の身体に入り込んでくるかのような。こんな絵に描いたような涼しくビターにチルアウトした夏なんて本当にあるのかな、とも思うけどでもこの曲くらいならまだギリありそうだなって思える、その辺のリアルさもまたYo La tengo。
4. All / BOaT(2001年)
あの夏に託された言葉 ハキながら繰り返す
缶コーヒーを飲む 友達の家で
赤い電気の下 燃えるローソクを切る
明日がもしも古いなら アキラムジナを吸う
あの夏に託された言葉 さよなら
日本が誇る夏の大名盤といえば、BOaTという世紀末からJimi Hendrix式のギターとミクスチャーロックネイティブ気味な感覚でパーティーめいて駆け抜けてたバンドが急変して全てを投げ打って作り出した、深淵で不可逆な名作『RORO』である。Jimi Hendrixは宇宙を目指してたけどもBOatは夏を目指し、そしてあのアルバムを残して帰ってこなかったんである*2。元々この夏ソングシリーズの記事も、あのアルバムがサブスク解禁されたことを記念して書き始めたものだった。
冒頭を務めるこの長尺の楽曲が、このアルバムが思い求めるところの“夏”がどういう性質のものなのかを、静かに、しかし雄弁に物語っている。はじめはとても静かに、延々と繰り返されていくリフがアコギで聞こえてくる。8分の10拍子と言えばいいのか、そういう変拍子でありつつもリフ自体はどこかノスタルジックなような感じがするのにAmerican Footballとかと共振するものを思わせるけども、何か日本のどこかの町から村の夕方に聞こえてくる祭囃子のような郷愁も感じられる。このリフを延々繰り返すかと思うと、少しトボけたセクションを挿入してみたりもしつつ、その後始まる歌はメインリフと実にユニゾンし、これより前の作品の元気さからは信じられないくらい思い詰めて醒めた調子の男女のユニゾンにはどことなく殉教者めいた雰囲気さえ宿っている。
この曲は同じリフと拍子の繰り返しでありつつも、おおよそ三つのパートで構成されていると言える。最初の静かなパート、ノイジーなギターサウンドの狭間にひどく聴き取りづらいボーカルがいるパート、そしてストリングスを交えて万能感と謎の祝祭に満ちたメロディが繰り返され続けるラストのパート。はじまりの静寂からラストパートの轟音の壮大さまで連なっていくのは圧巻としか言いようがなく、その荘厳さの中でも元々のリフが、いよいよお祭りのメインテーマのように鳴り響き続けるのが、この曲の執拗な一貫性と、そこから呼び起こされる爆発的な感慨につながっている。
しかし、実は一番この曲で作者がエモくなってしまっているのは、もしかして2つ目のパートではないかとも訝しむ。はじめと終わりのパートが語感とイメージ重視でなんか文法とか適当そうな英語歌詞になっているのに対して、このノイジーなギターの中ほとんど聴き取れないレベルでよく聴くと何かA×S×Eが言葉を発してるな…程度にしか分からないパートのみ、こっそりと日本語で歌われている。それが上記の引用した箇所で、やはりイメージ重視で何を言いたいのかよく分からない風ではあるけども、何か身近な関係性の中での瞬間を捉えつつ、本作特有の謎単語「アキラムジナ」も登場しつつ*3、そして必殺の夏の言葉「さよなら」で締めるこのパートの言葉としてのエモさ。もちろん彼がその夏に対するエモいパッションを言葉ではなく音で表現したかったであろうことは想像に難くないが、しかしここのパートにおける、言ってる自分が恥ずかしくて聴こえづらくアレンジしてしまうくらいの日本語詞の素直なリリシズムは、ノイズに埋もれながらも、この曲のどこよりも何らかのパッションによって煮えたぎっている。何らかの?それは儚くも美しい、儚いからこそ美しい、そんな“夏”のイマジナリーそのものであろう。だからこそ、この曲の最終パートは荘厳さの割にやたらとあっけなく終わってしまう必要があったんだろう。“夏“は驚くほどあっさりと呆気なく過ぎて、だからこそその美しさを永遠に求めたくなるような類のものなんだろうから。
5. Endless Summer / Fennesz(2001年)
抽象的でかつ長尺な夏の名曲が続く。この曲は今回のリストの中でも最も抽象的なものだろう。The Beach Boysかよって感じのタイトルを冠したアルバムのタイトルトラックでは、まさにThe Beach Boysが有してた夏成分の中のとりわけアブストラクトな部分との共通項を思わせるような、スピリチュアルなアンビエント・エレクトロニカな仕上がり。とはいえ、筆者はこのジャンルは全然普段聴けてないところなので、以下語彙が特に不十分な発語のもとの文章となってしまう。
『Endless Summer』なる爽やかそうなタイトルの割に、そのアルバムの1曲目はなかなかに醜悪なノイズで幕を開ける。不確かに不機嫌に空間が揺れ動くような冒頭のその『Made in Hong Kong』に比べれば、続くアルバムタイトルトラックはもっと平穏で、しかし相当にアブストラクトでファンシーな音から始まっていく。観念としての“夏”の中を泳いでいくみたいなその感覚は、やがてコード感を纏う何かの響きを軸に反復していく。かと思えばそのコード感が途切れ、また曖昧さの中に放り込まれ、また遠くからコード感ある響きがやってきて…といった展開を様々なノイズと並走しながら繰り返していく。そのコード感ある響きはずっとエフェクトが掛かり曖昧にされ続けるけども、4分50秒くらいで一気にクリアになり、その正体がギターのコードカッティングだったと判明する。最終的にはこの切なげな響きのコードカッティングが、漣めいた様々なノイズとともに反復して、この曲はゆったりとフェードアウトしていく。
思うに、ある種の“夏”の美しさというのは「輝かしくて、そしていつか終わってしまう」というところにあると思う*4。だからこそそんな切なくもいつか遠ざかってしまう“夏”が何かによって永遠に続くこと、「終わりなき夏」という非現実的な夢想に、どことなく甘美な儚さを覚えてしまうものなんだろう。その点でこの曲の、切ない二つのコードの反復をノイズの海に沈めたり浮かび上がらせたりで展開していく手法は、その「終わりなき夏」というモチーフに手法レベルで寄り添っているようにも感じられる。少なくとも、この曲の間に攻撃的なノイズがそこまで含まれず、基本的にどこか曖昧な安楽さに包まれているのは、そのような甘く儚い「終わりなき夏」という概念へのリスペクト故だろう。作者はそこに、攻撃的なノイズの必要性を認めなかった。“夏”って本当に幻想を呼ぶモチーフだなとまたまた思う。
6. サマースナイパー / くるり(2001年)
くちびるが切れた よそ見してたら切れた
だってそこの海は綺麗すぎた
予定調和を求めるこの旅は この辺で終わりましょう
今以上声は遠くなっていくばかり ごめん許してね
大事なグラス あなたの手から落ちた
僕らは夏のスナイパー
『ワンダーフォーゲル』というある程度いち時代のアンセムになってた曲*5のシングルのカップリングにひっそりと収められつつも、この野暮ったいフィーリングに溢れた楽曲は、くるりというバンドがいつまでか持ってた独特の「学生の延長っぽいモラトリアム感覚」を、"夏"というテーマを絡めて絶妙に気だるく野暮ったく放つ、もうその道で隠れた名曲と読んで疑いないものだろう。いやいや、こういう類の野暮ったさを一時期みんな出したがって出せなかったんじゃないか。
バンジョーを用いて、それで爽やかにカントリーを演奏したのが同時期の『リバー』なら、こちらはもっと貧弱に卑屈にマイナー調で、うだつの上がらない出口も見出せないままだらしなく過ぎる夏を、エレクトロ要素も交えつつ絶妙に捉えたナンバーだと言える。カントリーならウォームな響きになるバンジョーがここでは実にそっけなくボソボソと鳴っていて、それだけでもちょっと面白いのに、この曲は絶妙に情けない情緒で、かつ少しジャジーにメロディを紡いで展開させていく。案外丁寧にAメロBメロサビと展開し、最初は埃くさい雰囲気たったのが段々勇敢さを蓄えていき、でもサビも絶妙に突き抜けきらない。この辺はおそらく的確に計算されてそうなっていて、それが岸田繁のどこかヘナいボーカルと素晴らしくマッチする。
特に素晴らしいのは2回目のサビの後、様々なエフェクトを交えながら、学生の夏休み特有の何の理由もなしに世界観が広がっていくような感覚が溢れた後、バンジョーと歌のみの実に心細いAメロに着地するところだろう。このひもじさの感覚を他の誰が出せよう。このままもうそれ以上メロディが展開せずにそのまま終わってしまうのも情けなくて愛おしい。これは偏見だけど、学生の夏はこれくらいうだつの上がらない雰囲気の方が魅力的に感じたりしてしまわないだろうか。いやこの曲の作者は卑怯なくらいメチャクチャ器用なことやってるとは思うけども。
7. Summer Turns Too High / R. E. M.(2001年)
ワインとツバキモモを摂った後に
蛍たちがやがて 甘美な諦めとともに
夜空をシロップみたいに飛んでる
あったかもしれない可能性に患うことなんてない
ぼくは夢中になってる
夏は高まってく
夏は高まって高まって 大いなる夏
エレクトロ要素を導入したこの時期のこのUSインディーの王道を行くバンドが、ここでそのエレクトロ要素をThe Beach Boys的なポップソングのフォーマットに注ぎ込んでくることは、上のFenneszといい、翻ってThe Beach Boysってそんなエレクトロな音楽だったのかと、もとい、それほど抽象的な音が似合う、スピリチュアルな音楽してたんだなあということを後の時代から照射することで証明していると言える。まあここはR. E. M. の話をすべきところだからThe Beach Boysのことはそこそこにして。
とはいえ、こういう場面で咄嗟に夏の曲の要素としてThe Beach Boys的な要素をサッと出力することができるのは、オルタナ世代の大御所としての実力と責任を何が何でもクソ真面目に背負ったバンドの大人としての手管の充実具合を表していることは間違いない。そして、その本来弾けるような若さとともにあったようなポップセンスをこの曲の歌詞のように、中年の視点から過去の夏を振り切って今の夏を静かに楽しむような、実に渋い情感に落とし込んでいるのは何か象徴的な感じがする。The Beach Boys的な三連のリズムと突き抜けるようなコーラスワークとで、実に落ち着いたメロウなノスタルジーをサウンドとして作り上げ、しかしそこに乗る歌詞は案外懐古的でない、というこの取り合わせは、いかにも「現代に生きる人間」ということを自覚的に考えてやってきたクソ真面目なバンドっぽい在り方のような感じがする。
8. Sea of Teeth / Sparklehorse(2001年)
金星の風をその肌に感じるかい?
夕暮れに死ぬほど赤面するような慕情を味わえるかい?
星たちはいつだってぶら下がってるんだ
夏が隠し持つ血の吹き出す牙の中で
この曲が収録されたアルバム『It's a Wonderful Life』は、外部ゲストが多く参加した関係もあってなのか、これより前の作品に目立ってたザラザラなギターとチープなリズムとシャウト、みたいな曲*6の存在感がかなり後退し、もっと落ち着いたSSW風味というか、割と普通に王道なプロダクションでもって、彼の憂鬱さしかないような世界観を編んでいる。それが逆にユニークなところなのかもしれないし、または中心人物Mark Linkousが、他者との関係性が増えていく中で自身のエゴがどんどん希薄化し曖昧になっていくのをそのまま音に出そうとしているようでもある。
この曲はそんな曖昧化の流れの中でも一際曖昧に茫洋とした視界をそのまま音にしたかのようなスケール感がある。はじめなんだこれは…?と思うようなヘンテコなアコギのリフの反復が、ゆったりしたリズムとそしてタイトルどおりの海の感じを思わせる雄大なピアノが現れることで、波上を流されていく小枝のような心細い存在に移り変わっていく。歌の存在感も、言葉数が少ないこともあってかなり曖昧気味で、まるで音響派の作品のような感覚がある。歌詞の中では金星と木星の名前が不思議な形で登場し、そしてどんなに落ち着いた楽曲にあろうとせめて言葉としては彼自身的なむごたらしさを表現しようと妙に剣呑な言葉が入り込んでくる。それは音と言葉によって、この世界はなんか曖昧にぼんやりと美しいのではなく、無数のおぞましい様々な事柄を含みながらも、たとえば宇宙から眺めてみたりすれば、なんかぼんやりと美しく見える、みたいなことを思わせる。そのような星たちが、なんか残忍そうとはいえ夏の中にいる、というのは、案外彼も夏というものに「ただの盛りの時期」以上のもっと根源的なファンタジーを感じていたんだろうか。
9. Re-残暑 / クラムボン(2002年)
真夏に夏を忘れてはしゃいだ 変わらない二人を信じて
似合わないミュールで背伸びして歩いた
とびきりの二人になりたくて
9月の夏をはじめて知った 陽炎に揺れる東京
新しいヒールで階段を駆け上がる 二人で見た夏を探して
目を閉じても それでも消えない 眩しい光
もう一度会いたい どこにどこにいるの
もう二度と会えない たぐりよせる引力を
わたしに わたしに 今わたしに
今回のリストの3つある長尺曲の3つ目にして、シングルの時よりもずっと尺もスケール感も膨大なものになった、本人たちもこのバージョンこそをこの曲の完成形と思ってる節があるように感じれるトラック。シングル版はいきなり歌いはじめで、サビの強迫観念的な圧迫感などが、よりスムーズにポップな『サラウンド』の後塵を拝した感があったけども、この長尺とアルバム『id』以降的なミニマルでポストロックなアレンジをもってその楽曲自体のエネルギーをようやくのびのびと放つことができた形か。
この曲の元から持っていたエネルギー、それは「ある恋が終わってしまったのを夏の終わりとともに名残惜しく振り返る歌」であるところのはずのこの曲の歌詞は、しかし本当に「終わった恋を名残惜しく思う」だけに留まるほどのものしか求めていないのか、ということで、「もう一度会いたい」をまるで叫ぶように歌い上げ、「たぐりよせる引力を」と強く希求するその様子は、もっと根源的に夏そのものを取り返そうとしているかのような強い情念を原曲の頃から感じれた。原曲の場合、この時期のプロデュースが亀田誠治というのもあってか、まるで椎名林檎ばりのエモーショナルさの音圧でこの希求が飛んでくることになっていたけど、このリメイクにおいては、延々と反復するピアノリフに乗せて過去の情景を曖昧に思い返していくうちに、サビの感情に至り、その後に「歌ではなく音として、全体のサウンドとして」この曲のピークが訪れることで、その強烈な希求が果てしなくファンタジックさを放出する形に置き換えられている。
1回目のサビのメロディの終わりを契機としてドラムの入りとともに飛び出してくるシンセのフレーズが、まさにそんな強烈にして鮮やかなエネルギーの放出の様の象徴だろう。ドラムが入って以降は楽曲の推進力がぐっと増し、まるで疲れも知らずにイマジネーションの中の夏を駆け巡るかのようだ。だからこそ、二度目のサビ以降にさらに演奏が展開していき、明らかなひとつのピークに達した後に微かなピアノリフだけを残して一度ブレイクするのはとても寂しげに思えるし、そこからまた最後のサビで一気にエネルギーが放出されていく様は、まるで一度終わった夏が再誕したかのような勢いだ。そこでは「夏の終わり」と「永遠の夏」というのは隣り合う概念なんだろうな、ということなどを思わせる。最後の演奏のピークが終わって様々なリフが名残惜しく残っては次第に消えていく頃には、いつの間にか8分を過ぎてしまっている。
ちなみに、この実に作り込まれたリメイクをどうライブで再現するんだろう、と思ってたら、上記の動画のとおり、3人のメンバーだけでほぼ再現してしまえてる。ピアノリフはサンプリングとかじゃなくてずっと生演奏なのか、とか、ベースが普通のベースの役割を放棄してる*7、というかあの特徴的なシンセの担当はお前なんか、とか、様々な驚きがある。
10. The New Cobweb Summer / Lambchop(2002年)
The New Cobweb Summer - YouTube
かつて ぼくにはある友人がいた
地理について彼の心に深く話し込むコツなど誰が知ろう
坊や そう思うだろ それは問題があるんだ
ハンターは眠ってる 少なくとも彼についてはそう呼ぼう
新しく蜘蛛の巣が貼った夏の その午後に
ナッシュビルを拠点に大所帯で活動するオルタナカントリーバンド、という括りでこのバンドを紹介して本当にいいのかいささか怪しい気持ち。カントリーの郷愁感を出発点にして、そのシックで渋みの香るようなサイケデリアによって、どこかの誰かのなんらかの記憶が鮮やかに蘇ってくるような、まるで、昔フランスの小説家プルーストが『失われた時を求めて』*8で行った「無意志的記憶」の感覚を音楽で実践しているかのような感じの音楽家集団、という感じだろうか。その手法においてはロックンロールは不要、すなわちもはやドラムも不要、との境地に至ったのかどうか知らないけども、2002年のアルバム『Is a Woman』はそんなノンビートの中を、優雅なピアノと滋養のみみたいな声を軸に練り上げられた作品だ。
あのアルバムは冒頭から6分越えの曲が3曲も続くけど、この曲はその2曲目に位置している。ずっと落ち着いた音が続くアルバムなので楽曲ごとの起伏は大きくないけれども、この曲は夏というタイトルが付いているせいもあってか、どことなく、とても静かなどこかの人気のない夏のリゾート地のような感覚がある。基本とてものんびりしたトーンでありながらも、メロディのセクションの変わり目で少し緊張感ある憂いの響きが入り込み、また歌メロが穏やかにルート音に帰着した後にはちょっとばかり賑やかに演奏が空間を彩ってくる。2回目の歌が終わった後、ゆったりと同じ展開を歌無しで、楽器それぞれの響き重視で繰り返し終わる頃には遠くからサックスの2音の繰り返しがより出所不明のノスタルジックさを醸し出してくる。上記の歌詞はそのあとから始まる最後のセンテンスのものだけど、“afternoon”という単語を歌うときの切り方の絶妙に儚くもエロティックな感覚は本作の研ぎ澄まされ方の象徴かもしれない。そして「新しく蜘蛛の巣が貼った夏」という、夏に対してもはやなんの興奮も抱かず冷め切った姿勢である事の表現が、この後の実に幻惑的な演奏との対比として美しい。いやむしろ、記憶というのは蜘蛛の巣が貼ったくらいの方がより曖昧に美しくなるもんなのかもしれない。
11. 野いちご / 野本かりあ(2002年)※
野本かりあ - Wild Strawberries [Karia Nomoto] - YouTube
夏の朝の 寒い朝の 霧の中を ふたりドライブした
誰もいない 何処かの街 海のちかく ずっとドライブした
とぎれとぎれ ラジオの音 いつの間にか 遠くまで来たの
寒い朝は抱き合って くちづけをするのが 当たり前になるの口の中にひろがるのは 野いちごの味
夏はすぐに終わるのに
ここでふたりはまだ 恋をしてるなんて
子供みたい 乱暴なキス 野いちごの味
Pizzicato Fiveの夏の曲を1990年代のリストに入れるのを我慢しただけの価値が、この小西康陽プレゼンツのPizzicato Five時代の楽曲のリメイクには存在する。というか、化粧品のCMめいた原曲の雰囲気が逆になんだったのかというくらい、この曲のこのアレンジは緊迫感に満ちた緊張感と、そして見事に美しくゴスな具合に閉じたひと夏のファンタジーを描き出している。夏なのにゴスだって!?一体何が起きているのか。
サンプリングのせいで決まったフレーズしか出てこないトラムとフィルインとストリングスフレーズ、野宮真貴以上に徹底して無感動気味に歌われ、ダブルトラックで僅かに残った人間らしい情感もしっかりと殺されたここでの野本かりあの歌、そして「夏の朝の 寒い朝の」という歌い出しの、「夏の歌」としてありえない、考えられないようなシチュエーションの夏描写が、この曲の奇妙に突き抜け切った異様さ・スッキリした禍々しさを構成する。一般的な夏らしいエネルギッシュさ、汗の感じなど、そのような"不純"なものはこの曲の中ではまるで存在を認められず、ただひたすらに、この奇怪で壮絶な演劇めいた閉じた世界の要素だけが寒々しくも美しく響いてくる。
これはもしかして"夏"を"冬"に変えた方がまだ意味は通るんじゃないかと、そんなことも思いはしたけども、でも最後の方の歌詞の、まるでロマンチックで非実在的な"夏の世界"に置いて行かれたかのような感覚は、やはり夏だからこそ、という気もする。もしかしたら小西康陽の最高傑作かもしれないこのトラックを前に、夏の歌と思えない緊張感にいつ聴いてもゾクゾクするようなら音と情緒を前に、夏というものがなんなのか、全然分からなくなってくる思いがする。こんな夏の曲があってもいいと、いや、こういうゴスな夏の曲がどうしてこの世に他にそんなにないのかと、密かに強靭な作家性が叫び続けているのかもしれない。
小西康晴楽曲についてかつて色々書いたことがあり、この曲もその際に取り上げてたのを思い出した。結構昔になってしまった記事なのに、その頃から趣味が全然変わりやしない…。
12. Heavy Metal Drummer / Wilco(2002年)
ああ あのヘヴィーメタルバンドたちが懐かしい
夏が来るとステージを観に行ったりしていた
あの娘はそのドラマーに恋をした
あの娘はそのドラマーに恋をした 恋をしてたな
ギラギラしたズボンに脱色したブロンドヘアー
夏の川辺にツインペダルのドラマー って取り合わせ
あの娘はそのドラマーに恋をした
それから他の また他の奴と恋をしていた
ぼくにも判るあの手の純粋さ もはや愛おしい
KISSのカバーをしてたね 美しくてラリったんだったね
世界中でもとりわけタフなロックバンドとして活動を続けるWilco*9の、もはやロック史に定着した名曲のひとつとさえなっているかもしれない、必殺のポップソング。冒頭のまるでサンプリングかのように硬質かつインパクト大で響くフィルインをきっかけに、あとはひたすら爽やかに、かつボーカルやメロディ含めての程よい渋みと、情緒が熱し過ぎないよう程よくシンプルにコード進行をまとめられたフォーキーさと、そしてこの曲では隠し味的に効いた収録アルバム『Yankee Hotel Foxtrot』特有の不思議なシンセサウンド等とが、絶妙に風通しの良い奥行きを作っていく。サイケすぎもせず、素直すぎもしない、上手いこと乾いたノスタルジックな質感が、シンプルにして必殺なサビのメロディをフックとして駆け抜けていく。
この歌は夏フェスか何かで昔見た純真なヘヴィーメタルバンド*10の光景をノスタルジーの対象にしている。バカっぽいものへの憧憬、それに対してシニカルになってしまう自分への若干のヘイトも混じったその感覚は、別に何か物語が強烈に動くような情緒の動きでは決してなく、ふとした瞬間になんとなく湧き出してきた記憶とそれに対するなるべく嘘偽りなく綴ろうとした心情だろう。その、何某かのシニカルさを前提にした素直さの表出というのが、この曲に漂う類の爽やかさにおいてはとても重要なものだと思う。
なお、『Yankee Hotel Foxtrot』は筆者にとっても大変特別なアルバムだったので、全曲単独記事でのレビューをかつて書いています。もう結構前のことになってなんか懐かしい…。コロナ禍でなかなかできなかった来日公演が、新作を提げて行われる予定らしいので、ぜひとも行って、絶対演奏されるであろうこの曲を合唱したりとかしたい。
13. Summer Gypsy / Nujabes(2003年)
Nujabes - Summer Gypsy [Official Audio] - YouTube
“ローファイヒップホップ”という語に非常に遅まきながら少し興味を持った際に、J Dillaとともにその源泉となった存在として、やはりもうこの世にいないこの日本人DJの作品に触れることになって、あっなるほど、これくらいギャングスタとか闘争とかそういったものを一切脱臭脱色した、ある種とても日本的な洗練の仕方をした、もはや化粧品みたいになったヒップホップを、ローファイヒップホップは元にしてるのか、と少しばかり得心した。ヒップホップ本来のもっとドロっとした攻撃性なり混乱仕草なりのエネルギッシュさとはローファイヒップホップはあまりに対照的で、どうしてこんなのを“ヒップホップ”と呼ぶんだろうと思ってたので、そのミッシングな部分が繋がった気はした。
ローファイヒップホップといえばラップの入らないインストもの中心の世界だと思われるけども、Nujabesの作品はラップ自体は結構入る。英語で、誰がやってるのか分からないくらいヒップホップ的なエグさを徹底的に抜かれたスムーズさがそこにはあるけども、それでも人の声があるかないかは結構曲の感じに影響する。この曲はラップは入っておらず、ずっとうっすらとメロウな感覚が展開もせずにループし続ける。涼しげに響くアコギの音や遠くで鳴るメロウなラインのシンセなど、この曲がこのタイトルであることの必然性を感じさせる要素が入っていて、なるほどこのトラックはもしかしたら「夏=チル」みたいないつの間にか定着した文化の成立に少しばかり貢献してそうだと思った。こういったものが様々に寄せ集められネットで共有される*11ようになってはじめて、「夏=チル」って感覚が生まれてきたのかもしれないな。その感覚をなんとなくは理解するものの身体の芯に染みるほどに深く感銘を受けてはいない。でもそのくらいのライトさの方がチルという概念にはいいのかも。チルに必死になることはチルじゃねえ、みたいな難しさがチルにはありそう。
14. 通りすぎただけの夏 / ゆらゆら帝国(2003年)
小舟が風に吹かれて だんだん遠ざかる長過ぎた夢がさめた 無言で夏が終わる氷がグラスで溶けた 2, 3回かきまぜる夕暮れそろそろ僕は 消えるよさりげなくそこで出会えた人 そこで別れた人通り過ぎただけの人 いろんな夏が終わる
どうしても2007年の最終作『空洞です』の存在感が絶対的すぎ
じゃあこの曲が昭和のムード歌謡とどう違うのか、ということだけ
もうひとつ言えば、歌詞の面でも圧倒的にソリッドである。
それにしても、そんなに多くない言葉数で実に端的に「夏の意味も
15. Will the Summer Make Good for All of Our Sins? / múm(2004年)
※割と生理的嫌悪感を催す感じの映像なので閲覧注意
歯にハンマーが当たったからと泣かないで
下に溜まった可憐な雪を台無しにしちゃうよ
それに 夏はわたしたちの罪の総てを償ってくれるでしょ
ただそのことを十分に強く希うならば
息 貴方の吐息 誰が行くの 誰が泣くの
夜まではきみとぼくを信じて
息吸って 吐いて 償って 浮遊して
きみやぼくの血を流して きみは違う
彼女は泣く 目を閉じて 戻らなくていいよう願って
エレクトロ勢が“夏”に目をつけ始めたのがどこなのかその割と初期らしいものをこの一連の記事ではうまく把握できなかった。ハウスとかテクノとか辺りにありそうなもんだけども。イマジナリーな夏のサウンドスケープにエレクトロはとてもよく合ったジャンルだと思われ、もう少し後の年になればチルウェイブとかも関係してくるところと思われる。ところで、ヨーロッパでもとりわけ北の絶海の孤島のような場所に位置するアイスランドではポストロック・エレクトロ系アーティストを多く輩出しているけども、このmúmについてはそんな北国にありつつ、というかだからこそなのか、妙に夏に拘っている節があり、“summer”の語が入ったタイトルのアルバムを2作連続で出している。2作連続で夏ってタイトルに入れるアーティストはそんなに多くないだろう。今回の曲は2004年の『Summer Makes Good』に収録されているけど、じゃあ作品が夏っぽいチルな、くつろいだフィールに溢れてるかというと全然そうでもない。いかにも北欧的な、寒々しい光景が思い浮かぶようなサウンドをしている気がする。まあ色々な夏があってもいいので、こういうのも夏のイメージを広げてくれるだろう。
でこの曲。やはり、晴れ切った雰囲気になることのない荒涼として鬱屈したコード感が連なり、音の質感はいよいよテープの古くなった映画じみたボロボロ調子になり、そして作中あちこちで聴かれたのと同じ、子供じみたウィスパー気味なボーカルのゴスな雰囲気、こういったもので編まれたその音響は、いよいよ「どこかの国の哀しげなホラー映画」みたいな情緒を思わせる。いったいこの音のどこが夏なんだろう?と音だけならば首を傾げてしまうけども、歌詞の方も読むと「それに 夏はわたしたちの罪の総てを償ってくれるでしょ」というくだりで、ああ、ここにおいて“夏”というのは、冷たく厳しい、まるで原罪のように降りかかる冬から、人々をひとときの間“赦し”を与えて解き放ってくれる存在なんだなと、その文化的な立ち位置の本邦などとの違いを認識することができた。そうか、ある土地、ある場合においては“夏”はその存在自体が救いにもなりうるものなのか、と、言われてみればそりゃ当たり前のことだな…とも思えるけども、改めて気付かされた。
16. Fortress / Pinback(2004年)
秋までは長すぎるよ ベッドで送る病んだ夏
きみ そしてだるいムード 秋の10倍くらいの
長引かせられ クビにされ ぼくは間違ってきた
誰も動いてくれないさ 誰も動いてくれない
落ちてくには長過ぎかな ベッドに座り震えてた
きみ そして意思のテスト 落ち過ぎだし 失敗し過ぎ
誰も動きはしないさ 誰も動きやしない
電気が消えて凍りつく日々 きみとぼく 不安 青ざめて
待てよ もう遅えよ ウンザリだわ
要塞のかけらも見えねえ 要塞のかけらも見えねえよ
夏なんて きみといるとただただ冬
ねえ マジでどう感じてんのかね
二人の他人 ペアではないねぇ 誰も動かねぇ 誰も動かねぇ
ギターをコードを大味に掻き鳴らす楽器ともワイルドにフレーズを
果たして、満を辞して歌詞に夏が出てくるこの曲は、典型的に単調でメランコリー気味なワイヤー動作めいたギターフレーズがスカスカな空間を作り出す。主に二つのフレーズで構成され、それぞれが曲のセクションによって出たり入ったりする構成になっているのはアレンジとして思い切りが良くて興味深い。そしてその中で、せっかくのダブルボーカルなのにまるでどっちも死んだ目をしたようなテンションのPinback節な歌も、いい具合にダウナーなメロディを展開していきながら突如サビでシュールな歯切れの良さを見せる。リリカル一辺倒という訳でもない、なかなかにヘンテコな曲だ。そして上記の歌詞翻訳を読んで貰えば、「奈落の底の夏」というアルバムタイトルを地で行くこの曲が、アルバム内でも軸になってる曲なのかなと思える。「要塞のかけらも見えねえ」というのがどういう意味なのか明確ではないけど、ぼんやりとなんらかの失望めいた言葉なことは分かる。関係性の冷え込みでウンザリするような様子の“夏”。これじゃまるで「世間一般の楽しい夏」に対する当てつけのようだ。「ようだ」じゃなくてそのものな感じでやってるのかもしれないけども。でもまあそういう酷く虚しい夏だって世の中いくらでもあるよなあ。そしてそういうものでも気兼ねなく出せるのがインディーロックという磁場の自由さなんだと信じ続けていたい。
17. 朱い夏 / advantage Lucy(2005年)※
Advantage Lucy - 朱い夏 - YouTube
光と陰 過ぎてゆく日々は まだ 眩しく
降り続く雨 僕はただ ただ 朱い夏を待っている
光と陰 過ぎてゆく日々は まだ 優しく
ほどけた午後 僕はきっと きっと 朱い夏を駆け抜ける
歌詞はたったこれだけ。構造的に言葉数をメロディに対して詰め込みにくい日本語であることを差し引いても、サビ的な箇所を全部言葉なしのハミングのようなもので済ませてることを考えても、これは少ない。いかにメロディに対して無理に言葉を詰め込まず、伸び伸びと歌を構築してるかの証か。思えばadvantage Lucyはスーパーカーとかpre-schoolとかWINOとかと同じ括り方で“スニーカー系”なるなんか分かるような分からないような呼ばれ方をしていたりもしてたけど、そんなカジュアルそうな割には、日本語詞を英語っぽく気取った発音や載せ方*12をせずに、野暮ったいくらいに確実に1音に対して1つのひらがなを載せる形でメロディと言葉を編むバンドだった。その割には英語詞の曲も並行して歌う、という不思議なスタンスにも案外独特なところがある。
野暮ったさをきっちりと音楽にできる、というのは大きな才能だと思う。義務教育の中で音楽室で学ぶ歌か?みたいな曲から、洋楽を齧ったりして自分も音楽を作ろうとする人は離れたがるものだと思う。けどそうはせずに、しっかりと自分のルーツを月並みであろうとも恐れずにそこに見出して、捻くれることもなく真っ直ぐにメロディを編み続けていく様は本当の“純真”めいたものが感じられる。この曲が含まれたアルバム『Echo Park』自体がどこかそんな感じが程よい寂しさと並走する名作だと思っているけども、その中でこの曲の牧歌的なメロディの載せ方は実に、メロディ構成の純真さに磨きをかけたような形だと思う。「過ぎてゆく日々は まだ 眩しく」というラインに夏の終わりを感じさせつつ、そこに過剰なセンチメンタルを置かずに代わりに夕暮れの薄暗がりのようなハミングのパートでスルーしていく様は、日本語的な純真さとチルな感覚の和やかな折り合いのようでさえある。
18. Summer Skin / Death Cab for Cutie(2005年)
軋むブランコ 背の高い雑草 今までで一番長い影たち
水は暖かくて 子供たちは泳ぐ
ぼくらも夏の肌をしてはしゃぎ回った
不安のひとつも覚えてない 草木と湿度しか
そしてレイバーデイが来て 去って
ぼくら 夏の肌の残ってたのを脱ぎ去っていった
このバンドがどうしてエモで括られるのか理解しづらく思うのは、筆者が2003年の名作『Transatlanticism』やそれ以前の作品のような、まだギターがいくらか荒ぶることのあった作品からではなく、そういうのから密かにかつ格段に離れた感のある2005年の『Plans』から入ったからかもしれない。熱情の迸りよりも静寂の中の微妙な高揚の表現を好み、同じメロディが延々と繰り返されるオンリーの構成をも全然恐れないこの作品を、かつてのエモバンドの延長として期待してたであろうリアルタイムのリスナーはどう捉えたんだろう。筆者はそういうのがないから、「叙情派なんだなあ」くらいの適当な理解をしてたような気がする。
この曲もまた、派手な高揚感とは無縁の、延々と同じメロディを繰り返して、その中の微妙な感情の起伏や歌の間の演奏の奥行きに漂う寂寥感こそを味わうことこそをバンドが意図してるとしか思えないタイプの楽曲。彼らの演奏の凝ったアレンジは、しかしどこかプロフェッショナルすぎるのか大味な部分がなさすぎるのか、あまり評価されてる感じがしない。この曲だと特に、わかりやすく抒情的なピアノの間の空いた配置の中で時折メインリフと呼べそうなリリカルな旋律を挿入するベースの動きが興味深い。その心細い停滞感のうちにいつの間にか楽曲が通り過ぎてしまう様は、タイトルにあるような「いつの間にか夏を脱ぎ去ってしまう」みたいな感覚に寄り添っているようにも思える。「レイバーデイ」というのはアメリカの労働者の祝日で、これが9月4日なので、これが来る頃には夏の終わりが現れてくる、ということらしい。さて、日本の夏は世間的にいつ頃終わるのか。シルバーウィークあたりか。
19. Evening Sun / The Strokes(2006年)
別れ道を行きなよ いつかきみは戻ってくるだろう
そしてぼくは陽に焼かれることを夢見ることだろう
べつにきみの心を二つに割いてしまいたい訳じゃない
半分は取っておいて もう半分をぼくにおくれ
夏は好きだ 夏が恋しくてつらい
教えてくれ 何がしたい? 何もない? ぼくもさ
役者たちは装い続け シンガーたちは時折嘘を吐くだろう
子供たちはいつも正直 いつか死ぬなんて考えもしないから
ああ きみはチームの中でも最も可愛く 最も賢いね
他の17歳の生き物の誰よりも愛してるよ
夕日の中で 琥珀色の夕日 夕日の中で
縛りプレイのようにチャチなツインギターとグルーヴをあえて選択してロックの解体再構築を果たさんとしていたニューヨーク発のこのバンドがどうしたことか急に革ジャン式のロックンロールに目覚めてしまった感のある3rdアルバム『First Impression of Earth』だけども、中には結構従来的なスカスカさの中に独特の緩急を追求した楽曲も結構あって、ただ、そういう曲は格別のキャッチーさが無いと地味なもんだから、リアルタイムで聴いてた時は良くも悪くも目立つ前半のワイルドに転じた楽曲の陰になってそういう曲の良さには気づかなかったなあ…という言い訳。
アルバムラスト前に置かれたこの曲はまさにそういうタイプで、最低限の歪み、モジュレーションや空間系のエフェクトほぼ無しのほぼ素の音なエレキギターとシンプルなリズムの、熱量を感じさせない刻むような演奏の合間に、どうしたら曲タイトルのような淡い情緒が浮かぶかをサウンドとして挑戦している。スカスカの演奏はすぐにオフの方に引っ込めることができ、ヴァースの淡々とした様子からコーラスの少し情熱的でかつ不思議に強引な転調をして上がり、そして同じコーラスのうちにまた転調して下りと、地味に結構ひねくれたことをしていて、まるでこの曲がストレートな良さに陥らないよう慎重にコードを編むかのような様子だ。その乱された抒情性の中を、このバンドのボーカル特有の熱っぽさと少し感傷的な低音との的確な使い分けが貫いていく。
この二つの繰り返しの構成は安定し過ぎているためか、この曲にはミドルエイトが投入され、それが上記の歌詞抄訳の部分。この曲でもとりわけコード進行が妙なことになっていて、その中をグダグダながら強引にメロディを通していくボーカルによって語られる言葉もまたどこかグダグダな様子だけども、投げやりのように夏に対する愛と嘆きを語り、どこか捨て鉢のような言葉を吐いた後に元のメロディに戻る様にはちょっとしたカタルシスが確かにある。その後のどこか皮肉と諦観が浮かぶ歌の様子からしても、ミドルエイトの歌詞の感情が滲み出す雰囲気はなかなかに演出されている。
20. Long Forgotten Song / The Thrills(2007年)
男子なら誰でも誘惑にかかり どんな手でもきみを追いかけた
夏が来て 夏が過ぎ
ちょっとの間女子たちに視線を費やしてた日々を呪うんだ
長く忘れられてた歌を知ってる でも皆 まだ一緒に歌ってる
ああ そんな前のことじゃないのに 皆 手放すことを学ぶんだ
旧い運河に撥ね付けられ 雨が石畳に激しく降り注いだ
君が身を寄せる教会がある 風が強く吹いた 風が強く吹いた
どこを見回しても 美しい建物が壊されていく
どこを見回しても きみの顔が見えてしまう
アイルランドの地からカリフォルニアをひたすら憧れ焦がれ続けたバンドだった彼らの最終アルバム『Teenager』はそれまでのカントリータッチから離れ、ストレートなチェンバーポップめいたものを志向し、そのアルバム名が示すとおりの青春讃歌でありつつも、それが通り過ぎてしまったことの痛みをともかく引き受けまくった、それまでよりもグッとカラフルになったサウンドとは裏腹の相当な痛々しささえ漂う、そんな壮絶さまじりの荘厳さが魅力の作品だ。この作品がそこまでヒットせずに、それを受けてバンドが解散してしまった事実があることも含めて、その悲壮感が立ち上ってくる。このバンドのボーカルの、永遠に純真で幼いままみたいな高い声質が特にそういう思いを焚き付けるのか。
この曲なんかタイトルからして「長いこと忘れられてた歌」なんていう、実に世知辛い切なさが漂うもので、そしてそのとおりの、どこか悲痛さを抱えた乱れた高揚感が楽曲を貫いていく。ヴァースの箇所ではメロディというよりも、情緒の混乱をそのまま叩きつけるかのようなボーカルで、声質のせいなのかBob DylanとかLou Reedとかみたいなシックさなど微塵もなく、「情緒が混乱してるんだなあ」というのが素直に伝わってくる。「夏が来て 夏が過ぎ」なんて具合に、実に当たり前のようにあっさりと通り過ぎていく夏。そのこと自体に、おそらくはこの歌の主人公は何か耐えられない思いをしているんだろう。
そこからの、気高くもやはり悲壮感が滲むサビのメロディの高揚はシンプルに効くものがある。しかし、それさえまるで前座だったかのように、よりリズミカルに混乱した調子で言葉を畳み掛けつつ、作者ならではの「熱が通り過ぎてしまうことへの絶望」が詰まったミドルエイトが挿入されて、それが最後息も絶え絶えのようにメロディが途切れる様が実に、本作の悲壮感の象徴のような感じに響き渡る。
21. All The Years / Beach House(2008年)
All The Years - Beach House (OFFICIAL AUDIO) - YouTube
わたしのする献身すべて 海にせっつかれてたの
これから来る年月全部の 年月全部 全部 全部 全部の…
だから 夜が明けるまではたらいてようね
わたしたちの夢がみんな かつてどんなだったか
家事をみんなやって 教科書ぜんぶ返却して もう一生
その灯りは絶対終わらないみたいなフリでいこうね
そしたらまだわたしたち夏できるんだ
仲良くしてようね イェーイ
その名前の割にどの辺が「海の家」なのかよく分からない音楽性を持っているこのドリームポップユニットは、しかしドリームポップにしてもアッパーなサイケ感は薄く、どこかシュールでひねくれたところが目立つ。2010年前後にやたら出てくる「Beach」的な名の付くガレージバンド群とは根本的に違う存在だとは思う。デビューアルバムの2曲目で唐突に冬の東京で麻雀する場面が出てくるアメリカはボルチモア出身のドリームポップユニットって時点で相当にシュールだもんな。そして調べた限りその1stに夏の語が入った曲はなかった…2枚目でようやく見つけたくらい、夏について拘ってる風ではない。
とはいえこの曲のサウンドにはどこか夏の空気ごと熱波で蕩けてしまったかのようにトロンとベンドするリード音が採用され、低いテンションでしかし仄かに淡く甘いメロディが伸びていく様は、少しばかり夏っぽい感じもあるかもしれない。それにしても夏を楽しんでる感じなんてしないけども。夢見心地と言っても、それは清々しくクリアなものではなくて、大概濁っている性質のもので、一度だけ登場する少しばかりドラマチックなメロディの箇所に乗るアルバムタイトルのフレーズでさえ「海にせっつかれてた」からやるようなものらしく、真剣に捉えるべきような気も少ししつつ、あまり考え込んでも無駄なような気もしつつ。でも「その灯りは絶対終わらないみたいなフリでいこうね /そしたらまだわたしたち夏できるんだ」というフレーズはどこか皮肉めいていつつも、でも実際そうかもしれないねとは。その灯りは絶対終わらないっていうフリすらできなくなった時に、ある種の夏は終わってしまうのかもしれない。何故だか夏が終わることを惜しむあまりに、終わったってもうはっきり判ってる灯りを点いてるフリをし続けるのは、さまざまな大小のスケールで普通に行われてることかもしれない。
22. Sailing Round The Room / Emmylou Harris(2008年)
Emmylou Harris - Sailing Round The Room - YouTube
人生はでも ただの夢に過ぎないのかも
わたしは流れをボートでくだっていた
別の岸辺で目覚めるために
かつてなったことない何かに落ち着くんだ
オクラホマの平原に降り注ぐ夏の雨になれるのかもね
世界を自身の向こうに置き去りにしたりはしないよ
見渡してみて きっとわたしを見つけるから
だから部屋の周りを航海してく 窓越しに 銀色の月を超えて
わたしに寄り添う肉も骨もなく 最後にはこの魂を解放するさ
部屋の周りを航海する頃には
Neil Youngなどと同世代の、つまり1970年代に活躍したアーティストの多くはそれこそNeil Youngなど一部を除けば1990年代以降にはもう引退状態になったりすることがままあった。カントリーロックの伝説であるGram Parsonsとの共演で名を挙げカントリーシンガーとして1970年代に活躍したEmmylou Harrisは、しかし1990年代以降にU2等のプロデュースで知られるDaniel Lanois等との共同作業によりU2的な空間的なエレキギターが歌とともに奥行きを作り出す不思議なカントリーロック作品『Wrecking Ball』を発表し、時代を跨いで作品を残した。そのような作品をあと2枚ほど残していると今度は時代が巡って“アメリカーナ”という銘柄でカントリーの再評価も大いになされていき、その後彼女としては2枚のオリジナルアルバムを残している。
この曲はそのような流れの中で、もうエレキギターを空間的に鳴らすことをせずとも「現代的な音楽」として蘇った旧きカントリーロックスタイルの、その滋養に長年活動し続けてきた貫禄が乗り、そして上記抄訳の歌詞のとおりの、まるで死後のことを想うような歌が、この曲の朗らかなメロディと演奏に、土に還るかのような情緒性を付加している。それにしても、この曲の辛うじての夏要素である「夏の雨になる」というのは一体どういうことなんだろう。オクラホマといえば雷雨と竜巻がよく発生するらしいけども、そんな激しいものになりたいわけでも別にないのかもしれないし冗談混じりにそうなのかもしれない。アメリカの歌の地名が出てくるときのフィーリングってなかなか分からない、それは残念ながらずっとそうだ。でもなんか「夏の雨になる」ってちょっと剽軽な感じがして良さある気はする。
23. 若者のすべて / フジファブリック(2008年)
真夏のピークが去った 天気予報士がテレビで言ってた
それでもいまだに街は 落ち着かないような気がしている
夕方5時のチャイムが 今日はなんだか胸に響いて
「運命」なんて便利なもので ぼんやりさせて
最後の花火に今年もなったな
何年経っても思い出してしまうな
ないかな ないよな きっとね いないよな
会ったら言えるかな まぶた閉じて浮かべているよ
1曲くらいベタな曲を入れときたいと思った。リアルタイムで聴いた時は変なシングルが2曲続いたあとにこれだったので「急にまともな曲出すなあ」と思ったけど、それが作者兼歌い手の死んだあとしばらく経った頃に急に「あの時代を代表する名曲」みたいな扱いになってて面食らったりもしたような、それで割引いて見てしまうところがあるかもしれないけども、それでもやっぱりいい曲なのは否定しようがない。
この曲が入ったアルバム『TEENAGER』全般にもかなり言えるところだけど、それまでよりも歌っている情緒の内容がより「普通に暮らす若者たちの思いや光景」にフォーカスしている。そんな方向転換の最中で急に「若者のすべて」なんてタイトルをぶち上げるのは挑戦的だけど、なんというか、割と「普通の人」になれなかったであろうところのある志村正彦という人が「普通の若者の光景」に向かっていこうとする努力は、どこかそれ自体になにか感動的なところがあって、夏の終わりが見えてくる瞬間にしばらく前の感傷のことを思い出す、そのどうにも冴えないような感覚が、しかしなんか劇的な風味があるような、というか単に日本人が花火に弱すぎるのか。
24. Graveyard Girl / M83(2008年)
死は彼女の恋人で 彼女は夏に唾吐き 夜に微笑みかける
黒バラで編んだ冠を集めていて でも心臓は風船ガムで出来てる
墓地な少女
闇色の絨毯と赤い星 彼女は高校の薄汚い魔女
サタンを父親のように崇拝し
でもMolly Ringwaldみたいな姉妹になるのを夢見てる
墓場な少女
聴いた順番が逆だったが故に、この曲を聴いた時「あっまさにGallileo Gallileiのサウンドと歌の元ネタじゃないのコレ!」とひっくり返った。煌めくギターと裏でオブスキュアーに反復するシンセの取り合わせ。結構そのまんまだったんだなあと、時間差で驚くやつ。M83はエレクトロユニットだと思ってたけど、思いの外ギターポップに踏み込んだこともやってて、これなんかどう考えてもエレクトロ要素よりもギターポップバンド成分の方が大きい。こんな甘酸っぱいギターサウンドをシューゲイザーじみた敷き詰め方をして、絶対そういう趣向の日本人が好きになる取り合わせだなあ。
それにしても、まさにオカルト系陰キャといった感じの女の子について歌った曲でここまでギターの音がキラッキラなのは、ギャップを狙ってるのが明らかだけどもそれにしてもエグいのでちょっと可笑しい。明るいメロディとコードとギターの音で一体何を歌ってるんだと。あまりに陽そのものなギターの音はシンセエフェクトをバックにともかく強調されていて、パートによってはこのギターとシンセの煌めき具合によってリズムの音まで掻き消されてしまうほど。ともかくこの、何もかもを超えて輝いて見せようとするギターの煌めきこそがこの曲の主役だと言っていいだろう。しかしだからこそ、そのギターが消えて、ドラマパート的な語りの後にブレイクなとこから、シンセのフワフワして暖かげのあるリフレインが聴こえたときの、なんともドキッとくる感じはとても甘い。青春めいた甘さだ。そりゃGallileo Gallileiもこういうのしたくなるよな。仕方がなかったんだ。
25. Summertime Clothes / Animal Collective(2009年)
スウィートな夏の宵 シーツを脱いだ 額に汗 エアコンの軋み
時計から声がして「きみは疲れやしないよ」
ベッドがプールで壁は火事 ちょっとばかり頭をシンクに浸せ
首が冷えて笑顔になるけど 骨を動かさなきゃ 肌は呼吸しなきゃ
きみが電話に出て めっちゃ安心したわ
きみは階段を降りて熱気あふれる街へ
太陽が僕らの足を滑りやすくさせてた
そしてきみと歩き回りたいな きみと歩き回りたいな
一緒にいよう さあ行こうね
Animal Collectiveみたいな奇妙なシンセポップ集団がよく天下を取ったもんだと改めて思うけどそれくらいには2009年のアルバム『』のリード曲はこれも『My Girl』もキャッチーで、アルバム全体で聴くと元来的な実験性の高さでよく分からん感じもあるけど、いくつかのキャッチーな曲によってジャンル外のリスナーにも聴かせるものがある作品とは思った。
この曲はそのシャッフルビートっぷりといい、夏のなんとなくだるい感じと楽しい感じが合わさった歌詞といい、妙にファンキーで剽軽でうわついたヴァースから派手なメロディの躍動を見せるコーラスへの移り方といい、彼らのシンセポップでThe Beach Boys的な「夏の何か」を目指した曲、と言えるだろう。その割には延々とシャッフルビートと裏表な3拍子で反復するシンセが鳴り続けたりと、このユニット的な変に透き通ったトライバルな質感はこの曲にもあり、しかしながら同時にフロア対応バッチリなカジュアルさも備わっている。なんか変な取り合わせのはずだけども、でも夏をテーマにしたそれに相応しいポップさを元に強引に統合できている。不思議なシンセのブヨブヨした音も、ウォータードラムみたくグジュッとしたスネア音も、すべて「まあでもなんか楽しいから」って雰囲気で結び付けられている。勢いに乗ってるときって感じがとてもとてもある1曲。
26. Let's Go Surfing / The Drums(2009年)
起きぃや 綺麗な朝やん ハニー 太陽出とるうちにやね
起きぃや 一緒に出掛けよや ハニー ビーチに駆け出しや
ああママ〜 サーフィン行きたいやん
ああママ〜 心配事とかなんもないやん
2010年代前後の「やたらチープでガレージ感あるサーフポップ」の代表曲のひとつがこれだろう。まさにインディロック的ニューウェーブなヘロヘロさで演奏するThe Beach Boys、もしくはカリフォルニアのJoy Division。まあニューヨーク出身のバンドだけども。アルバムではもっとガチに初期The Beach BoysのBrian Wilson的なものをニューウェーブ的スカスカサウンドで目指したような楽曲があって結構より本格的なThe Beach Boysガチ勢っぷりが堪能できる*13。
けどもリード曲となるとこの圧倒的にチープな曲になってしまうだろう。なんてバランス感覚だ。実は歌詞に明確に「夏」と入っていないけども、でもサーフィンを夏以外にするサーフィンガチ勢じゃあるまい、ということで夏の曲。この延々と手前に向かってヒョロヒョロと走っていくのが大半を占める脱力PVといい、もはやこのヘナヘナな演奏とメロディでサーフィンの歌なこと自体がどこかギャグめいて聞こえたもんだった。2回目のヴァース以降の歌詞などに、この曲を書いた当時がオバマ大統領が登場したときでその期待感みたいなのを表現している、とかいう蘊蓄がつくのが逆にマジかよ…って感じがして笑える。間奏の口笛の頼りなさすぎる感じとか本当に、この音楽が何も背負わずに聴ける証拠かもしれない。「何もかもから自由な学生の、ヘボいけどユルく楽しい夏」みたいな感じがして、これはこれでもう眩しい。
それにしても、こんなヘロヘロな曲で始まって割とすぐメンバー脱退もあったバンドがそれでも現在まで続いていることにはしみじみとした感動がある。相変わらずJoy Divisionめいた高い位置のベースサウンドを軸にヘナヘナで透明感のある音楽をやっていて、この10月には新譜も出すという。このヘロヘロな声で歌っているJonathan Pierceという人が実はこんなにタフだなんて、この曲の出た頃からはまるで想像もできなかったな。いくつもの夏をこのバンドで超えてきたんだ。
27. Summertime / Girls(2009年)
お墓から這い出て 名前のところの埃を払って
いい靴を履いてさ 夏が来て きみと陽の光を浴びるんだ
公園で横になって 暗がりで草をふかす
昔みたいにハイになってさ 夏時 きみと陽の光を浴びて
夏の間 きみと陽の光を浴びるんだ
The Drumsも大概なバンド名だと思ったけど、Girlsに至ってはもう、検索という概念を積極的に回避しに来てるとしか思えなかった。幼少期にカルト教団『神の子供たち』に身を置き、脱走し、浮浪するような生活を続けていたクィアのChristopher Owensがボロボロのボーカルと相棒Chet "JR" Whiteの音楽的助けを借りて音楽を作る、それ自体がこのバンドの物語であり同時に音楽的アイデンティティであり、“この音楽性を自分たちはやる”という軸が個人の物語とほぼ同化した最たる事例のひとつかもしれない。なので『Lust for Life』のようなチープなガレージロックもあれば、この曲のようなドリーミーなウエストコーストロックみたいなのもその作品集にはある。
ゆったりして伝統的なポップスの雰囲気が少し香るギターのコードの流れにはバックでシンセがゆったりと空間を永遠の夏模様に歪め、この辺は2000年代後半以降の、シンセが当たり前に使われるロックバンドの感じがある。そこからある程度メロディを展開させた後にくる「いやそりゃ無茶だろう…!」ってくらいに音量差のあるギターの入り方に、製作者たちのファナティックな姿勢が垣間見える。ジザメリじみたノイジーさでありながら、ギターのラインとしてはあくまでドリーミーなうねりを表現していて、ドラムの存在さえ殆ど打ち消されるくらいのその音の強引な広がり方には、もはや「何もかもを無視してうっとりしたい」という願望そのもののようにさえ感じられる。それが終わって曲が終わったかなと思ったら、ギターと歌だけまた登場して、申し訳程度のメロディを歌って終わってしまう。それはまるで、永遠に続くかのようだったのに意外とあっさり終わってしまった「永遠の夏の感じ」を惜しむかのようだ。
28. 小宇宙 / GRAPEVINE(2009年)
季節の終わり 風の訪れにも
夏のからくり解けやしないままに
予報は大嘘つき
体中で待ってた明日 小宇宙を埋め尽くした
GRAPEVINEがまたえらい夏の曲がたくさんあるバンドなので、時間がある時にまたそういうまとめ記事でも書きたいと思ってはいるところ。最近出た新譜でもどこかの曲で“夏”の語を聞いたような気がするし、とりあえずアルバム1枚に1曲くらいは夏の曲を入れるのが定番にでもなってるのかなってくらいのもの。
この曲はレアなギターの西川氏作曲の楽曲。この後もう1曲を出して後はもう彼の作曲が出てきていない。そういえば氏の曲は夏の出てくる曲がちょっと目立つな。「真夏に咲いた花は枯れて」とか「短い夏はそこでねばってんぞ」とか。全体で見たらそうでもない?この曲の話に戻ろう。
空間を埋め尽くさないよう慎重に引かれたそれぞれの楽器のラインがけっかとしてぼんやりとしてどこかノスタルジーを喚起させるコード感を作り上げていく。ドラムさえタムを多用し輪郭のはっきりさせない演奏を強く意識している感じ。その中で上記の歌詞が出てくるというのはなかなかにイマジナリーさ巧みなところ。「夏のからくり解けやしないままに」というのはこの曲のぼんやりと遠くを想うようなコード感になんてぴったりなフレーズなんだろう。で、この曲はそんな曖昧さに浸り続けることを目的としているのではなく、最初のサビも曖昧なままにドラム演奏もブレイクして、すっかり淋しい雰囲気になったと思った次の瞬間に、急に演奏が沸々と噴き上がってきて、そこにどのような感情や感傷や何やらを見出すか、というところが熱い。その後しれっと元のテンションで歌が再開するものの演奏はより厚くはっきりとし、そして最後のサビで一気に曲タイトルを感じさせる重力感が演奏でも言葉でも表現される。とてもロジカルにかつ生真面目にエモーショナルさをコントロールするその様は熟練のそれで、彼らの年輪を重ねた修練と何かの諦念の末の表現を感じさせる。
29. Pursuit of Happiness (Nightmare) / Kid Cudi feat MGMT(2009年)
ちょいとすり潰して 巻き上げて ヒットすんだ
灯りな気分 正しい感じさ 深夜2時の夏の夜
気にしないさ ハンドル握って 酩酊運転 したいことする
ミッドウェストを抜けて 自分の生を生き 夢に手を伸ばす
みんな落ち着けよって言うけど クソッタレがって叫ぶんだ
したいことをするんだ 前を見て 振り返ることなんてねえ
もし吹っ飛んで死んでも 人生を最高に生きたって覚えてて
もし吹っ飛んで死んでも 銃弾を避けて生きてたって覚えてて
幸せを追いかける 知ってんだ 輝き全てが黄金って訳じゃねえ
いちど手に入れりゃおれはもうオッケーさ もういいのさ
ギラギラした夏の曲に目を向けないでいるとどうしてもヒップホップの夏の曲の出番はなかなか来なくなっていく。日本とかに輸入されたものはともかく、アメリカ本国のそれはやはりどこか基本的にマッチョでギャングなところがあるのか。でも、今やすっかり名前を出しづらくなったKanye Westが『808 Heartbreak』でプリズマイザー多用して歌いまくったり、このKid Cudiがよりインディロック化したヒップホップを作り出したりして、次第に2010年代のPitchforkがいつの間にかヒップホップメインみたいになったりする土壌は作られていった。トドメは2010年の『My Beautiful Dark Twisted Fantasy』だろうけども。
この曲はそんなKid Cudiの、コーラス部でそれこそインディポップユニットのMGMTをフューチャーしたポップな楽曲。もう全然シンセポップとの境界などないようなファンシーでドリーミーなシンセに彩られたポップなトラックには、しかし歌詞抄訳してみると案外ヒップホップ的なドラッグまみれな世界観が繰り広げられている。まあPVもそんな感じだし、曲のファンシーさに対してのこの辺はなんか不思議な気分になる。まあ黒人だったらそんなもんなのか。いやでもドラッグはしてるけど攻撃的なこと言ってないし、案外相対的にポジティブでファンシーな内容なのか…?なんか最後に歌詞に酔いつぶれたオチまで付けてるし、結構ファニーではあるのかもな。
30. Come Saturday / The Pains of Being Pure at Heart(2009年)
The Pains of Being Pure at Heart - Come Saturday - (2 of 10) - YouTube
きみの写真を見てるのも耐えれない
それもぼくのいなくなった化粧台でさ
まるで別の晴れた日 きみは80マイル先の火曜日
でも土曜日になれば きみは泊まりに来るだろう
きみはぼくの腕の中で揺られに来るんだ
どっかでやってるパーティーなんて誰が気にするかよ
ぼくら家にいるんだ
土曜日になれば きみは言いに来るんだ
多分害なんてない ドラマーもいやしないクソな夏さ
ぼくら家にいるのさ
きみの色褪せた家族写真の中の備品でいるのには耐えれた
でも夕日の中なんて見えやしない
知ってるのは まさに今のきみが完璧だってことだけさ
リアルタイムで彼らが出てきたときにバンド名を見て「はァーっな
代表曲であるこの曲はまさにそういうものの代表でもあり、勢いだ
…という、青春最大風速みたいなことをしてると後が辛いだろうなあ、と思ってたこのバンド、2nd『Belong』はおっそっち行くかあ、となるほどなって思ったけど、結局2020年代になる前に解散してしまった。そしてSpotifyで見るとなんか2ndと3rdがなくて、この現代的に痛々しい様はなんというか、何かの代償なんだろうか。夏はなんか遠くになってしまったような感じだ。そんなに深く興味があったわけでもないけど、なんか意味もなく寂しいな。
・・・・・・・・・・・・・・・
あとがき
以上30曲でした。本当に随分時間が掛かってしまって、それは、なんか40曲集めきれなかったり、30曲以上集めたけどなんか色々と外したくなったり、なんか旅行に行ったり、仕事が忙しかったり、疲れて書く気が起きなくなったりで色々な事情です。情けないなと思ってはいます。もう10月で、夏も流石に終わりきった感じの気温してたし。年もうまくバラけなかったなと。2006年と2007年がやたら少ない。絶対、見つけられていない、思い出せていないこのリストに入れるべき楽曲がもっとあるだろうに…と思うと悔しい気にもなるけども、どこまで悔しい気になるべきかも途方もなくて分からないので、考えても仕方ないですね。
幻想的な夏・抽象的な夏を想うことというのは、どこか夏を対象化する心理になるところがあり、これが意味するのは「そう思う自分は今、その“夏”の中にいない」というどこか寂しい現実です。で、その寂しさが深くなればなるほど、最初の方で言ったとおり、測れる夏の尊さや美しさの輝きも増すのであれば、それは残酷なものであるような、しかし何もしなくても得られる美しさが増してお得なような。しかし、その効き目もどのくらいあるものなのか。
ともかく、30曲に絞った分ある程度の幅で「幻想的な夏」みたいな感じにできたかなという気が少しだけするのでよかったです。いつものようにプレイリストを貼って終わります。それではまた。
*1:またこの曲が収録されたアルバム『Bloodflowers』全体としても。
*2:このあとバンド解散してそのまま夏連発なNATSUMENに移行していくくらいには戻ってこなかった。
*3:吸うもんらしい。
*4:こう書いて、そうなると案外日本における“桜”の地位と似てんなあ…と思った。
*5:なのに続くシングルがより時代を超えれた感のある名曲『ばらの花』なのがこの時期の作者の勢いを思わせるところ。
*6:そういえば、2023年の“新譜”として現れた遺作はそんなチープでジャンクなロックミュージックで幕を開ける。何か原点回帰でもしたい気持ちで、自殺に至るまでこの遺作に向き合っていたんだろうか。
*7:これはベース部分の音を補完できるピアノという楽器の性能によるところも大きい。歌いながら3音アルペジオを繰り返しながらそれも演奏するのか…とも思わされる。『Folklore』ではミトがギターを演奏するし、ベースに拘らず彼が様々な楽器でサウンドを広げることが、この時期のクラムボンの自由で広がりあるサウンドに繋がってるのか、とライブ動画を見て改めて思わされる。
*8:当然ながら未読。逆にこの小説の紹介文だけを読んで、Lambchopがやってるようなことを小説で先にやってたのかな、みたいな理解さえしてるかもしれない。
*9:去年に続き今年また新譜出すというから驚き。
*10:この際、果たしてKissはヘヴィーメタルバンドだろうか、ということは考えなくていいだろう。いちいちこんなこと書いてる方がバカなんだ。
*11:この過程においてチルウェーブのブームがあったことはおそらく重要だろう。
*12:当然これを筆者が嫌ってるわけではない。GRAPEVINEとか大好きなんだから嫌いなはずない。
*13:曲によっては本当にボーカルがBrian Wilsonにすごく寄せれてる瞬間があってちょっと笑う。