
この手の記事はいつもサムネ画像をどうするか悩む…今回はもういいやって感じで25枚のジャケットそのまま出し。
2023年はとっくに終わり、新年早々地震に空港の衝突事故にと全然おめでたくないことばかり起きている状況ですが、この2023年中に書きそびれたものが2024年最初の弊ブログの投稿となりそうです。いささか周回遅れ感は否めませんが、書かないのもアレなので書いておきます。今回は遅れた分、2022年の20枚から5枚だけ増やして25枚としましたがまあどうでもいいですね。上のサムネ画像は単純にA→Zの順番で並べただけなので順位とは無関係です。
過去の弊ブログ年間ベストはカテゴリーから見てください。今回も書いてて嫌になるような“いつの時代を生きてるんだ”的なリストです。
ジャケット画像にsongwhipのリンクが付いてます。
なお、Twitter(今はもうXか)で見てしまった「年間ベストではアーティストの出自とかレーベルとかをちゃんと紹介してくれないと見る方も困る」とかなんかそんなんだったような大変ご親切な指摘*1を考慮して、今回はなるべくそういうの書かないような感じでいきます。
25. 『Almost There』GRAPEVINE(9月)
前作『新しい果実』はこのバンドの通常時って感じの曲が少なくてなんかうわぁすげえってなってたけど、今回は結構そこそこ揺り戻しがあった感じがした。とはいえ、田中和将作曲が前作同様半数近くを占めるという、このバンドにおいてもなかなかないことだったはずな事態は今作も続いており、今後はもうそんな感じで行くのかなあって思ったりした。
本作はそんな田中曲の尖り具合が前作と比べると…というところか。まあ色々あったもんねえ。最終曲が『SEX』なのは笑いを取りにきてるのか果たして。彼の楽曲はどことなくソウルテイスト重視というか、そこはかとなくStevie Wonder感が浮かび上がっていて、『停電の夜』は丁寧に作られたバンド駆動のソウルだと思わせられる。田中曲以外だと本作でも例外的に幻想的なシューゲイザー要素を見せる『Ophelia』はかなり良い。
歌詞のテイストも、幻想的な方向で尖ってた前作からの揺り戻しなのか、どこか現実的生活感を醸し出した内容で、「子育ての終わった人との恋愛の再燃」とかいう妙な方向に生々しかったり、急にアニソンを罵倒するような歌があったり。こういうのがあんまりなかったのも前作が尖ってる割に聴きやすかった原因なのかもなあと逆に思った。
アルバムリリース後しばらくしてから急に出てきた新曲『Loss(Angels)』は一体何だったんだろう…ジャケットからして、アルバムのアウトテイクなんかな。
24. 『Sit Down for Dinner』Blonde Redhead(9月)
話は逸れるけども、こういう年間ベストを年の終わりやらに慌てて作る時の「まだ何を知らなくて聴いてないんだっけ」を調べるのに英語版Wikipediaのその年出たアルバムのリストを活用していて、便利だなあと思う反面、所詮はその範囲でしか音楽を追えてないんだなあと思うと同時に、このアーティストも今年出してたのか、となる度に、なんだか不甲斐なさみたいなのを覚える。全部仕事が忙しいのが悪いことにしたい。
そういう経緯でこのアルバムも見つけた。アルバムごとにサウンドの質感の違いなどはあるにせよ、このバンド特有の少し殺伐とした耽美なコード感は相変わらず健在で、むしろ『23』とかの頃よりもそれは研ぎ澄まされているのかも、とも思える。そりゃああのアルバムからももう何年経ってるよ…という話だけど、でも、一貫して同じ特性を磨き続けられるアーティスト性というのは尊いと思う。この、不穏なコード感に雫が垂れ落ちるような歌、そしてポストロック以降的な音感覚が彼女らの好きなところだけど、これは案外その時代特有のものだったのかもということも、今回この年間ベストのリストを作ってみて思った。別に古びてるとか言いたいわけじゃないけども、リバーブの感覚ひとつ取ってみても、90年代的な殺伐気味にザラついた感覚が、本作のナイーヴなサウンドの曲にさえあるような気がして、特に組曲形式で登場するタイトル曲はその殺伐さに捨て置かれた感覚の世代のそれを洗練させたかのようなスタイルにこのバンドの積み上げてきたものを思わせる。
Blonde Redhead - Sit Down For Dinner (Pts. 1 & 2) (Official Video) - YouTube
23. 『Bird Machine』Sparklehorse(9月)
上の方で「今回は一切バックボーンとかを書かない」と言ったけど、それが限りなく無理なこういう作品もある。しかしMark Linkousが自殺したのは2010年で、そこから実に13年という長い月日を経て“遺作”が登場するというのも不思議な話だ。普通そういう“遺作”は亡くなってそこそこの期間で出てくるもので、これだけの長い時間を経て出てくることそれ自体がちょっとした不思議ではある。
不思議なことは他にもある。本作はこれだけ手作り感に溢れた音ながら、あのSteve Albiniと共にシカゴで録音された音源を母体としている。冒頭曲から溢れ出るチープなロックンロールっぷりに「これが他者と共演して出来る音楽なのか…?」とも思わされるし、まあでもAlbiniならそういうこともあるかあ、ともなる。今回聴き返して思ったのは、特にロック色が出た曲では、案外「ひとりCloud Nothings」みたいなところがあるな、という、順番がまるであべこべなもの。声もちょっと似てる?ミドルテンポ等の曲では質感はもっとSSWじみてくるけども、そこにおいても、プロフェッショナル的な画一的な艶よりも手作り特有の揺らぎが随所に感じられて、「これは確かにAIとかではなく、ひとりの生きていた人間が色々やって築き上げた音源なんだな」という。まあそのうちAIでもこういう手触りができてしまう、もしくは既に出来るのかも、とは思わんんでもないが、こういう「Soundcloudの片隅でキラリと輝くようなトラック」的な味わいは非AIの世界でこそ続いていってほしいって身勝手に思う。
それにしてもこの、アルバム全体からそこはかとなく感じられる「スタジオの棚の隅に落ちてたデモテープを再生してみた」的なサウンドメイクは誰のディレクションのもと行われてるんだろう。実に彼の音楽らしいけども、ちょっと演出過剰かなあ。いやこういう試み好きなんだけども。
22. 『Bunny』Beach Fossils(6月)
前作がいつだったっけなと調べたら2017年、なんかその時も年間ベストで取り上げてそこでかつてのCaptured Tracksレーベルの栄華も今は昔、みたいなことを既に書いてしまっていたかな…と思って見返したらやっぱり書いてたのでその辺の話はよそう。
彼ら自身もかつての『Clash the Truth』の頃の作風に拘泥するつもりも、また6年前の前作の音楽性をより発展させる気もそんなになく、前作からも感じたインディーバンド的牧歌性によって、1960年代サイケデリックロック的なギターポップ具合が今作は特に明確になっている。かなり増加したコーラスワークもそれっぽくて、まるで同じくぐっと牧歌的な作風に寄ったRideの3枚目のアルバムにも似た、かつての特徴的な音楽性をかなぐり捨てて地味だけど良質な音楽を作ろうとするマインドをそこはかとなく感じた。
まるで別バンドの作品のようでありつつ、しかし自然と滲み出してくるソングライティングの癖の部分に、かつてのシャープなリヴァーブ感で疾走していたバンドの面影が垣間見えたりする。かつての面影をアルペジオ軸のコンパクトなスタイルに閉じ込め切った『Dear me』を聴いてると、なんとなく「あの頃」の感じ*2がふと蘇る。
21. 『everything is alive』Slowdive(9月)
2017年に“再結成後の新作”という難しそうなテーマにて傑作をモノにしたシューゲイザーバンド御三家のRideとSlowdive。Rideが割とサクッと再結成後2枚目を前作と似た路線で出したのに対し、約6年後にリリースされたこちらの再結成後2作目は、自然なバンド感が漲っていた前作と打って変わって、冒頭よりアナログシンセのウネウネとしたフレーズが響き、ドラムは1980年代ゲートリヴァーブ的な響きに加工された、無機物的な煌めきと反響を思わせる作風となった。流石は『Souvlaki』から『Pygmalion』に移行した経験を持つバンド。というかMojave 3も合わせるとこの人ら何気に振り幅が極端だなあ。
轟音ではなく静謐で曖昧な反響の中にシューゲイザーというジャンルの居場所を作った節のある彼らの功績を思うと、本作はそんな彼らの面目躍如なのかもしれない。『prayer remembered』の静かにノスタルジックさと感傷が粉みたいに舞うかのような様を聴いていると、これはむしろドリームポップなのか、あるいはシューゲイザー寄りのスロウコアとかポストロックとかなのか、という感じがする。もしくは、無骨なリズムの始まりの割に延々とメインフレーズが心細げに揺らぎ続ける『sky in the game』の感覚。曖昧さの美学については彼らは第一人者のひと組だったなあそういえば、というお話。
20. 『映帶する煙』君島大空(1月)
1年に2作アルバムを出すというのはアーティストにとっておおむね、絶好調な状況だったか、もしくは作品を出すスパンが開いている間に多くの楽曲が制作されていたかのどちらかもしくはどちらも、という事情だろう。数年前に日本の新世代SSWの一角として現れた君島大空においては、1stフルと2ndフルを2023年にリリースし、こちらがその1stの方。意外とフルアルバムはまだだったのか、という印象。
ランキングによってはこちらの方が首位や上位、という方も多いかなと思うけども、弊ブログでは2ndももっと後に登場させます。2ndに比べるとこちらはより従来の作風と連続した、文学的に繊細な情緒とSSW然としたどことなくフォーキーなテイストが軸となった作品と言えそう。同世代の長谷川白紙とかみたいなインターネットネイティブなバグった感覚と比べると、彼は割とオーセンティックなSSWを大切にした人物のように本作までの作品を聴いてるとそう思える。とはいえ、SSW的な装いに加えドリームポップやらのトラックメイカー的な側面も余裕で標準装備しており、本人の音楽的素養の高さ、また元々の本人のジャズ志向なども加味され、基本的には曖昧で切なげな楽曲が多くを占める。
ただ、いくら風流なSSW風味で装っても、そこを強烈に「雰囲気で誤魔化せない激情」が突き破ってくる場面も所々あり、本作ではそれはアクセント・または事故的な存在になっている。突如えらくノンエフェクトな声が大雑把にブレイクを繰り返すバンドアンサンブルととともに聞こえてくる『都合』、そして最後に置かれた、急に不穏な歪み方をしたノイジーなギターが重く響き、それまでの穏やかな美しさが嘘のように醜くフリーキーなインプロが展開されていき、楽曲自体もブルーズじみた殺伐としたコード感で歌い方も思う存分ささくれて裂けていく『No heavenly』の辺りで、彼は「美しい音楽」の中に安住できる性質の作り手ではないんじゃないか…もっとどうしようもなく荒くれたものを内に有した人間なんじゃないか…という疑念が湧く。その疑念への答えは、彼のそういった側面こそ1番好きという人にとってはご褒美のような2ndにて。
19. 『Laugh Track』The National(9月)
The Nationalもまた2023年に2作出したアーティストで、こちらは前作が2019年、えもうそんなに経つの…と素で思ったけど2019年で、なので長い間隔が空いたのちに制作に入って2作分の楽曲ができたのかなあというパターン?
おそらくは『First Two Pages of Frankenstein』の方が精密に作り込んだ作品だと思われて、このバンドのこれまでの歩みを丁寧に再度取り上げ精密にかつ誠実に作り込んだ作風には、随分とシリアスなトーンが続く様に、正直言えばある種の退屈さも覚えないではなかった。その点、タイトルからして“ラフさ”を強調した節のありそうなこちらの方が、よりバンドが本来持っていたダイナミックさが伸び伸びと発揮される場面が散見されて気持ちいい。2曲目『Deep End(Paul's in Pieces)』の冒頭から聴こえる大味な鳴りのドラムとギター、これぞロックバンドという、そういうのを待ってた。
タイトルトラックがPhoebe Bridgersとのコラボの丁寧な楽曲で言うほどラフじゃなかったりもするけど、その次の『Space Invader』がチープなシンセの導きの中で沸々と高まっていく楽曲で、特に終盤のインプロ的な展開にはいい具合の“ロックバンドな”ケレン味がある。そして最終曲『Smoke Detector』の、もはや歌を捨てて語りと、そしてそれが次第に感情の迸りに移行していく様には、徹底的なコントロールの術を体得した大変に大人なバンドが、あえてハンドルを手放しで暴発して見せる面白さがしっかりと宿っている。
18. 『HOLLOWGALLOW』dip(12月)
このバンドもまたリリースがかなり開いていて、前作はなんと2014年。ヤマジカズヒデというひとりのギタリストとしては様々なものに参加してるイメージだったけども。そのブランクなど気にしないくらいにマイペースに良作となっている。長い尺の楽曲が結構あるせいで70分越えとなっているけどもまあ。1曲目から歌無しの9分超えインストだけどまあ。
ヤマジカズヒデという人自体が日本有数のオルタナティブロックなギターの名手であることもあって、dipのアルバムというのはそういったものの見本市状態となる。伸ばすところのフレーズの流麗さもザクザクと刻む時の歯切れの良さもどれも一級品で、歌ものの楽曲が多いはずなのに、演奏と作曲の境界がまるで分からなくなってくる。楽曲によってはインスト曲に後から歌を乗せたようにも感じられるし、その辺はまあ厳密にどうこう区別する意味なんて全然ないんだろう。そして、作曲と演奏の境界が曖昧ということは、オルタナなギターが弾ければ、オルタナな作曲もできるということ。様々なツボを押さえたものが並び、特に『for never end』の明らかにMy Bloody Valentineなイントロが吹き出すギターロックのキャッチーな様は新たな代表曲になりそうだなあという感じ。一方、淡々とサクサクと進行する歌もののように始まりながらも段々とノイジーさを増していき、壮大にサウンドが展開していき終盤はノイズインストみたいになって尺が8分を超える『perverse』のような曲もある。
3ピースバンドながらスタジオ録音だからこその多重録音が楽しい作品であり、なので色々とライブでどうなるんだろうなと気になるけども、最近は忙しくて福岡のライブも観に行けなかった…。
17. 『e o』cero(5月)
“東京のハイコンテクスト音楽!”という感じで出てきていながら、やがて都市の外を目指していた感じのあったこのユニットの、そういう流れでいけばこのデジタルで描かれたあばら屋ジャケットにバンド名のローマ字が2文字欠け落ちたタイトルの作品の、どことなくの志向の一角は推し量れる。地方に住んで、車を持って、よく分からない田舎の海沿いを走ってみると、時折こういう、ロケーション的には良さそうなのに打ち捨てられた廃屋はままある。
つまりは、“都市の狂騒”みたいなのから過去一で距離を置いた、都市に労働力を提供する“郊外”ですらないどこかの侘しい場所の音楽のように、このハイコンテクストながら熱の取り除かれた楽曲群は感じられる。リズムへの熱中は薄れ、というか「すげえ演奏を追求して重ね合う」みたいな欲求が見えなくなった。歌詞に出てくる移動手段は基本車のようだし、これは彼らなりのどこかの侘しくくたびれた場所の音楽なんだろう。もちろん作り手が彼らであるから、実際の田舎にあるような泥臭さとかなんとかはほぼ存在しないけども、代わりに音楽的にはピアノをメイン使用するスロウコアとかそういうのに接近してる感じさえする。最終曲『Angelus Novus』を聴くと、特になんだかそんな感覚になる。
音楽で熱中する人たちのひとりではなく、ある場所にて暮らすどこか慎ましくも寂しい人たち、みたいなところに、彼らはどういった思想を重ねているんだろう。その辺の難しいことは分からんけど、田舎の海沿いの夜にこれを聴いてるとなんだかしみじみと寂しくていいなってなるところはある。ceroの音楽でこんななるなんてねえ。
16. 『Hackney Diamonds』The Rolling Stones(10月)
The Rolling Stonesが実にThe Rolling Stonesっぽい音楽をやってる!と思わせるのに適切な冒頭4曲までの流れで、やっぱこの人たちは自己理解とセルフプロデュース力が高いなあと思わせられる。カバー集だった7年前の前作では味わえるはずもなかったこのバンドの作曲能力の特殊さをしっかりと感じられる。ドラマーが死んでしまったけども、このバンドらしい荒々しさ・泥臭さ・バラッドの高らかな感じは実に的確に冒頭4曲に詰め込まれ、特に『Depending on You』の名バラッドぶりは見事。
5曲目ごろから「ベタに泥臭い感じのストーンズ」以外の面も見えてくる。『Whole Wide World』のサビのメロディのポップさはNew orderか何かか?と思えるほどだし、リズムもさりげなくディスコ的なビート。『Mess it Up』もまたタイトルをディスコ的なリズムの上で奇妙に反復させるのがこのバンド的なキャッチーさを生み出してるナンバーで、この曲と次の猥雑でルーズなノリが実にこのバンドな『Live by the Sword』の2曲はドラムはCharlie Watts。一方、The Cureか何かか…?みたいな悲しげなアルペジオがKeith Richardsボーカル曲『Tell Me Straight』の呼び水だったりという意外さもある。こういうアルペジオも案外ブルーズなのかも。
別に「本作は新しいストーンズ像を作り上げた」とかそんな大それたもんではない。そんなこと流石にしなくていいだろう。しかし「今の」「2020年代の音をした」ストーンズであることは間違いない。なんせオリジナル曲では2006年がアルバムでは最後だったんだから。2023年のストーンズの新曲に合わせて部屋の中で2023年的なニュアンスの付いた変なダンスを踊ってみるのもまた一興だろう。
15. 『Javelin』Sufjan Stevens(10月)
2020年のエレクトロで神経質な前作*3から後にまたアコースティックな方面に揺れ直した彼の活動の、その流れのひとつの終着点にこの作品が当たるのかどうか。なぜだか大体の曲が「始まり方は『Carrie & Lowell』の時みたいにシンプルで、しかしいつの間にやらシンフォニックな合唱と合奏に膨れ上がっていく」という構成を取っていて、その妙なワンパターンさにむしろ思想を感じられもするけども、その辺の事情はよく分からない。彼が基本一人で演奏を重ねて制作したことも関係するんだろうか。インディーフォークとチェンバーポップの両方を1曲で味わえる、という曲がいくつも並んでいる構図は少し可笑しくもあって、ちょっとはユーモアなのかもしれない。
歌詞を読まずとも、本作がパレード的な、楽しいばっかりの合奏に満ちた作品ではないことはなんとなく感じられるはずで、全体的にその合奏には何かスピリチュアルな雰囲気がつきまとい、特に所々に挿入されるエレクトロ要素にはそのような歪みが感じられる。案の定、monchiconの解説によると歌詞は非常に沈痛な個人的事情やら感情やらを歌っているものらしく、そういう意味ではとてもSSWじみた作品だったわけで。しかしそれを『Carrie & Lowell』みたいにせずに、スピリチュアルなオーケストラサウンドにまで発展させてしまうその謎の爆発力こそが彼の本領発揮といったところか。その分なのか、最後はなぜかNeil Youngのオーケストラ曲『There's a World』を『Carrie & Lowell』形式のシンプルな弾き語りでカバーして終わりという、不思議な締め方をする。一体あの曲に彼は何を見出したのか。
14. 『Cousin』Wilco(9月)
今回のWilcoの新作はなかなか難解だった。招いた若手の外部プロデューサーによる方向性のこともあるだろうけども、基本的に抽象的で曖昧なサウンドが多くみられ、それは2作前の2019年『Ode to Joy』にも連なるところだけど、あれよりも今作の方がもっと掴みどころがない感じはある。そしてその掴み所の難しいところにこそ本作の聴かせたい部分があるんだろうなということは、最も溌剌として勢いあるポップな爽快感を感じさせる『Meant to Be』をわざわざアルバムの最後に追いやっていることからもなんとなく感じる。そもそもジャケットもなんだいこれは。
掴み所のないものを語るのは難しい。それでも冒頭曲『Infinite Surprise』の、想像力の無数の破片が舞うようなイントロからギターと歌が出てくるところ、そのメロディの具合が実にJeff Tweedyを感じさせるものなのにはホッとする。2曲目くらいから、ゆったりと日常の光景が陽光とかによってぼんやり揺らぐ感じの雰囲気が多くなっていく。当然分かりやすいギターソロなんてない。『Sunlight Ends』とかもう音の揺らぎと反響の具合が侘び寂びのような感じさえする。時間の豊かにある時にどこか田舎に行ってぼんやりこういうのを聴いてると心地良さそうだ。『Pittsburgh』の渋味の効いたアコースティックサウンドと別世界への誘いじみた奇怪なサウンドの取り合わせもまた本作的な複雑さを思わせる。最後2曲のサッパリしたポップさがありがたい。でも、ちょっと前に公開された本作からの唯一のヴィデオクリップが本作でも例外的な『Meant to Be』なのはそれでいいのか…?まあでも、3月のライブがとても楽しみ。
13. 『Romantic Piano』Gia Margaret(5月)
12曲27分弱の、ピアノを軸としたノスタルジックで寂しげなインスト楽曲集、という取り回しのいい作品。ピアノを取り巻く様々なドローン音や虫の音や、そして豊かな思い出の向こうに閉じ込めるリヴァーブの効き。そして饒舌でなしにポロポロと紡がれるピアノの可憐な佇まい。この雰囲気でいて、SSWの作った作品だというのが面白い。もちろんそれが病気で一時的に声を失ったことによるものであることは承知の上で。
基本的には短い曲ばかりで、まるでふとした拍子に弾いてみたちょっとしたフレーズを簡単に録って少し加工しただけ、みたいなプライベートな空気感が、しっかりと丁寧に演出されている。実際は色々手がかかってるんだろうが、それにしたってどことなく手作りの感覚があって、こういう音楽もまたAIで自動生成などできないままでいてほしい気持ちになる。そして、1曲だけサウンドの質感は同じままで歌もしっかりと添えられた『City Song』の切なげな様子が大きすぎるアクセントとして働き、アルバムの真ん中に置かれたこれが他トラックのしみじみとした印象をより際立たせているのか。後半になるとリズムトラックやスピーチ、逆再生音の挿入などより曲の仕掛けはささやかに増え、そのささやかさの加減にこそイメージの広がりうる“余白”が託されているのかも。
12. 『感覚は道標』くるり(10月)
ジャケットにこれ見よがしにドンど座った「かつての3人、はじまりの3人」の姿。格好もなんだか野暮ったく、いかにも「あの頃の感じ」を狙い澄ました感じもするものの、別に本人らはそう思ってなくてもそう思われてしまうのもくるりというバンドの持つ性質だったよなと。あの頃よりも手管は充実しまくってるんだけども、その手管を隠し味程度に留め、基本ロックバンドの少しもっさりしたグルーヴにて形作った本作は、久々にいいなって思った。それがある種のノスタルジーだとしても、そのノスタルジーに的確に溺れさせてくれるものがちゃんとここにはある。
所々に明確に「あの頃」を感じさせる曲が置かれてるのに笑う。『朝顔』は彼らの数ある『ばらの花』と同系統の楽曲の中でもとりわけ『ばらの花』だし*4、『window』のゆったりと光景の奥行きに溶けてく感じは『屏風ヶ浦』とかを思わせる。『LV69』はタイトルだけ過去のスタイルから拝借して、今の3人でハチャメチャに加工しまくったロックンロールをやってみた感じで、おっさんの僻みじみた歌詞の可笑しさも含めて「あの頃」のユーモラスさが歳を取ったかのようなものをしっかり作ってる。個人的には『doraneco』の基本平坦で飄々としたバンドサウンドに緩やかに不思議な音が重なって、そして歌のメロディに仄かに漂う細野晴臣フレーバーがとても好き。かつてのようなささくれだった激しさはほぼなくて、全体的にどこかくつろいだ空気感は「でも同窓会で喧嘩する奴とかおらんやろ」っていうあの感覚かもしれない。別にそれでいいんじゃないかと。
このほっこりしてしまうリユニオンを彼らも最大限に利用し、映画を作り、その主題歌として出して恥ずかしくない『In Your Life』の感傷的なギターリフには、演出とかそういうものも気にさせないくらいの鮮やかでちょっと寂しげな晴れやかさがしっかりと宿っていて、そういえばこういう寂しい爽やかさがくるりだったかもなあ、と思わせてくる。どこまでが計算でどこからが天然か、そういうくるりを久々に感じれたような。
11. 『Why Does the Earth Give Us People to Love?』Kara Jackson(4月)
全米青年桂冠詩人に選ばれた詩人だとかいう経歴はこの際どうでもいい、と、歌詞をしっかり読み込む時間がないのではじめにそんな危ういことを書いてしまう。個人的にはそれよりもこの、まるでKaren Dalton『In My Own Time』のような、実に土っぽくいなたい歌とアンサンブルの滋養にかなり惹かれた。特に歌はまだ23歳とは思えないほどにブルーズなハスキーさ。アコギのアルペジオを軸にした曲でも、歌の枯れ具合によってとてもブルーズなものに聴こえてくる。
それでいて、曲によってははじめ音数の少なさによって生じていたはずの無音の闇がいつのまにやら宇宙的な感じに広がってることがある。そういう曲では声をラフに振るうのではなく、しっとりと歌が旋回していき、弦楽器などとともに優雅にかつ強い重力を纏って、アナログな演奏の奥行きをずっと深くしていく。それにしても楽器やコーラスのアレンジがいちいち的確で、まだブルーズとかロックとかソウルとか分化する前の音楽がそのまま2023年を迎えたかのようだ。なんだか、早熟とかいうのにも程がある感じがするけども、凄い人はいるもんだ。
10. 『SUPERIOR』Lillies and Remains(7月)
冒頭の曲を聴いて、ハット連打の打ち込みのリズムも刻む歪みギターもあまりに3rdの頃のジザメリで笑ってしまった。このバンドからこういう半ばギャグめいた飛び道具が出てくると思わなくて、しかも曲としては普通にとてもいいので、グッと惹かれた。同じメロディのリフレインの後半を頭打ちにしたりとツボを押さえてるのがいい。
2曲目以降も、世界中に案外たくさんいるらしいJoy Divisionのフォロワーの一角としてニューウェーブさを基調にしつつも、的確に様々なパターンを繰り返していく。それらについても、ダークなものも少し交えつつも、シンセやらエコーやらを駆使して、どことなくCaptured Tracksっぽかったりとか、時にはエレポップな風味も効かせてみたりと多彩で、そして案外メロディにしても演奏のフレーズやコード感にしても、クールに徹するでもなしにベタに熱い感じが混じるのが面白い。Joy DivisionにおいてはIan Curtisの生前にスタジオで『Ceremony』を完成させられなかった、その偶然によって生まれた“ポップなJoy Division”という空白の可能性に多くのバンドが挑んできて、そういう意味では本作はその相当な上澄みじゃなかろうかとか思ったり。Joy Divison要素ってもう歌い方がちょっと低いだけじゃないか…?とかここまで書いておいて変に冷静になってもみるけども、それでも本作はひたすら良い。一体いつの間にこんなに上手なバンドだったのか。
9. 『luminous』ART-SCHOOL(6月)
残念ながら本作からライブで2曲しか聴けてないけど、その上での感想が「クソデカい音でライブで聴くのが最高なアルバム」って感じ。『Moonrise Kingdom』はぜひライブの定番として毎回デカくノイジーな音で演奏し続けてほしいなって本当に思った。
もっとしっかりしたレビューはしばらく前にもう書いたので、こちらをどうぞ。
8. 『Tomorrow"s Fire』Squirrel Flower(10月)
これが上位に入る、どころかこれが入ってる年間ベストもあまり見てない気がするので、その辺は弊ブログの独自性なのか、いまだにロックに拘泥する半端もんっぷりを露呈してるところなのか。いやいや素晴らしい3枚目だと思うな。
いやでもこの、1曲目にCocteau Twinsとかそういうのを想起させるオブスキュアーな美学を匂わせる曲を置いておいて、それを自ら2曲目の端的にオルタナ極まった楽曲で平気でブチ破る様とか最高だと思うけどもなあ。さっきまでCocteau TwinsだったのがあっけなくSmashing Pumpkinsになっちまったっていう。Big Thief辺りと存在感が被っていたりするけど、こっちの方がより露骨にオルタナティブロックしてるなあって感じがあって、リヴァーブが効いて繊細そうなボーカルの割にあちこちでギターがハウリングしたり重く歪んで棚引いたりしてるのを見るに、延々と幸せな気持ちになる。
それにしても、楽曲構成の思い切り加減がいい。2曲目『Part Time Job』はそれなりに間奏もあった上で僅か2分弱という極まった切り詰め具合で、かつそう感じさせない自然さがある。思うに、同じメロディ・コード位進行のみを繰り返して1曲を作ることに躊躇がなく、その一つの雰囲気でしっかりと押し切ってくれてるのが楽曲の短さを呼び寄せるんだろう*5。そして、こういう音楽性のバンドならアルバムを3枚も重ねてると、キーボードとか入れたくもなりそうな気になりそうなものだと思うのに、ひたすらギターの轟音で押し切ろうとするスタンスが、なんだかとても頼もしく感じる。ギターって、本当いい楽器だと思うよ。
7. 『ひみつスタジオ』スピッツ(5月)
今回は実によいスピッツでした。リードシングル『美しい鰭』*6の時点で意外とこれまでそんなにやってない“ファルセット”を有効活用したしっとりした出来になっているのは興味深く、また中盤『手鞠』以降は最後までいい曲が連続していく。というか『手鞠』自体がめっちゃ透き通った感じがあって素晴らしい。ラスト前の『讃歌』のいきなり歌が始まり、近作ではなかったほどの高音にサビで至る様には精神の飛翔の尊い感じがするし、やはりいつからかラストの曲はパワーポップとなっていたそういう類だと思われた『めぐりめぐって』も終盤に意外なロマンチックな展開を見せるなど、純粋に楽曲のクオリティとちょっとした味付けで魅せてくれる。なので、珍しくメンバーが全員で替わるがわる歌う『オバケのロックバンド』の異質さもまあご愛嬌。
ここまでキャリアのあるバンドからこれほど普通にいいアルバムを出されると何を言えばいいのやら。各曲解説をするくらいしかない。また数年後、いい感じのやつをお願いします。それにしても一度はライブを観たいな。。
6. 『Hadsel』Beirut(11月)
ジャケットを見て、あれっなんか随分変わったなあ、と思ったけど、調べたら今回はノルウェーのしかもかなり北部の方に滞在したのか、とその意外さの性質に不思議な納得をした。
そして、その音楽性のどこか神秘的な寂しさをたたえた様についても、連れ添った楽団を解散させてノルウェーの寂しくも美しい町を拠点にひとりで制作をしたと聞いて、ああなるほど、だからこんなに心細げな美しさに寄ってるんだ、と思えた。リズムボックスを用いたいい具合にチープな楽曲は彼は昔もやってたけど、本作で聴くそれは実に雰囲気にマッチしている。なんというか、本作は「一人で大体全部作ってる」という背景を知ることで美しさが増してしまうタイプの作品だとは思う。なんか恣意的な評価な感じもするけども、でも一度知ってしまったらそれを外して考えることのできない性質のものも世の中にはいくらでもある。何でもそうなのかもしれない。「寂しい北方の小さな町でひとりで作った音楽」という文字列そのものだけでそそるものがあるでしょ。
楽団としての万能感を失った代わりに、ここでのZach Condonは古いパイプオルガンに導かれて、寂しくも険しい、しかし日々のささやかな祝祭も混じり込んだ清らかさを得た。いいオルガンの音というのはそもそもが必殺の感があって、『Melbu』のオルガンを重ねただけと思われる音像がどうしてこうも途方もない感覚を呼ぶのか。この中にトランペット等の居場所などあるわけがない。ひとりで制作するというのは、メンバーの担当楽器などを考える必要がないということでもあり、ここでの彼はそういう意味で自由で奔放で、それは切なくも気高いことだと思える。
5. 『Lahai』Sampha(10月)
あまりこの人のことを知らなかったから、これを書く段になって多少調べて、実はこれが2枚目のアルバムだとか、歌の客演が多くて歌手として存在感があるとかいうのは作品を何回も聴いた後だった。ここの数行は本作を前にすればどうでもいいな。
とても美しい音や響きや余白に溢れた、素晴らしいトラックがひたすら並ぶ作品だ。洗練の極みのような音色が次々に現れる様は実にロンドンのクラブ音楽という感じがするし、その徹底したサウンド志向はローファイヒップホップとかにも通じる感覚のように思えた。というかこれはもはやジャンルがR&Bなのかどうかさえ定かじゃない。特に冒頭曲含むいくつかの楽曲に現れるAphex Twinばりの高速ブレイクビーツの透き通った疾走感には、夜の闇を自在に突っ切っていくような快さがある。どこまでも透き通ったトーンが響いていくかと思えば意外なところでビートが詰まったり途切れたりして、ちょっとした切り替わりがサクサクとトラックを進めていく。
そのようなトラックに乗るボーカルもまた美麗で、ガッツリとラップするでもなくおおらかに歌い上げるでもなく囁くようなその質感にはR&BにおけるSSW的なものを感じさせてくる。Frank Oceanとかと同じような。様々な客演ボーカルも効果的に挿入され、華やかさよりももっとスッと入り込んでくる感じがなんか爽やかだ。あらゆる形で挿入されるボーカルも、まさにサウンドとしてのボーカルという風で、その上でメインの力強いラインが中央にあり続ける様は、やっぱ歌うめえ人なんだな、とこれを書くときに仕入れた情報に納得する。
それにしても清らかなアルバムだなあととても感じる。こういうのがスッと効いてくるような夜を過ごしてみたい。
4. 『夢中夢』Cornelius(6月)
前作でしっかりとしっとりと歌い出した小山田圭吾がとても好きだった。歌もの曲がもっと多ければもっと好きだったのに、が前作の感想だったので、本当に歌もの曲が増えたこのアルバムはとても素晴らしいと思った。
冒頭からボーカルが全開で響いてくる。ボーカルのサウンド的配置の妙は流石で、それらが鮮烈にサウンドとして響けば響くほど、シングルトラックで歌う場面のどこか寂しい感じもまた際立ってくる。不思議な揺らぎと反響に満ちたサウンドは魔術師的だけど、本作ではそれらと歌は対等のように感じる。フラットな歌い方を元々していたけども、本作はそのような世の中にそれなりに膾炙した歌い方の、ひとつの研究の結晶的なものでもあるかもしれない。そしてそのような歌という軸があるからなのか、サウンドコラージュとしてよりももっとアンサンブルとしてはっきりと演奏が聴こえてくる。2曲目『火花』とかなんなら相対性理論の曲みたいでさえある。ついでに、歌詞の殆どが小山田自身というのに何気にびっくりする。自身がインタビューで言及するくらいには、本作はCorneliusなのにSSW的な作品だ。まあ色々あったもんな…。
特にびっくりしたのは『環境と心理』で、ここまで来るともうもはやシティポップだ。2023年、まさかCorneliusでここまで踊れるなんて。まあMETAFIVEからの流用だけどもそれでも。マシンスネアの入り方があまりにポップすぎて笑ってしまう。何となく楽器を弾きながら歌ってできたというエピソードからして、サウンドスケープ重点なCorneliusの制作イメージからかなり離れて、というかえらく普遍的でベタなところに現れたもので。
あと、『霧中夢』の、サウンドのうねりが一瞬途切れて「Dream」って一言言うの、ゆらゆら帝国の『ソフトに死んでいる』リミックスのオマージュっぽくある。こんなに歌いまくるCorneliusのライブとか観てみたいな。
3. 『the record』boygenius(3月)
実力ある女性SSW3人が集まった、昔で言うところのスーパーグループ的な存在なんだということをぼんやり知りつつも、他の2人をそんなに知らないから、個人的には正直なところ実質Phoebe Brigdersの新譜みたいな具合に受け止めてる部分は少なくはない。ちょっと調べたらかなりそうではなさそうだけども、別にそういう誤解込みでも素晴らしさは間違いないし2023年も終わってるし時効だろうか流石にまだか。
いつぞやのConor Oberstとのコラボの時といい、Phoebe Brigdersという人はコラボする時はバンドに拘ってんのかな。2曲目から早速爽快なオルタナ仕込みの歯切れのいいバンドサウンドを響かせて、ボーカルの素晴らしさとかはともかく、別に他のボーカルの作品だったとしてもこのバンドの音とソングライティングはすげえ好きだぜ、ってなる。もちろんその上にいかにもな具合で連なるコーラスワークはとても楽しい。そんな調子の最高なバンドサウンドの楽曲が幾つかあり、一方でアコギ弾き語りに3人のボーカルが美しく乗るトラックも幾つかあり、もう少しアブストラクトで切なげなサウンドの楽曲もあり、つまり何でも最高だな。ケチのつけようなどない。これが売れたってのは、そりゃそうだろと思いつつもとても良かった。。。
静かな曲もバンドな曲もどっちも素晴らしいけども、やっぱところどころ叫び出すのがいいなって思う。静かに沸々と囁くように歌って溜めに溜めといて、案の定爆発する『Anti-Curse』とかほんと最高だな。あっけない終わり方含めて完璧だ。なんか、なんもかんもこんなに最高だと後で振り返った時に寂しくなったりしないかなって心配してしまいそうなくらいに最高だ。
2. 『This Stupid World』Yo La Tengo(1月)
エレキギターを担いだYo La Tengoはやっぱ最高だ。しかもそんな曲ばかりが詰まったアルバムを出してくるなんてどうかしてる。冒頭『Sinatra Drive Breakdown』の不穏なベースラインと、そして明らかにデタラメな不協和音ギターが格好良く響き、そしてその後ベースラインに似つかわしくないえらくポップでゆったりしたメロディが入ってくる時点で、あっ、やっぱこういうYo La Tengoは向かうところ敵がない、と思った。続く2曲目も歪んだギターにポップなメロディが響き渡って、3曲目でアコギだ、ってなった後にすぐまたギターノイズがずっと浮遊し続けるトラックだと判明する。おいおいどうして今回そんなにノイジーなエレキギターばっかりなんだ。おれみたいなやつを喜ばせて何をしようというのか。
時に実験的な長尺曲を入れてくる彼らには珍しく、本作は9曲50分弱と尺も比較的聴きやすい。それでいて彼ららしい奥深い曖昧さを生み出すサウンドや歌の妙もこれでもかと注がれている。どこにも辿り着かないノイジーな反復の吹き上がりが延々続いていくタイトルトラックの、それでもそこに強引にポップで柔らかなメロディを乗せてくる様はまごうことなくYo La Tengo。そして最終曲『Miles Away』の、それまでのバンド感と異なりもっとトラック然としたビートの中を柔らかなギターのエコーとノイズが満たしていく様はかれらのぼんやりの表現のまた新たな1ページだろうか。これで締めるところははっきり言ってすごく格好いい。
当初はこれを1位にするつもりだった。これを書いてる今でも1位は別にこっちでもいいなあとも思わないでもない。
1. 『no public sounds』君島大空(9月)
すんでのところで今回の1位はやっぱこっちがいいやってなった。それまでは2位だった。
君島大空という人については元々すげえギターが弾ける人、というのを聞いてた。でそんな人の作品を何年か前にはじめて聴いた時、案外に正統派な文学的SSWな感じで、いやいい作品なんだけど、あれっ、って気持ちになった。『映帶する煙』においては、なんかそういうオーセンティックさを食い破ろうとする存在が覗くものの、基本はそういうのが基調だったろう。
本作の曲目を見よ。あるいは1曲目『礼』のイントロ、どこのハードロックだ?という困惑をよそに展開される、前作が嘘のようにマッシヴなセッションを聴け。そしてそんなところから何の脈絡もなしに飛び出してくる繊細なアレンジとセンチメンタルな歌を聴け。つまりは、前作で蠢きつつも食い破りはしなかったものこそが、バグってメタってグチャって叫べるなら叫び倒したいくらいのドロリとした何かこそが、本作の主役だ。内に秘めてた原液ドロドロ、SSWの形式よりも自由なフィーリングとナイーヴさがこんがらがりきったボーカル回しとソングライティングで、温故知新などと知ったことかとインターネットネイティブの理不尽極まりないフリーフォームで叩きつけ続ける11曲43分。前作までの風流さがノイズの向こうに滲んで消えていく。
ブリグリみたいなサビのメロディをひたすらロウな音で叩きつける『c r a z y』に、ノスタルジックなセンチメンタルさが高速ブレイクビーツで突如謎の高速機動を見せるのがエモい『映画』、ナイーヴにしっとりした日本的なR&Bさを咀嚼しきった『curtains』、ノイジーに引き攣った轟音と夢見心地さがブチ切れてささくれたボーカルに切り裂かれていく最終曲『沈む体は空へ溢れて』と、もうやりたい放題の本作は、表現力の化け物としてのこの作り手の圧倒的さをまざまざと見せつけてくる。あちこちでギターもドラムもそれ以外のサウンドもひたすらに爆発と混沌と性弱と洗練とを繰り返し続け、その変幻自在に全開なトラックの漲り具合はかつての七尾旅人『ヘヴンリィ・パンク・アダージョ』を思わせるようなある部分では凌駕するような。ひたすらにそれぞれに爆発したりキメ切ってたりする楽曲が並び続ける様は圧巻で、特にひたすらドラマチックに展開し続ける『讃歌』『16:28』というクライマックス級の曲が2曲続くところの密度はものすごい。いい意味で、曲順考えろよアホかと思えてしまう。ロマンチックなイメージをどこまでも展開し炸裂させ続けられるスキルがあってのもので、それが出来てしまうこの人は常軌を逸している才能なんだと、強く思わされた。
…こんなセンスドバッドバのものを出して、次はどうすんだよと、もしかして2002年の『ヘヴンリィ・パンク・アダージョ』を聴いた人も思ったりしたんだろうかと、なんか歪んだ思いを馳せる。そして、こんなすげえトラックがSoundcloudの片隅で埋もれる訳ねえだろと本人のステートメントを一旦斜めに見つつ、でも自分もその片隅の埋もれたものだった身として、ステートメントの訴える内容に無感情ではまるでいれなくて、なんとも収集などつくはずもない感情とか感傷とかの果てでこのアルバムはずっと記憶しておこうと思う。
・・・・・・・・・・・・・・・
おわりに
以上25枚を見てきました。ギリギリ1月中に投稿できました。
2023年はマジで時間がなくて、特に9月以降はまるで自由がどんどんなくなっていて、正直ずっと嫌な思いで暮らしていますが、なんとか生きています。いろんな敬愛する人が亡くなったりしてやるせなく、しかしそのやるせなさで書いた投稿がとりわけ読まれたりもして、複雑な気持ちがしつつ、またひどい戦争が始まり、政治はどうしようもなく、そして2023年が終わり新年を迎えて早々に地震と衝突事故と様々な酷いことと…。
そんな状況を音楽が救ってくれる、などと思えるはずもなく、何ともに何ともですが、それでもこうやってたまに頑張って何か書こうとしたくなるほどには、音楽はいまだに縋り付いていたくなるものだと思うので、2024年も全くいい展望が社会的にも個人的にも見えてこないところですが、細々と頑張っていこうと思います。
それにしても、今回のリストを振り返って、やっぱギターって楽器、好きだなあと心底思います。それではまた。




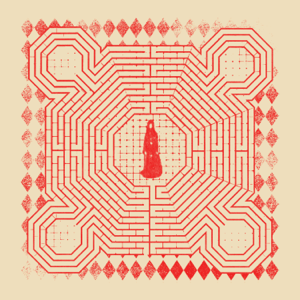


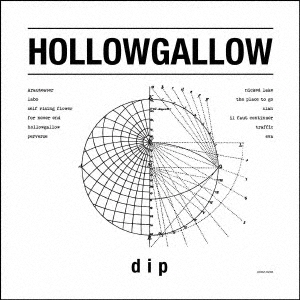
![cero/e o [CD+Blu-ray Disc]<生産限定盤>](https://cdn.tower.jp/za/o/3W/zaP2_G3766003W.JPG)










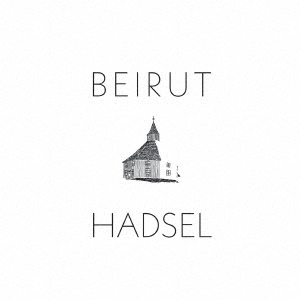


![boygenius – The Record (2023, Blue [Blue Jay], Vinyl) - Discogs](https://i.discogs.com/H5bGyDPDjDH2uASz8M2IuaiF4ze72qR2uHWwPQo-gAo/rs:fit/g:sm/q:40/h:300/w:300/czM6Ly9kaXNjb2dz/LWRhdGFiYXNlLWlt/YWdlcy9SLTI2NjAx/NjQxLTE2ODAzNTMw/MzAtNTU4Ny5qcGVn.jpeg)

