
ART-SCHOOL全作品レビュー記事のリマスターという体裁の仕切り直しの一連の記事の11個目。筆者のオルタイムベストで3本の指に入るくらい好きなアルバムです。邦楽だけでオールタイムベストを作るならこれが1位です。当然2003年のアルバムでも1位。
重くて暗くて情けなくて綺麗で救いようがないです。虚無のベクトルで作品全体がどこか透き通っていた『SWAN SONG』と比べてももっと様々に乱れていて、見方によってはこっちの方がより引き裂かれて悲痛な感じがします。タイトルからして「愛と憎悪」に引き裂かれてるわけだし。そしてバンドの関係性もとっくに崩壊していたことから、このアルバムの後にメンバー2人脱退して活動停止と、あらゆるネガティブさが集まったような状況。
なのに、なのか、だからこそ、なのか、これは信じられないほど感覚と音のスタイルとが奇跡的に噛み合った、本当に素晴らしい作品です。一部ではバンドの最高傑作とも言われるかもだけど、それ以前に、とても感覚を揺さぶられる、というか、世界の見方が変わってしまったまである、個人的にとてもとても大事な作品です。
前作となる先行シングル『UNDER MY SKIN』のレビューは以下のとおりです。
また、アルバムとして前作となる『Requiem For Innocence』のレビューはこちら。色々と比較して聴くとまた面白かったりするかもしれません。サブスクにはありませんけど。
何回目の書き直しか分からないけど、何を書こう。
ART-SCHOOLの「Love/Hate」をApple Musicで
前書き
今回は流石に前書きの段階から書くことが多いです。
異様な楽曲リリースペース
シングル『EVIL』から始まる2003年のART-SCHOOLのリリースラッシュの総決算がこのアルバムになります。前の記事で書いたことをもう一度書くと、
『EVIL』2003年4月11日リリース 4曲
『SWAN SONG』2003年7月30日リリース 2形態7曲
『UNDER MY SKIN』2003年9月29日リリース 3曲
『LOVE/HATE』2003年11月12日リリース 14曲*1
となり、どんどんリリースペースが加速していっていることが分かります。シングル等からの収録は5曲で、残りの9曲、初回盤ボートラ1曲を含めれば10曲がアルバムで初出となる楽曲。前作アルバム『Requiem For Innocence』が11曲入りで既発4曲・初出7曲だったことを思うと*2、その創作ペースの加速っぷりが分かりやすいかと思います。インタビュー等から、『EVIL』『SWAN SONG』はそれぞれのレコーディングが行われ、『UNDER MY SKIN』についてはアルバムと同一のセッションから生み出された形なので、アルバムセッションではシングル『UNDER MY SKIN』の3曲とアルバム初出の10曲の合計13曲を少なくとも完成させたらしいです。後述するとおり、本当にボロボロで稼働してるのが不思議な状態のバンドが、よくここまで様々な充実した楽曲を短期間に量産したものだと、つくづく不思議に思います。
2枚組構想について
こんなリリースペースな上で、少なくとも当時は木下理樹本人の口から「アルバムは2枚組になる構想もあった」と話が出るのは、驚異的なことだけどでもありえないことでもなかったと思います。2003年だけで24曲もの新曲リリースして、これだけでアルバム2枚分になるので、史実としても2枚組構想はやろうと思えば可能だったわけです。果たしてシングル等の、現実ではアルバム未収録となったカップリング曲を活かした2枚組構想だったのか、それとも未発表曲や第二期以降の楽曲を含む構想だったのか、気になるところ。
当初は2枚組のアルバムを考えてたんですけど、2枚組は聴かれないなって気付いて止めたんですけど(笑)、曲はたくさん出来たので、“EVIL”みたいな攻撃的な曲と“BUTTERFLY KISS”や“しとやかな獣”みたいなメロウな曲をごちゃ混ぜに入れたっていう。だから、通して聴くといびつに聞こえるかもしれないですけど、そのいびつさにありのままの自分がいると思う。
少なくとも、以下に改めて述べるバンドの状況と反比例するかの如く、木下理樹の、そしてバンドの創作能力がピークに達していたことは間違いなさそうです。
(壊滅的な脱退を前提とした)終末的なバンド状況

『SWAN SONG』の記事でも述べましたが改めて。
一連の記事で唯一に近い形で出典にしているMARQUEE56号(及び58号)の木下理樹全曲解説インタビューにおいて、このアルバムの制作時期について、こんなコメントがあります。
(この時期にレコーディングした楽曲数が膨大なことを指摘され)
そう。ひたすら曲がある上に休みがない、イコール、メンバーと常に一緒にいるってことだから。毎日レコーディング中お酒を持ち込んで…(笑)呑んでやってましたね。
既に『シャーロットe.p.』くらいの時期のストレイテナーとのスプリットライブの時点で移動の車が別になるくらいの状況で、『Requiem For Innocence』録音時に上記と同じインタビューで「その頃はバンド内部が最悪だったし(笑)」とコメントされ、そして『SWAN SONG』の頃には「このレコーディングしてるときは「あ、もうこの先はないな」と思ってた」とコメントしているように、既に関係性はとっくに崩壊し、確か2003年の中頃には既に日向秀和と大山純の脱退も決まっている状況で、それでもバンドも録音も続いたという事実があります。この時期の木下の飲酒アピールは幾らかは中嶋らも等の先人に憧れてやっている節もあるものの、割と本当にせめてもの救いを求めての行動だったところがあるんだろうと思われます。
それで、これだけ人間関係が拗れてしまうのは、幾らかはやはり、木下理樹というバンドの中心人物の性質が関係してしまうもので。実際、このバンドはメンバーチェンジについては日本においてくるりの次にネタにされるバンドなので。
ただ、彼は別にそういう人間関係の拗れをそんなにバンドの楽曲の中に表現することを頻繁にする人間では本来ないです*4。『Requiem For Innocence』の中で辛うじてそう感じられるのはおそらく『サッドマシーン』『乾いた花』くらいのもので、本来はそんなもの。この時期より後だって、そういうことが楽曲中に表面化してくる場面というのは相当に限定されているような気がします。
本当に例外的に、この時期だけ、そのようなバンド関係の殺風景さ、その無情さや無力感から出てきたようなフレーズが歌詞に出てきます。これを、そうやって吐き出さないとやってられなかったのか、単純に曲数が多いので歌詞を書いていく上でそういうことも歌にしないと回らなかったのか*5、こういう苦しみを歌詞にすることの価値を重視したのか。おそらくその全てであり、そのどれでもないのかもしれません。
僕には花があったのにね いつか散って消えてったね
そうさ今日はひきがえるの様に
はいつくばって ただ願うんです
『LILY』(『SWAN SONG』収録)より
狂わせて 狂わせてくれ今日は
誰のため 鐘は鳴り続けるのだろう
完璧で 誰からも愛し愛されて
次は違う 人に生まれ変われるんだ
『MEMENTO MORI』(『SWAN SONG』収録)より
いつから穴があいたっけ 何も感じなくなって
手を伸ばす、その度に指先は何も触れなくて
誰かを裏切る度に これ以上はもうなんて
閉じたまま見た空 何か少し澄んでた
『UNDER MY SKIN』(同名シングル収録)より
アルバムにもこれら先行リリースされた楽曲群のネガティブさを引き継いだ・発展させた楽曲が多数存在します(というか全部そうか…?)。これらのような無力感方面のネガティブさの頂点として、アルバムのタイトルトラックが存在するのは木下理樹本当にギリギリのところで頑張った…という感じがします。深刻な機能不全のはずのバンドもその状態で新曲10曲を含むアルバムを作り上げてしまうのは何なのか。いくら契約があったかもしれないとはいえ、そのゾンビ状態での創作能力は驚嘆に値します。
大山純というギタリストについて

『SWAN SONG』の宣伝チラシより。ヤバい時期だけど顔がいい。
この終末的なバンドの状況に一番苛まれたのは、ギタリストで、CDのイラスト等も担当していた大山純だったようです。その痛々しい状況は、2003年末の脱退後、2008年にストレイテナーに加入するまでの期間の大半を、ずっと音楽業界から離れていたという年譜からだけでも察せられるものがあります。それ以上のことについては、ストレイテナーのヒストリー本にも記載があるし、普通にインターネット上で本人がTwitterで連投していたもののまとめや、それを「新成人へ向けたメッセージ」の記事でもう少し整理して書き直したものなどが普通に見れます。
それらから分かることは、メンバーの求める音が出せなくて、借金して機材を買っても苦悩し続けて、かつての音楽への・ギターへの愛が失せて、すっかりステージ恐怖症に陥ってしまっていたこと。この時期の彼は「ギターを背負っただけで震えや吐き気、冷や汗」の状態で、ずっと自分の演奏が責められる妄想に頭が埋められてしまって、かなり深刻に精神を病んでいた状況だったといいます。酒を飲んだりしてギリギリ保っていたのか。
でも、そんな状況がいつからなのかはよく分からないけど、それでも辛うじて、ライブで弾いて、レコーディングで弾いて、それでこれだけの名曲の素晴らしいギタープレイが並んでいるのは、本当にギリギリの中で何とかフレーズを曲に添えていたんだろうなと思われて、何と言えばいいのか…感謝しかありません*6。この時期のギタープレイの特徴については後の項目で述べます。
彼の場合、脱退後もしばらくはかなり困窮した状況が続いていたようで、その辺の話は読んでいて普通に辛くなります。ストレイテナーのメンバーとして戻ってこれたからこそ話せる内容なんだろうと思います*7。
それにしても、2003年のART-SCHOOL脱退組の2人はそのまま後に2人ともストレイテナーに加入するわけですが、こういう事情を思うと下手に茶化す気もしなくなります。
CD概要
というわけで、オルタナティブロックバンドART-SCHOOLの2枚目のフルアルバム。初回盤なら15曲。ボーナストラック前の無音を除いても55分近くあり、これだとこのバンドのオリジナルアルバムで最長の尺になります*8。こんな大きなアルバムを出してメンバー脱退してレコード会社からもクビを切られて、という流れはでも、悲しいことは悲しいけど、今の地点から見ると何かをしっかりやり切った感じにも見えます。
曲間なし・クロスフェードの展開
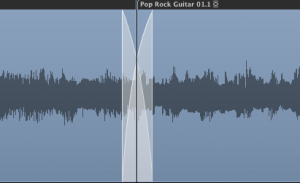
本作はまず、曲間無しに、1曲目から14曲目までずっと演奏が鳴り続ける、という特徴があります。多いのは、曲の終わりのギターノイズの余韻がパッと消えた瞬間に次の曲の演奏なりSEなりが間髪入れず鳴り始める展開。もしくは曲によっては前の曲の余韻と次の曲のSEがクロスフェードで入っていくこともあります。
このようなことで何が起こるかというと、通しで聴くときの、息も付かせず次々に曲がやってくることによる緊張感だったり、パッと曲調が変わることによる場面転換的な質感の強調だったり、その効果は様々なものが考えられます。欠点としては、トラック単体を取り出すと前の曲の余韻が冒頭に入ってしまったりアウトロの余韻が強制的に断ち切られたり、といったことが出てしまうことです。
14曲で52分以上のボリュームを一気に聴けることというのは生活習慣によってはなかなか難しいこともあると思いますし、時間が取れても52分連続は聞き終わったら疲れてしまうかもしれません。でもその代わり、1枚を通しで聴いた時の印象の残り方は、普通に曲間があるものとは少し違ってくるとも思います。月並みな言い方をすれば、1本の映画を見終わったのに近いような感覚がそこにはあるかもしれません。
その昔、Princeは『Lovesexy』というアルバムで、CDにも関わらず、収録曲9曲を1つのトラック扱いとして収録し、楽曲を飛ばすことを許さない形式でリリースしたことがあります。また、Princeは2015年のグラミー賞でプレゼンターを務め、その際にはサブスク等の普及により楽曲単独で聴かれることが増えた世情を踏まえた上で「アルバム…って、覚えてる?アルバムは今でも重要だ」という発言をしていました。そんな「単体の楽曲の集合体というよりも、全体でひとつの作品として響いてくるようなもの」を、この『LOVE/HATE』もきっと目指していたんだろうと思います。
「グランジのアルバム」としての『LOVE/HATE』

これについては「最初3曲はともかく、その後はそうでも…」ということになります。日本の新進グランジバンド、みたいな売り出し方をされていたりもする当時のこのバンドですが、そもそもがっちりとグランジしている曲ってそんなに多くないです。『Requiem For Innocence』でグランジって呼べそうな曲が何曲あったか考えると、グランジ色が比較的強かった第1期でも、そこまでグランジ一辺倒な感じは全然ないなと思います。まず、メジャー調でオンオフの激しいやつをやってもあんまりグランジ感が起きない、というところがあります。
でも、コード間の意味でも、演奏の具合的にも、冒頭3曲のグランジ感は中々のものだと思います。先行シングル『EVIL』の装飾を極力廃した直球のグランジに、R&B風味の効いたポストロック的要素とグランジを強引に結びつけた『モザイク』も再録し、そして冒頭にこの時期の荒涼感とアルペジオの感じとをグランジと結びつけた『水の中のナイフ』を置いて、この3曲を連続で聴いた時のグランジな流れは、このバンドの作品で最もグランジな場面だと言えるでしょう。勿論、Nirvana式のオンオフスタイルのグランジではあるけども*9。
あとは、グランジなコード感でノイジーなサイケデリアを展開する、いい意味でグランジ歌謡と言いたくなる『アパシーズ・ラスト・ナイト』とかもまだグランジ寄りか。グランジ要素は前半に固まってる気がします。アルバム後半はそういう意味ではまた違う雰囲気かもです。
また、グランジっぽい曲に限らずですが、この時期の歪ませたギターの、重く鈍い、時に粘り気を感じそうになる響きは、ザラザラとハイが効いている感じの『Requiem For Innocence』の時期のギターの音と対照的なように思います。どっちがいいという話ではなく、この時期のサウンドの大きな特徴のひとつだというところ。
単調な、だからこそ虚無的な情緒のあるアルペジオ

“アルペジオ”という、ひとつの和音を分散して演奏する奏法については、The SmithsとかThe Stone Rosesとか、日本だとスピッツとか、そういったバンド群が華麗なアルペジオを弾いて、時にドラマティックに、時に可愛らしく楽曲を彩るのが普遍的なイメージなのかなと思います。
ところが、ART-SCHOOLにおいてアルペジオのあり方は少し違っていて、「曲のコードが展開しつつも、アルペジオは常に同じ2音か3音を繰り返し続ける」というのが彼らの基本スタイルです。特に「LOVE/HATE期」はこれがかなり徹底され、とりあえず静パートのバックに3音アルペジオ、と言っていいくらいに多用されます。この時期の彼らの楽曲が時にワンパターンと批判される原因のひとつでもあります*10。
でも、この単調で曖昧な、多くはadd9の響きを持たせられたアルペジオは、楽曲のコード感をひたすら曖昧にしていく効果があります。楽曲のコード感が曖昧になるとどういうことが起こるか、次の項目で考えてみますが、徹底してこの奏法を繰り返すことにより、この時期特有のコード感みたいなものが湧き上がってきて、それは作品全体の情緒の具合にも大きく影響するところです。
ワンコード感とその中をベースラインだけ変化していく展開

この要素はこの時期のみならずこのバンドの音楽的な魅力の核心部分のようにも思えるけども、とりわけこの要素が輝いているのはこの時期だと思います。
ワンコードの楽曲というわけではないんです。ルート音がしっかり動いて、楽曲としてはしっかりコード進行がある。あるけども、そのコード進行を無視するかのように、延々と同じコードのアルペジオやカッティングが鳴り続ける、というアンサンブルがこの時期は非常に多用されます。そうじゃない楽曲を探した方が早いくらいに。
これによってどんな効果があるか、文字で説明はしづらいところですが、逆にきっちりとコードチェンジ感があるとそのコードの変わり目で何か雰囲気が切り替わるような感覚がするのに対し、このようにワンコード風にしてしまうとその切り替わりが起こらない、それによって曲のコード感がずっと曖昧に保たれるのが、その大きな効果です。コードが切り替わらない、つまり雰囲気が切り替わらないことによって、雰囲気の停滞感や、それに伴うぼんやりした感覚が漂ってくることになります。しかしながら、太いベースラインによってルート音は移動していくために、全体で見るとちゃんとコード進行は起こっていて、そこに当時絶好調だった木下理樹の綺麗なメロディが乗っていきます。
ここにこそ、ART-SCHOOLというバンドの独特のコード感の秘密が隠されています。逆に言えば、この要素が特に鮮明なこの時期の楽曲を好むかどうかは、このコード感を好きになれるかどうか、という部分も大きいんだろうと思います。別に彼らがオリジネイターではなく、昔から成されてきたことだけど、でも彼らがここで執拗にこのアンサンブル形式を繰り返したことは、とても印象に残ることだと思います。それは、当時のバンドの作品に漂う濃厚な虚無感と深く関係します。まるで神経が損なわれてしまったかのように執拗に続く同じコード感、という印象は「LOVE/HATE期」の楽曲特有の魅力です。しかもそこで鳴る同じコードがadd9等の曖昧なコードであることも余計に、感覚が曖昧になってしまったような情緒を抱かせます。
同じコードでルート音だけ変えることで曲展開を作っていくパターンの先例をいくつか確認しておきます。
Smashing Pumpkinsの代表曲にして彼らの最もドラマチックな楽曲のひとつである『Tonight, Tonight』のサビ以外の部分はまさにこのパターンで、それは弾き語りバージョンがより確認が容易です。
もっと振り返れば、The Beatlesだって同じ様なことをやっています。特にホワイトアルバムの時期のJohn Lennonはこの奏法に熱中していた節があり、この曲はその代表曲。延々と同じ音が続いていくアルペジオと、その下でベースが降下していくことによって生まれる渇いた空気感は、1968年の録音と思えないくらいにニューウェーブ的でオルタナティブロック的です。
木下理樹の重要な音楽的メンターの一人であろうRobert Smithにおいてもこの手法は大いに使われているところで、もしかしたら木下のワンコード志向に一番影響を与えたのはThe Cureなのかもしれません。この曲も、よく聴くとギターのカッティングの響きがずっと同じ音で鳴ってるのが聴き取れます。アンサンブルとしてはベースやシンセでコード感が移り変わりつつも、密かにずっとミニマルな刻みを入れるギターがこの曲に拭いきれない鬱屈した停滞感を付加しているように思えます。勿論それが魅力です。
徹底的に虚無志向で、救われようのない世界観

「LOVE/HATE期」の楽曲のネガティブさは、基本ネガティブな作風で知られるこのバンドの歴史の中でも突出しています。この時期の末尾である『LOVE/HATE』において最もポジティブらしいことを歌ってる楽曲が『しとやかな獣』という時点で、全然“救い”のようなところに辿り着けていないことが分かります。あとで歌詞を読んでいきます。
この時期の詩情を支配しているのはやっぱり「虚無感」ということになります。それは一方では映画や小説の世界でのダンディズムめいた孤独の感じに憧れつつも、バンドの壊滅的な状況や私生活の荒廃から、現実における無力感やら喪失感やらを感じていたことが非常に大きいんだろうと思います。この時期の歌詞が100%妄想から出てきたものとは全然思えないし、木下理樹本人も当時の自身の内面のことを歌詞にしていたことをインタビュー等で吐露しています。
この時期ぐらいからカット・アップに魅力を感じなくなって、自分の内面のことをしたね。多分言いたいことの方が強くなったんじゃないかな。イメージを喚起させるよりも『俺の気持ちを聞け!』という感じ。
『MARQUEE Vol.56』の『Dry』に関する記述から抜粋
完璧、虚無でしたね。非生産性…(一同笑)。何も生産的なことはしてなかったな。
(インタビュアー:えっ?でもその時期にこれだけの曲は書けてる。)
曲は書いてましたね。詞も書いてた。自分で“立て直そう”としているときの方が、確かに際立ったものが出てくるのかな。
同じく『MARQUEE Vol.56』の『アパシーズ・ラスト・ナイト』の記述から抜粋
ART-SCHOOLの暗さにも色々ある*11けれど、この時期は徹底して、「孤立した状態の虚無感」みたいな感覚で、それは『SWAN SONG』において一旦純度の高い形で極められて、その後の『LOVE/HATE』においては、そこに幻覚めいたネガティブな妄想物語とノスタルジーが陸続きになった何かも混入され、様々な光景が映りながらも、そのどれもがひどく虚しい情緒に彩られています。
だけどその、まるで「救いのない状態のまま夏休みが永遠に続いていく」ような感覚の光景をこのアルバムで幾つも表現し切ったことは、状況的にひたすらしんどいことしか無いような立場の木下理樹が、それを奇跡的に美しい形で歌詞や歌に昇華していることの証左でもあり、その、当時の姿を見る限り全然タフには見えない身体で、よくギリギリ持ち堪えてこのアルバムのリリースまで辿り着けたもんだと、その事実だけでちょっと感動しそうになります。関係性が崩壊しているくせに、それでも彼に連れ添って行ったメンバー達も偉い。いくら感謝してもし足りない気持ちです。
坂本麻里子氏のライナーノーツ

前作『Requiem For Innocence』に引き続き、坂本麻里子氏がライナーノーツを書いています。氏の文章は時に、アーティストの情緒に突き動かさたリリシズムが滲む文体なのが特徴的で、『Requiem For Innocence』のライナーの前半はかなりアルバムの詩情に寄り添った形で、音楽自体の解説を超えてまるでシンパシーを告白する手紙のような内容になっていましたが、この『LOVE/HATE』においては、とりわけ前半部分でここまでのバンドの経緯やリリースの順序等、及びこれから書くような楽曲の内容を(その裏のバンドの内情は流石に語れないにせよ)端的な形で記載してあって、正直この記事のここまでとこれからの文章を読むよりも遥かに端的に内容を抑えてあって分かりやすい、明瞭で示唆に富んだ文章になっています。
後半の文章はややポエジーな領域に踏み込みますが、ただここで思うのは「ポエジーな要素ゼロでART-SCHOOLを聴くことに何の意味があるんだ?」ということです。音楽だけを純粋に聴く、ということが時折議論になることがありますが、個人的には「歌詞付きの音楽でそんなことは不可能だろ」という思いがあります。なので、氏がここで綴った木下理樹の詩情に関する解説は、様々に解説しすぎな気がしつつも、でもそうやって語りたくなる気持ちはとても分かるし、内容だってそのとおりだと思うんです。
この先の文章で、もし彼女のライナーノーツにの内容に何か付け加えられる内容が含まれていれば、大変光栄なことだと思います。そりゃ文章量が限られたライナーノーツと、幾らでも好きに無限に書き散らせるこんなネット上の落書きとじゃ、条件は違い過ぎるんですけども。
本編
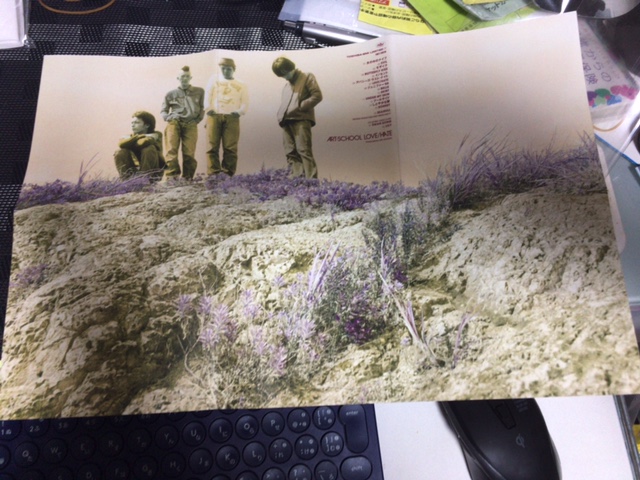
1. 水の中のナイフ(3:16)
鈍重に歪んだパワーコードを冒頭から強く響かせる、今作のグランジ面を強く強調しつつも木下節とも言えるメロディと詩情とを高らかに叫び倒す名曲。木下自身は「単にノリのいい曲」と言っているけど、歌詞にしろサウンドにしろ、いきなり気迫に満ち溢れている。まるで、相応の気迫が無ければ動かない機構を無理矢理動かしているような、バンド自体を無理矢理引きずってるかのような情緒がどこか感じられる気がする。
4つのパワーコードで、マイナー調気味のゴツゴツした響きの組み合わせで繰り返していく様は、ずばりNirvanaの雰囲気そのものを呼び出そうとしているとしか思えない。上記のタワレコのインタビューで「日本のNirvanaみたいに紹介した方が都合のいいレコード会社側の事情があるんでしょ(笑)」と言わんばかりの挑発的な発言を木下がしているけども、そんな思惑に正面から乗ってやるよ、と言わんばかりのイントロで、また、ひたすら衝動だけみたいなギターカッティングで始まる『Requeim For Innocence』と比べても、遥かに何かの事情が重く苦しくなっていることを告げるようでもある。
イントロの後は、同じコード進行にも関わらず、件のadd9の3音アルペジオと木下のメロディによって、調がメジャーなのかマイナーなのか分からないような、宙吊りの雰囲気が生まれている。その感覚がでも、この曲においては不思議と曖昧に落ちず、どこかジャケットの感じを思わせるような荒涼とした雰囲気を醸し出している。音楽的には、ブリッジミュートでパワーコードを弾き続けているからなんだろうけど。この荒涼とした情緒に、木下の細く気だるくへたれた声はとてもよく合う。メロディも、こんなグランジなコード進行からこういうメロディをよく引き出してくる、と思えるものだと思う。
サビは、それまでの4つのコードを下の音から上の音へと並び替えただけの進行なのに、それがエモーショナルで、そしてその上に、今作の詩情を端的に示すような歌詞が、全編シャウトのような歌唱で歌われる。この歌詞で「単にノリのいい曲」なんて、無理があるってきっとみんな思ってる。
いつだって雨が、ただ此処に降りそそぐ
むき出しの傷跡に ひび割れた硝子の瓶に
髪を少しくしゃくしゃにして 笑うあの仕草
あの日から僕は 誰よりも上手に
あざむける様になっていた 裏切れるようになっていた
繋いだ身体のぬくもりも うまく思い出せやしないんだ
やっぱりこの頃には『SWAN SONG』の頃よりも情景を妄想し描写する能力が戻ってきてる感じがある。かつての映画や文学のイメージと戯れてた頃の幸せそうな感じとはかなり情緒は異なるけども。それにしてもここには、荒涼とした光景ではあるけど、そこで苦しく息をする人間の“人間らしさ”が実に人間臭く滲み出してきている。2回目のサビのフレーズはもっとモロだろう。
そうさ いつも光の中 君は淡く揺れていた
そうさ いつも影の中で 身動きさえも取れやしないんだ
この「光の側で美しく触れられない者として存在する“君”と、日陰の側で惨めに這い回る“僕”」の構図は、これ以前の歌詞でも見られたものだけど、とりわけこの後の木下理樹の歌詞世界の重要なファクターのひとつになっていく。
それにしても、次曲と異なり、グランジの形式の中でザラザラとした感情が爆発していることがこの曲の大きな特徴だ。それはサビ後の吐き捨てるような「I wanna be twisted」の呟きが、その繰り返しの最後に悲痛なシャウトになるところにも、また間奏部分のアルペジオのバックで棚引くフィードバックノイズをコントロールを放棄する方向でコントロールしている光景などからも窺える。「I wanna…」の箇所の重く鈍いキメがまた、『Requiem…』の頃の歯切れのいいキメと対照的な、何かが不全になってしまったような感覚を覚えさせる。
曲タイトルは同名の1962年のポーランド映画からの引用と思われる。このアルバムで初出の曲では圧倒的に存在感の大きい楽曲で、ライブでの演奏回数も多く、またベスト盤にも『EVIL』を差し置いて収録された。また、インタビューで木下は、この曲の歌入れが従兄弟の結婚式に出た直後だったとかで、そのときのなんとも言えない感情が出ていると話していて、そういう背景を知ると、歌詞の響きがさらに人間臭いもののように思えてくる。
2. EVIL(3:14)
前曲のグランジ具合に付随していた人間的な感情、悔いや惨めささ捨て鉢さなどのそういったものをアルペジオ等と一緒に削ぎ落としたらこうなりますよ、と示して見せるかのような曲順。特に、前曲最後のギターのノイジーな余韻を強制終了する形でこの曲の無骨なドラムイントロが始まるので、尚更この曲の“削ぎ落とした”グランジという属性は強まっている。
この曲の、本当に様々なものを削ぎ落としてNirvana式のグランジ様式の骨組だけで曲を書いたかのようなスタイルは、グランジバンドと呼ばれた彼らにあっても少々特殊なもので、その様式の骨格自体を駆動させるようなスタイルはBlurの『Song2』に近いものがる。しかし、追加サビのように現れる部分の、歌唱もギターも機械的な駆動域を超えて暴発していくような有様が、この時期のこのバンドらしい情緒の乱れ切った様が表現されていて、悲痛な爽快感がある。
既出曲なので、詳しいレビューは以下を参照。
ねぇ 笑って そう 笑って そう 笑って それだけで
その匂いで その匂いで その匂いで 哀しみで
もつれ合って もつれ合って もつれ合って 僕等皆
羽根になって 羽根になって 羽根になって 堕ちるだけさ
それにしても、歌詞の最後の部分のこの、短いワードの繰り返しでマッドな相互依存を描き出していく様は、本当に爽快な病的さがある。この時期に暗い重いファンが増えたという話は大変よく分かる。似たようなグランジをやっているアーティストで比較しても、視野が自由にブッ飛んでいける浅井健一には逆に出せないタイプの、思い詰めた袋小路の情念の感じがここにはある。
3. モザイク(4:16)
本作冒頭のグランジ3連発の締めを担う、R&B風味やポストロック的音響が粘っこいグランジ展開と結びつく強力な楽曲。前曲の静寂の素っ気無い殺風景さと異なる、パッドシンセから始まるこの曲の不思議に奥行きのある殺風景さのコントラストに、本作の殺風景さの表現の幅の広さを思う。その16ビートのねっとり気味の荒涼感の中で、木下理樹のキャリアでも一、二を争う悲痛なシャウトが響き渡るところで、ここまで3曲の絶望的なテンションの高さのピークを示してみせる。
前曲と同じシングルからの収録ながら、曲順を少し変えて並べてみせることで、このアルバムの中での曲の流れにしっかりと組み替えられている。ここまで徹底的に痛々しい流れにしたからこそ、ノスタルジックな音響とポップさが慈愛のように響く次曲がとてもよく映えるようになる。後半の流れもそうだけど、本作は既発曲を並び替えてアルバム内でのドラマチックな物語性のある曲順を生み出すことにとても成功していると思う。
既発曲なのでより詳細なレビューは以下を参照。
4. BUTTERFLY KISS(3:33)
ここまでのハードな流れを一旦リセットし、ソフトで柔らかな音響とポップさとでアルバムのファンタジックでノスタルジックな面を強調し、作品内の絶望的な感覚を多面的なものにする約針を果たす名曲。
この曲はある意味では『SWAN SONG』収録曲で獲得したエフェクティブで抽象的な音楽性をよりポップに発展させたものと言えそう。それは、イントロから湧き上がってくる柔らかいパッド系シンセの棚引く様からも窺える。そこに、エフェクトの曖昧さとは対照的な歯切れのいいアコギのアルペジオを伴った軽快な演奏が始まっていく段階で、これまでの鬱屈した空気感が一変するのを感じる。特にドラムの軽やかさがとても印象に残る。ここまでのこのバンドで最も軽快な、軽く空中を跳ねるかのようなプレイだと思う。コードも明確にメジャー調で、柔らかなアコギ共々、とてもファンタジックな空気感が生まれている。このファンタジックさも、第一期ART-SCHOOLではずば抜けたものがある。木下理樹の声には深めのリヴァーブがかかり、リリカルなメロディも含めて、本作でこれまでやたらと刺々しかった音の輪郭がひたすら可愛らしくなっていくのを感じられる。
そんなフォーキーとも言えるAメロに対して、サビに入ると今度は一気にシューゲイザー的な要素が高まってくる。面白いのは、シューゲイザー的なエフェクティブなギターサウンドが溢れ出していく中で、リズムは軽快な4つ打ちのビートに変化するところ。それまでからはっきりとリズムが変わるけど、その代わり方の淀みない具合と、剽軽さ・可愛らしさがまた、この曲のテンポのいいポップさの発展の仕方を支えている。
その意味では、間奏や終盤などでよりシューゲ感の強まる多重ギターサウンドの鮮やかに連なる中で「Tonight」とファルセットで連呼する様も、この曲の爽やかさを邪魔せず、むしろよりロマンチックさを加速させるように働く。特に間奏の、Aメロのコード進行を繰り返しつつもギターはワンコード気味にエフェクティブな浮遊感を放ち続ける箇所は、独特のノスタルジックな質感を備えていて、多幸感も寂寥感も同時に湧き上がるような音響をしていると思う。
そして、そんな幸せな轟音から、元のあっさりした演奏に戻ってスッと終わるところにまた、寂しさへのフェティシズムのようなものが感じられる。そういえば、同じくシューゲイザーな浮遊感を有していた『LOVERS』も、轟音から元のオフの演奏に戻って終わるスタイルで、この辺の「陶酔的な響きの轟音はそのまま演奏を終わらせない、元の覚醒してしまった状態に戻して終わる」という共通点には何らかの美学を感じる。
歌詞で綴られる言葉についても、初期スピッツ的に“死の暗喩”として示される“冷たさ”の描写にどこかあどけなくて可愛らしい感じが乗って、不思議なファンタジー世界を形成している。
氷を砕いて歩こう 何も話さなくていい
何より 澄んでいるから 冷たく乾いた朝に
彼女は優しく死んだ 何一つかなえられずに
誰一人知らない場所で 声にもならない声で
光の中へ君は 触ろうと手を伸ばしたのさ
僕は思い出すんだ 永遠に触れなかった事を
Tonight Tonight*12
最初2行はそれこそ木下理樹ソロ時代の歌詞に共通するような、切れ味のあるあどけなさが現れてきている。その後の「彼女」の死は、木下はインタビューで「どこか遠くにいる人とか、そういう意味で使いましたね」「何となく『本当に好きな人には触れない』みたいな感じってあるじゃないですか」と発言しているけど、そういう風に読むかどうかで想像の余地が広がるのもいい具合だと思う。そのまま字面どおりの物語として読むのもまた、どこか寒い国の童謡みたいな感じがして綺麗だと思う。
この曲は、このバンドのキャリアに点在するギターポップ・シューゲイザー要素が濃く出た楽曲のひとつとしても知られ、後にこのバンドのインディーギターロックの側面の再評価が進むようになって以降、この曲のファン人気が絶大なものになったように思う。2008年の『エミール』*13はこの曲に連なる系統の楽曲と言えそう。当時だって結構本人の気に入りだったのか、このアルバムの後のライブ盤でライブ演奏が聴けるし、またテレビ出演時の演奏の映像もネット上には流れている。ライブ演奏だとテンポが上がってちょっとエモくなってしまうのも、それはそれで可愛くてキャッチー。本当に愛らしい曲だと思う。
5. イノセント(4:02)
前曲に引き続き、明確なメジャー調の循環コードのもとで、オンとオフの強調されたアレンジによってよりパワフルに勢いよく駆け抜けていく、本作では疾走感のある方に含まれるであろう楽曲。同じく疾走感のあるパワーポップな『ジェニファー '88』に比べるとこちらの方が屈託まみれの捨て鉢感があって、それがサビで一気にメロディとして高揚するのが面白いところ。
イントロの、ギターの逆再生か何かをリピートし続けるようなSEの登場で、『モザイク』からここまで3曲連続でそういう音が登場したことになる。そこからブリッジミュートのギターが聞こえ出すところのフワフワした感じは前曲からの余韻と連続性も感じさせる。ただ、この曲の場合歌い出しのところから入ってくるベースの存在感がその後はグイグイ引っ張っていくおかげで、フワフワ感が上手く推進力に切り替わっていく感じがある。アームで揺らされたギターの音も、途中から入ってくるドラムの沸々としたタム連打も、コード進行の遂行を強く引き受けるベースの存在感によって纏め上げられていく。
その沸々としたテンションがドラムのスネアフィルで一気に解放されるサビの、メロディは高く飛翔するけれどでもギターの歪みが案外重くて爽快感がある程度殺されているところが、どことなくこの時期の歪み方のらしさだなあ、と思える。バックのファルセットのコーラスも込みで歌は高く浮かび上がるのに、演奏はどこか浮遊しきれないまま這うような、この乖離の感覚がこの曲の面白いところだと思う。それにしても、Aメロと同じ循環コードで見事にメロディを飛躍させるのは流石。何ともこの時期的なネガティブな歌詞なのにメロディが明るく勢いに満ちているのがちょっと可笑しい。このサビメロディはしばらく後に、木下理樹の根暗サイドを実に根暗な形で表現した『LUNA』*14という曲で再利用され、同じメロディでも情緒の違いすぎる様に興味深いものを覚える。*15
2度目のサビ後の間奏以降では、印象的なギターフレーズが繰り返され続ける。これはThe Cars『Just What I Needed』の終盤のシンセフレーズからの引用。どことなく楽曲自体のコード感やギターのブリッジミュート等の音も被らせてある感じがしなくもない。ちなみにこの元ネタの楽曲は、The Cureの初期の名曲からタイトルを取った映画『Boys Don't Cry』の主題歌にもなっている。そして『Boys Don't Cry』というタイトルは後にこのバンドもライブ盤のタイトルとして借用することとなる。このギターフレーズは特に最後のサビ後でひたすら繰り返され、終いにはこのバンドにおいて珍しいフェードアウトによる終了の仕方をする。確かにこのリフの繰り返しをどこかで止めるよりも、ずっと続いていく風にしたほうがこの曲のアドベンチャーな雰囲気を止めずに済んで良さそうな気がする。
メジャー調の楽曲だからなのか、歌詞には『Requiem For Innocence』の頃のような情景描写の感じがほんの少しだけ戻ってきている。
街路樹の下 二人は重なって
愛されたいと初めて思うんだ
静脈管に愛を打つだけ 哀しみさえも透き通って
I'll fall down with you もう何も見えないさ
I'll fall down with you この眼を潰して
「重なって」をセックス的なものとして捉えるかどうかでも大きく変わる一節で、でもこれをもっと曲タイトルに準じたピュアなものと捉えるにしても、結局その後の行でドラッグ的な描写が入ってくるという、結局愛とドラッグじゃん、というこの時期な世界観なんだなあって思う。それにしても、歌詞の内容の割に本当にグイグイとパワフルに侵攻していく様が可笑しくも悲しい。
6. アパシーズ・ラスト・ナイト(3:30)
アルバム前半の比較的明るいパートは全曲で終わり、ここからアルバムのダークサイドに向かって一気に重力感が増していく。Smashing Pumpkinsのマイナー調のゴス気味な楽曲をシューゲイザー化したような趣のある、または木下流シューゲイザー歌謡とでも言いたくなるようなメロディ展開を有する楽曲。先にシングル収録の『JUNKY'S LAST KISS』で書いていたとおり、Smashing Pumpkinsのマイナー曲『Apathy's Last Kiss』からタイトルを部分的に引用したもう一方の楽曲でもある。
さらにややこしいことに、この曲のメインリフ的存在のダークなアルペジオのフレーズはThe House of Love『Shine On』のアルペジオフレーズのサンプリング的な使用で、このフレーズをグランジ以降的なマイナー調のコード進行とねっとりした16ビートで鳴らすことが基本軸となる。原曲では8ビートで突き抜けていく感じのアルペジオが、16ビート気味なリズムを基にすると急にどこかどこかねっとりした印象になるのは面白い。また、その背後でダブ的に駆動するベースや、ワンコードを鳴らし続けるクリーン気味のリズムギターなど、色々と不思議な取り合わせの中、憂鬱げなメロディが潜伏する。
そして、サビでのメロディの飛翔の仕方。いい意味でベッタリとメロディを大きく昇降させる様には、彼のキャッチーなメロディ書きとしての味わいが、珍しく大胆で王道めいた形で表出している。短いメロディを連続で詰め込むことが特徴的な彼のメロディ群の中でも珍しい、大きくダイナミックな動き方で、歌詞共々悲痛さの色合いが劇的な感じになっていく。ナチュラルにシャウトが混じってくるようなメロディの描き方の妙というか。一気に歪みが重くなるギターも重力感があっていい。
あとは、この曲もまた間奏や後奏でギターサウンドがシューゲイザー的な色味を帯びていく。この曲の場合それはワウによる嵐のようなサウンドの具合が特徴的で、今作の荒涼の大地に嵐が吹き荒れるかのような情緒がある。木下のファルセットもまた怪しさを煽る方に働く。
歌詞について。この曲もまた、喪失と無能と失望とを共依存で回していくような内容だ。
クリスマス・イブに裸足のまま逃げ出そう
上手く刺さらなくて彼女はただ叫んだっけ
二人だけの国で失ってばかりねって
君はただ笑って そう言って笑って
光にさらされ 二人は溶け合って
光を失くして 何処へも飛べずに
光にさらされ このまま沈めて 沈めて
「どこへも行けない二人」という本作で何度か出てくるモチーフは、妙に甘美な退廃さを匂わせてくる。スピッツの『ロビンソン』なんかにも出てくるような、誰も触れない理想郷的なもののはずの「二人だけの国」でどうしようもなくなっているところに、主人公たちの生きていけなさ、その可憐な不器用さが美しく描かれている。
7. LOVE/HATE(4:46)
このアルバムの底、とでも言うべき、この一連の時期の虚無感にとどめを刺すようなボロボロの情緒と、まるでそういうエモかスロウコアのようなテンポと演奏の装飾で、崩壊する寸前の機械のように駆動していくアルバムタイトルトラックにして名曲。テンポ感といい諦観に満ちた情緒といい、ある意味では『LILY』の焼き直しとも言え、おそらくはこの曲があるために『LILY』はアルバム収録から外れたんだと思われる。妥当だろう。
また入ってくる光の揺らぎのようなシンセエフェクトにスローな演奏が絡みだした時点で、ボロボロに疲れ切ったような光景が、これまでの積み重ねもあってか、見えてくるような気がする。2音のアルペジオは何のコード感も演奏者の感情も感じさせずにただただ反復し、太い白玉のベースだけで楽曲のコード感がギリギリ形成される。淡々と進行するドラムの音色も含め、そこにはどこかUSエモ〜スロウコアの情緒が滲んでいる。最も大きな影響源としては、エフェクトから始まるイントロも含めて、Sunny Day Real Estateの1stに収録の『Grendel』だろうか。木下理樹は、ここぞという時にSDREの1stからの引用をしてくる傾向がある。しかし、歌の乾いた進行具合なんかにはむしろSDREの3rdくらいの、エモ的な爆発をしない情緒具合からの影響も感じられる気がする。言葉数少なく配置されたメロディはまるで歌うのもやっと、というような息も絶え絶えのくたびれきった趣。
サビ的に展開する場所でも、言葉数は増えても、そのフレーズも込みで疲れ切ってるような具合に、同じ短いメロディを繰り返している。演奏も、バンドの精気の抜け切ったグルーヴに高いピアノの音が天国めいて響いてくる。ドラムのオープンハイハットばかりが音圧を稼ぎ、飛翔できないしグランジ的にも炸裂しようのない演奏とメロディは、作曲者の“諦観”を響かせる意思を懸命に遂行する。
そしてやはり、2回目以降のサビ以降に更なる展開として、ようやくパワーコードの決断的な、やや重たげなリフが鳴らされる。それもまた、途切れ途切れのフレージングは、演奏中に生命力が湧き出ないよう、曲のささやかな潤いすら許さない、ひどく乾いたエモ成分だけを出力する仕組みになっている。休符具合のフレーズの元ネタはSDRE『In Circle』の終盤のリフと思われるけど、より激情が希薄な、擦り潰れてしまったような鳴り方をして、だからこそ、そこから飛び出してくる木下の呟き、もしくはシャウトがひどく惨めに作用しうる。そして、間奏の歪み切った3音アルペジオを主軸とした砂嵐のようなギターサウンドの展開は、そこに乗る木下の虚ろで美しいファルセット共々、この時期のサウンドの象徴のような瞬間だ。
そんな、木下理樹のこの時期の虚無感の限りを曲に落とし込んだようなサウンドに対して、歌詞についてもまた、この時期に書き続けてきた自身の無能、もっと素晴らしい人間になれたらな、という虚しい願望、そして諦めが、ひたすらに描写される。
愛を交わすと俺は泣いて そんな資格は無いと知って
作り笑いが上手くなった 25歳*16で花が死んだ
どんな時も 完璧で 誰からも 愛されて*17
一度だけ 味あわせて その気持ちを
それだけでもういい もういいよ
あと、インディーズ時代を中心に盛んに行なっていた過去の文学作品等からのカットアップについて、その行為自体をすり潰すようなフレーズがちょっと入ってくるのも、どこか思い詰めた風があって興味深い。
千の天使*18が俺の中で
羽根を焼かれた 今、目の前で
木下理樹によると、「『何だこの暗い曲は』って自分で、がっくりしました(笑)」とのこと。また、ライブ中に歌ってて泣いてしまったらしい。『MEMENTO MORI』*19といい、この時期の彼の惨めさを自らまさぐるような曲には、彼も思わず涙してしまうらしい。エフェクト抜きのライブ演奏が本作の後のライブ盤で聴ける。やはりどこかダーク目のエモバンドっぽいロウさがある。
どことなく、ここまででレコードの片面、みたいな感覚がある。実際にレコードでそうやるには尺が長すぎるのかもだけど。
8. ジェニファー '88(2:40)
前曲の極まりきったネガティブさを振り払わんばかりに元気で朗らかに疾走してみせる、罪のない感じのポップで明るい楽曲。3分に満たない尺で駆け抜けていくのもアルバムの雰囲気を転換するのに実に丁度いい尺で、わざわざシングルから引っ張り出してきた意味も理解できる。後のライブ盤でも前曲と続けて演奏されるくらい、この曲順のパッと切り替わる感じを気に入ってるのかも。
可愛らしくも力強いイントロの重量感も、そこからパッと疾走するリズムに切り替わるところも、この暗くて重い傾向にあるアルバム中で聴くととりわけよく目立つ。張り切った具合に演奏されるギターソロに至るまで、本作の他の曲では感じられないタイプの可愛らしさが凝縮されている。思うに、木下理樹はその気になればこのタイプの曲は幾らでも書けただろうけど、この曲ほどプリティーな曲をゼロから作るには、バンドの状態が悪くなりすぎていて、素直にシングルからこの曲を引っ張ってきたんじゃ無いかという気がする。同じシングルから3曲も持ってくる、という事実にも目をつぶって。
既出曲なので、細かいレビューは以下を参照。特に、こんなライトな曲でありつつも歌詞の世界観はしっかり『LOVE/HATE』していることと、本作の終着点である『しとやかな獣』につながる歌詞を内包していることは注目できる。
また、坂本麻里子氏のライナーにも書かれているとおり、ここから先はアルバムの第2部という感じがする。レコードのB面、2枚組のもう片方、みたいな。14曲(もしくは15曲)のアルバムは、7曲入りミニアルバムの2枚組、みたいに捉えることも可能だろうと思うと、ここで前編・後編別れる、というのはとてもしっくりくる。
9. BELLS(3:09)
明るく突き抜けた前曲からまた本作の暗く乾いた雰囲気に戻るべく仕掛けられる、荒涼感そのものを表現しようと目論まれた砂嵐のようなエフェクトが楽曲中ずっと鳴り続ける、砂嵐の中の浮遊感みたいな情緒の楽曲。インタビューでは木下から「この辺りからもう記憶が…」とか言われたちょっと可哀想な曲でもあるけど『ジェニファー '88』から直接『SKIRT』に繋ぐよりもこの曲があった方がいいテンポになると思う。
この曲の象徴であるジェット機めいたエフェクトは、同じインタビューによると、J.Mascisのソロアルバムの最後の曲*20での「ぐぉぉぉぉ」みたいな音を出したくて木下と日向が頑張った末の音らしい。ここに3音アルペジオや8ビートから離れたリズム、そして曲タイトルどおりのベルの音が響くことでこの曲の雰囲気が作られる。木下の歌うAメロは過去曲『TEENAGE LAST』*21からのリサイクルで、そういうこともあってか、この曲はバンドサウンド中心の作品における「バンド外の音を多く含んだアクセント的な楽曲」という雰囲気がある。
サビのリフレインよりも、その終盤に洪水的な様々な音がブレイクする瞬間にこそこの曲のハッとする瞬間が用意されている。それは特に2回目以降のサビ終盤のブレイクを繰り返す展開と、そのブレイクの箇所で残り続ける砂嵐ノイズの対比*22や、間奏から最後のサビに向けて駆け出して、サビに入る直前でブレイクしてみせることなどからも伺える。特に最後のサビ後のブレイクの連発には、この曲ならではの吹き曝しのような寂しさが滲んでいて、それが曲間無しにパッと次曲のカラッとしたアコギイントロに繋がるところがまた、それ自体聴きどころになっているようにも感じられる。
件のインタビューで木下本人から「歌詞は全くもって覚えてないけど(笑)」と言われてしまった哀れな歌詞は、本作の基本軸をなぞる感覚の劣化とノスタルジーを絡めた内容。そういう詩作面でも次曲との連続性を感じさせる。
そばかす レインコート 柔らかい耳の形*23
本当は知ってたんだ君が云おうとした事*24
10. SKIRT(4:01)
既発曲から引っ張られてきつつ、しかし次曲と連続してきっちりとアルバムの山場を形成してみせる、本作のあどけなさ・ノスタルジー方面からのエモーショナルさを象徴するミドルテンポのナンバー。アコギ主体のいい具合に野暮ったいサウンドと歌がどこか開けた光景を思わせ、砂嵐の続いた前曲からパッと晴れたような感覚になるのも具合がいい。
そして、2回目のサビ後のブレイクの、やたらと景色が広がっていくようなところから、その中でひしゃげてしまったイノセンスそのもののような木下理樹の言葉になってない惨めなシャウトは、タイトル曲でひたすら抑圧された類の感情が激烈に噴き上がってくるような思いがする。ここまでひたすら抑圧されてたこともあり、ここで聞くこのシャウトは元の『SWAN SONG』収録時にも増してエモーショナルに響く気がする。もしかしたらART-SCHOOLで一番エモい瞬間はここかもしれないと時々思う。
既出曲なので、細かいレビューは以下を参照。
ちなみに歌詞カード上で見ると、『ジェニファー '88』からこの曲まで3曲連続で、同じフレーズを繰り返す歌詞が書かれているため、字面だけ見るとちょっとアホっぽい感じになってしまってはいる。
11. UNDER MY SKIN(3:42)
前曲の少し寂しいアコースティックな響きからクロスフェードするようにこの曲のフィードバックノイズが聞こえてきて、そして例のベースラインが始まるところの不穏で邪悪な格好良さ。既出曲を並べただけとは思えないほどの曲順の良さによって、シングルと同じ音源なのにその時よりも疾走感が増して聴こえそうな程の勢いを感じさせる、この時期的な虚無感をそのままシンプルにかつ“的確な単調さで”疾走させた楽曲。
この曲特有の、ベースの邪悪な躍動っぷりの割にそれ以外の要素がひたすらシンプルに削ぎ落とされたことから生じる「何も無さ」的な音の感じは、幼さが爆発したような前曲の後だからこその情緒が、この曲順によって生まれてさえいる。この後終盤のミドルテンポ2曲に繋ぐという意味でも申し分ないし、本当に、置く位置がとても良い。曲順というものの意味を深く考え込んでしまいそうになる。
既出曲なので、レビューは以下を参照。これより後3曲(初回盤は4曲)は全て初出曲となる。既出曲だった『シャーロット』以上の山場となる曲をアルバム終盤に置かなかった『Requiem For Innocence』とは大分状況が変わってきている。
12. プールサイド(4:05)
このバンド特有の透明感とシューゲイザー由来の轟音の感覚とがミックスされた楽曲群*25のひとつとして挙げられる、寂しい陶酔感に包まれたオフとどこか悲壮な推進力を有したオンを繰り返す、乾いた空気のある今作では例外的に水中のサウンドの感じが濃厚な名曲*26。
前曲の激しいギターのフィードバックの余韻が千切れ去るのとほぼ同時に湧き上がる3音アルペジオの、バックの今作的SEも伴った潤った陶酔の感じが、この曲のこれまでの楽曲との違いを如実に表す。まるで水槽の中に突然ワープしたかのような感覚。その宙吊りにされた感覚は、やはりワンコードで鳴らされ続けるギターのカッティングにも支えられて、その中でベースだけが、少しダビーな響きでコード感を形作っていく。アルペジオ等の陶酔感にはSDRE『Shadows』の、コード感にはDeath Cab For Cutie『405』の影響を感じさせつつも、特にベースのローの効いた音がサウンドを強く牽引する。そこに飛び込んでくる木下のメロディも、メロディ間の空白を慎重に取った、サウンドの雰囲気に上手に潜むスタイルで、その宙吊りの感覚を維持し続ける。
スネアのフィルインから雪崩れ込むサビでは、今作でもとりわけ奥行きの深い轟音を構築してみせる。それまでと同じコード進行で8分のベースと歪んだギターを鳴らす傍ら、ワンコードのクリーンなギターの響きも多重に交差し、更に奥の方で輪郭を曖昧にされた何かが高速でかき鳴らされてるのが響いてくる。そして、8ビートにポストロック的な変則性を含ませたドラムが推進力として、メロディアスさと勢いとを持ったメロディと共に強力に躍動していく。まるで静かで憂鬱な水中でもがくような、そんな焦燥感の混じったドラマチックさが感じられる。
2回目のサビ以降は例によって間奏セクションが生じ、その轟音の中を泳ぐ木下のファルセットが、何かどこかの民謡を誦じたかのような、美しく印象的なラインを描いていく。彼のファルセットの中でもとりわけ素晴らしいもののひとつだろう。特に、曲終わりでこのファルセットとともに演奏が止むところは素晴らしく、その余韻のまま、本作の物語の最終段階と言えそうな次曲に繋がる辺りは、本作のクライマックスと言える。
歌詞も、木下本人がインタビューで語るところの水族館のイメージをもとに、豊かに儚いロマンチックなイメージが広がっていく。
影の中 光を壊せば 君はちょっと 嬉しそうだった
××××*27と愛 あるいは感情で 抜け出そうと そう誘ったんだ
プールサイド ただ君に見せたかった場所があるんだ
プールサイド 水の中で感情を失くして泳ぐ 二人で
メジャーデビューアルバム冒頭曲『BOY MEETS GIRL』の歌詞にあった「ねぇ 今から 美しい物を見ないか?」と連なるような、気取ったようでいてどこかあどけなくも真剣な願いのようなものが、ここでは虚しげな共依存の感覚とともに歌われる。「影の中光を壊す」遊びのあどけないようなどうしようもないような状態といい、もしかしたらこの曲の歌詞世界が一番ドラッギーで危ういかもしれない。勇敢な純真さとドラッギーさが隣り合ってる怖さ、というか。サウンドの感じも伴って、第一期ART-SCHOOLの楽曲中でも『シャーロット』と同等くらいのとりわけ蠱惑的な雰囲気を放っている。
ライブ演奏では、流石に2本のギターでは完全再現は難しいためある程度演奏は端折られるが、それでもこの曲のイメージをしっかり保持したものになることは、本作の後のライブ盤特典DVDで見れるこの曲の演奏等を聴くと理解される。それにしても、精神が病み切った、ギターに触りたくもない状態だろうに、大山純は本当にいいギターを弾いている。なお、件のインタビューでは「この曲はみんな、そんなに話し合わずに普通に録れて、よかったですね」と言っていて、崩壊状態のバンドがこの曲をポンと出したという事実がちょっと理解できない。極限の状態ながら、クリエイティビティーは本当に最高潮の状態にあったんだな、と思わせる。
ちなみに、日本のロックにおいて一番有名な『プールサイド』の題を持つ曲はおそらくbloodthirsty butchersのものだろう。NUMBER GIRLもカバーしている。あと、偶然だろうけども、本作と同じ年に出た真空メロウのアルバム『ぞうの王様』にも同名の楽曲が収録されている*28。どの『プールサイド』も、豊かな水中の揺蕩う感覚が音に活かされた、素晴らしい名曲ばかりとなっている。動画のリンクを貼っておいたので、よかったらぜひ『プールサイド』聴き比べしてみてください。
13. しとやかな獣(4:04)
水中をもがくようだった前曲から、一気に眼前が無限に開かれた荒野の光景にこの曲のイントロになった瞬間に切り替わる。シングル『EVIL』から続いてきた2003年のこのバンドの困難も荒廃も虚無も退廃も、全てをRadiohead『Black Star』譲りの大らかなスケール感と屁理屈のようなギリギリのポジティビティで受け止める、一連の時期の「結論」を担うに相応しいポテンシャルを持った名曲。思うに、アルバムの締めに相応しいこの曲が出来たがために、同じベクトルの『SWAN SONG』がアルバム収録から外されたのではないか。『LILY』共々、アルバムでその発展形が出せた、ということでもあるけども。
イントロの段階からはっきりと、その雄大なスケール感が十分に感じれる。ゆったりしたリズムを刻むドラムとベース、『ジェニファー '88』ぶりのメジャーコード主体の安定したコード感、アームで揺らすギターとキラリとしたアルペジオとの穏やかな交差などなど、そのアンサンブルの“安心感のある”響き方はこれまでこのアルバムに無いものだった。すぐに歌に入らず一旦ブレイクしてみせるのは影響元の楽曲に忠実で、むしろ「この曲は『Black Star』を下敷きにしてますよ」って宣言しているみたいだ。そもそも、ART-SCHOOLでRadioheadからの引用自体がとても珍しい。
歌が始まると、演奏はかなり整理される。呟くような這うような低音で歌う木下のメロディに煌めきを付加するように鐘のように鳴るギターのコーラス掛かった音が印象的で、どこか清らかな感じが、やはり雰囲気を安心させる働きをしている。
そしてサビの、もうモロに『Black Star』なギターリフの展開に乗って歌われる木下の、必死さの伝わってくるような懸命なボーカルの飛翔は、原曲どおりに下降してはまた高いところから下降するのを繰り返すギターリフと美しい対比を描き、ファルセットのラインが終わる頃には、歌詞の上では何も解決してないような歌なのに、何かホッとするような安心感が訪れる。
やはり2回目以降のサビに新たに展開を設けてくる楽曲だけども、この曲の場合、ミドルエイト的にも感じられる新たなコード進行の展開でサビが引き継がれる2回目と、イントロと同じ開かれたコード感と演奏の中をラララ調のコーラスで晴れやかに歌われる3回目とで展開が違うところが、この曲のこの時期の曲としての特別な作り込みを感じさせる。特に最後の「ラララ」コーラスの大団円感は素晴らしく、本当に歌の中で何も解決してないのにハッピーエンドな感じがして、ちょっとばかり可笑しな気持ちになる。続く最後の曲で現実に引き戻されるけども。
歌詞。本当に、この時期的な凄惨さは何も解決しないまま、でもひとまず、屁理屈でもいいから「生きれる」という言葉を残している辺りに、木下理樹の、誤魔化しでなくきちんと何かこのどうしようもない情緒と状態にケリをつけようとする誠実さを感じる。
うたかた あえぎ声 注射針 行き着く果てには何も
死ぬまでギリギリと分かっていた
生まれた事に意味は無いから 明日も生きれるよ
腐ったアジサイの赤の色
美しい、しとやかな獣よ 貴方は空っぽのままでいい
光は、光は此処には射さないさ
裸足で、裸足のままでいい 裸足で
セックス・ドラッグ・ロックンロールを地で行った陰惨物語の果ての、この結末。「生まれた事に意味は無いから 明日も生きれるよ」なんて屁理屈にもなっていないような言葉を、それでもせめて杖にして、空っぽであることを肯定するこの歌のヒロイックさは、ネガティブな歌を積み上げてきた彼だからこそのものだろう。「腐ったアジサイの赤の色」という鮮烈なイメージも携えて、なのに、なぜだか晴れやかな気持ちになるのは、なんだか可笑しいけど、清々しいことだ。
曲タイトルは同名の1962年の日本映画からの引用*29と思われる。件のインタビューでは『プールサイド』とともにアルバム中で好きな曲と言及され、自分の生き方・感情をちゃんと乗せられた歌だと話している。ライブで聴くことは相当珍しい楽曲だったけど、それだけに2015年当時の活動休止前最後のライブの際にアンコール含む全てのラストで演奏された際は、とても衝撃的で、かつ、なんか安心したことを覚えてる*30。
14. SONNET(初回盤・11:43*31、通常盤・4:25)
前曲の大団円の感じから「いやいや何も解決してませんよ」と現実に引き戻すかのように始まる、ドラムレスのままアコギを中心にしたこじんまりとしたサウンドに、この時期のネガティブさをありったけ注ぎ込んだような歌詞を載せた、結局暗いな!って感じの楽曲。まるで後味の悪いエンドロールのように、アルバムの最後にぴったりと張り付いている。どことなく、シングルの最後とかに収録されてた宅録系の楽曲と同じ趣が感じられる。
延々と3つのコードを繰り返し続けるアコギのコードストロークが印象的。このアコギは木下でも大山でもなく、何故か日向秀和が演奏している。メジャー調のコードのはずなのに何故か全然そういう明るさが感じられないのは、バックで喋り続ける何かの映画の子供の喋り声の切り抜きリピートの怖さや、バックで曖昧な輪郭で鳴り続けるギターのせいか。ベースも含めて演奏はどこかモコモコした質感で纏められ、やたら線の細い感じのアコギのタメの効いた響きが刺々しく感じられる。木下の歌も、呟くようかと思えばメロディの高いところは張り裂けるように歌い、歌詞の虚しさを体現する。
サビの箇所の、ささやかに単調なフレーズのピアノが入る感覚は、なかなかに侘しい感じがして、少しばかり力の入った木下のボーカルにいい意味で冷や水をかけるかのような響き方をする。木下もまた、サビのフレーズを歌い終わった後のファルセットにおいて、かつての『シャーロット』のそれを思わせるような美しいラインで、この曲の惨めさを美しく縁取ってみせる。
楽曲が終わると、延々繰り返されてきた声のサンプリングが切り替わって、「Girls Back Teen!!Girls Back Teen!!」としゃべりだしてこの曲が終わる。曲間を隙間無く繋げてきたアルバムの最後の音がこれで、何処までもノスタルジックさに彩られた虚しさに突き落とされたような気持ちになれる。
歌詞は、何気に本作タイトル曲に並ぶくらい暗く、コンプレックスに塗れている。
飲みたいし 浴びたいよ その蜜を誰よりも
人間のくずなんて 知ってるさ昔から
これさえも出来ないの? そう云われ育った
感情を切るたびに あふれる物は
一度だけ愛されたら 声になど、ならない位
その腕の中なら死ねる 手遅れとわかってるさ
それでも
そして、失うことのふわっとした悲しさを、さらりと詩的に描いてみせる。
人はただ失うから 太陽や指輪、匂い
僕もまた失うだろう 雪どけにくちづけした気持ちを
歌詞が全然タイトルどおりのソネット形式でないのはご愛嬌。というかなんでこの曲のタイトルは『SONNET』なんだろう。優しい音でとびきり暗いことを歌う、木下理樹の意地のようなものを感じさせる本当の最終曲。もちろん、初回盤だとこの後4分程度の無音の後に、ボーナストラックであるところの次曲が始まるけども。
15. SEAGULL(3:10*32)
「最終曲の長い無音の後に始まるボーナストラック」という、1990年代以降のCD文化の中で生み出された文化を自分たちでもやってみるART-SCHOOL。初回盤のみに収められたのは、初期Smashing Pumpkins的な明るくどっしりしたグランジ感のあるパワーポップ曲、というかコード進行や展開がかなりモロにFountains of Wayne『Sink to the Bottom』している楽曲。トラックとしては14曲名の一部分、という形。
どっちりと元気の感じられるドラムから始まり、ジャリジャリしたギターサウンドも、あまり動かないリードギターも含めて、軽快で爽やかな響き。ベースも爽快感に全振りな譜割りで鳴らされる。木下のボーカルもこの時期ではかなり溌剌としている方で、威勢よく情けない歌を歌っているところが清々しくていい。
サビのタイトルコールみたいなのを短く繰り返す様も、実にスッキリとしていて、リードギターもダブルチョーキングを用いたいかにもなフレーズを入れたりして、全体的にどこか楽しげな感じがある。この曲はさらにミドルエイトセクションまであり、そこで沸々とした地点から爆発的なボーカルになる箇所の爽やかなしみったれ具合は、本編のエモさとは異なるもこれはこれで爽やかにエモい。
歌詞の方は、それなりに「LOVE/HATE期」の世界観な内容。やっぱりコンプレックスやら「愛される資格が無い」やら何やらを「わめき散らして」いる。
俺の心の中 確か 12歳の時に死んで
偽る度に 偽られたんだ 今は夢のように思えて
えらく溌剌としたサウンドや歌に、なんとなくボーナストラック送りになった理由が理解できるものとなっている。歌詞的にも上記の部分がタイトル曲の「25歳で花が死んで」の部分と被って「どっちやねん」ってなりそうだし。でも単体で聴くと、このバンドの基本体力そのものをナチュラルに投げかけてくるような親やすさがあって、死蔵するのも勿体無い限りの楽曲。シングル『UNDER MY SKIN』に入れるのもあの3曲のいい緊張感を壊す感じがあるし、なんとなく、生まれた時期が悪かったような感じの不憫さがあるといえばある。同じようなメジャー調の初期スマパンっぽい楽曲は随分後年の『ローラーコースター』*33まで無いので、そういう意味でも貴重さのある楽曲。
・・・・・・・・・・・・・・・
終わりに・これもしかしてエモのアルバムじゃね?
以上15曲。初回盤なら無音込みで59分58秒、通常盤なら52分34秒の作品でした。
書いてて段々思ったのは「これはグランジというよりも、むしろエモのアルバムなのでは?」ということ。本当にもろにグランジな感触は冒頭3曲だけで、その後は、なぜだかえらく広いサウンドをカバーしてしまう“エモ”というジャンルの範疇にそのままスッと収まるようなサウンドのように思えました。案外、この記事で何度か言及したSunny Day Real EstateのCDの横とかに置いた方が、Nirvana作品の横に置くよりもしっくり来る気がしました。
「ハイを上げて突進すればそれでいい」みたいな潔さのアルバムな『Requiem For Innocence』に比べると、グッと各楽器の音質やミックスの感じが“まとも”なものになっていますけど、もしかしたらこれも、USインディ・エモ系の作品に照準を合わせて作ったのかな、という感じが所々あります。ドラムのプレイや録音なんか、特にそれを感じたりして。この後『PARADISE LOST』『Flora』と、しばらくは音質が更にハイファイな方面にバンドの作品は移り変わっていきますが、USオルタナの系譜のアルバムとしては、本作くらいのハイファイさとローファイさの具合が丁度いいようにも思ったりします。
鬱屈して、どこにも行き場がなくのたうち回るのが、やがてひとまずの結論めいた開き直りにたどり着く、という構成も、どこかエモーショナルな抜け方をしている感じがあっていいと思います。このアルバム、暗いことは暗いけど、ドロドロとした暗さではない気もします。性にも薬にも乱れた世界観ながら、どこかずっと透明感が保たれているのは、木下理樹の天然のナイーヴさ・潔癖さゆえなのかなと思います。だからこそ、この作品はどこまで行っても美しい。
もう書くことがない
多分、自分の人生でこのアルバムはこれが4回目くらいに、何度も全曲レビューを書いてきました。前回書いた分は2014年10月で、なので7年ぶりに書き直した形になります。
それだけ何度も書いているものだから、このアルバムの検索結果を大概自分の書いた文章が汚染してしまって、なんだか悪いことをしてるような、この名作を私物化しているような気持ちになっていました。
私物化するんなら、もっとマシな文章にしとけよ、と思って今回、ようやくここまで書きました。字数だけで言うと、自分のオールタイム2位くらいのアルバムに対して、たったこのくらいのもんか、オールタイム1位の『Yankee Hotel Foxtrot』には記事14個も費やしたのに?という思いも無くはないですが、でも、もう今思いつく限りのことは書き尽くしました。
自分の音楽観を決定づけたアルバムだし、しかも上記の私物化的なこともあって、自分にとって本作はなかなか冷静になって見つめることのできないアルバムになってしまっています。なので、ここまで書いた内容が読めたものになっているか少し怖い思いもありますが、もしこの記事にほんの少しでも、誰かが読んで面白いと思える部分があるのであれば、このアルバムの検索結果を私物化していた人間として、本当に幸いです。
これからも、このアルバムを自分のことのように思い続けていたいです。当時この作品を作るのに関わったメンバーの方々やスタッフの方々、大変ありがとうございました。あと、ここまで読んでくれた人も、大変ありがとうございました。
裸足で歩いていきましょう。
ART-SCHOOL作品の記事のリマスターを続けるか、まだ書いてない他の作品を書くかは未定です。ひとまずは、この作品の「よりちゃんとした記事」を書くことを目標に続けてきた一連のシリーズの、その完結編になります。
それではまた。
*1:初回盤はボートラ1曲追加で15曲。
*2:ただし、『Requiem For Innocence』に結実する2002年の彼らのリリースペースもまた十分に速いもので、ミニアルバム『シャーロットe.p.』が4月、シングル『DIVA』が10月のアルバム11月で、『DIVA』以降はメジャーデビュー直後の売出し中のこともあるけど、速い。ポイントは、そこからさらにずっと大量の楽曲を作って2003年のほぼ1年後にまたアルバムを出すまでになったことだ。
*3:この2003年のウェブ記事が今日でもみられる状態にあることは何気に敬意を表すべき事項だと思う。
*4:そういえば、日本で一番メンバーチェンジについてツッコミが入るくるりについては、岸田繁は楽曲中に一切そういうことを受けての不安や後悔みたいなのを表現しないですね。
*5:参考に、Pizzicato Fiveにおける小西康陽は、特にその後期において、自身に関する事柄も歌詞にしないと歌詞のネタがなかった、みたいな発言をしていました。これも素直に受け取っていいか悩ましいものではありますが。
*6:勿論、木下や、場合によっては日向が弾いたギターなんかも混じってるのかもしれないけども。
*7:思うのは、こういう風に表に出てくることのないような、彼みたいなハッピー寄りな結末を迎えなかったような人生が世の中には幾つもあるんだろうな、ということ。報われてくれ、とも、せめて何か幸せになってくれ、とも無責任に言えないから、ただ何か良いことを祈るしかないなと思う。
*8:ちなみに次に長いのが4枚目の『Flora』の15曲54分。この時期もアルバム前のリリースが多いことは興味深いところ。
*9:実際のオリジナル世代のグランジバンドって、エフェクターのオンオフによる展開よりも、リフと曲展開でドロドロと変動するタイプの方が多い感じで、むしろNirvana式のグランジサウンドの方が例外的な感じがする。だけど、Nirvana式のオンオフ形式のスッキリした格好良さの方が“グランジ”として分かりやすく格好良くて、そちらのイメージが定着している。これについては、筆者もドロドロ系グランジの魅力がよく分からないところではあるので、Nirvana式の方が結局好きだなあ、と思います。
*10:他の原因としてありそうな「曲展開が一緒」「何回間奏の後ブレイクするんだよ」といった批判については、むしろ木下理樹のソングライティングが割とずっとそうなので、まあお好きじゃないなら他の音楽を聴いててくださいよ、と言いたくなるようなものです。
*11:この時期と同じくらい暗い気がする『Anesthesia』の時期は、こちらは「それなりに生きてきたけど、結局どこに向かえばいいのかまるで判らない」という困惑が展開されて、ある意味ではこちらの暗さの方がリアリティがあるものかもしれない。
*12:ここのフレーズにSmashing Pumpkins『Tonight, Tonight』からの影響が全く無いとは言えないだろう。楽曲自体としてはむしろ『1979』をシューゲ化したような塩梅だけども。
*14:アルバム『Flora』収録。
*15:この曲については他に、後に木下と日向で組んだポストパンクバンドKilling Boyの『You And Me, Pills』に、Aメロ部分のブリッジミュートのコード感が流用されている感じがある。
*16:作曲・録音した当時は24歳だったらしい。
*17:この辺の「もっと他のまともな人間だったら」願望については、この時期より後しばらくも歌われ続ける。『PERFECT』(『LOST IN THE AIR』収録)とか。
*18:中原中也『宿酔』に出てくるフレーズ。木下は『FIONA APPLE GIRL』や『ダウナー』など、度々このフレーズを引用していたので、この曲で久々に引用されたと思ったら羽根を焼かれてしまう様は、当時の彼の心境の凄惨さを物語る。
*20:おそらくアルバムはJ. Mascis + The Fog『More Light』だけど、言われてる曲がアルバムタイトル曲なのか、それとも日本盤ボーナストラックの『Leavin' on a Jet Plane』(John Denverのカバー)なのか判然としない。タチが悪いのが、どっちも同じようなジェット噴射的なエフェクトが掛かっている。
*21:シングル『DIVA』収録。
*22:ここのブレイクの仕方は『OUT OF THE BLUE』(『SWAN SONG』収録)とやや被ってる感じがある。
*23:この辺の描写はちょっと村上春樹っぽい。というか「柔らかい耳の形」という微妙に意味の通らない感じが、かえって好き。
*24:この時期は「言う」と「云う」の両方の書き方が混在している。歌詞カードをよく読むと『アパシーズ・ラスト・ナイト』では両方とも使われている。おそらく、使い分けに大した意味はなく、単にどちらかに統合するチェックさえ間に合わないスケジュールだったんじゃないかと訝しむ。
*25:『プール』とか『シャーロット』とか『IN THE BLUE』とかは同系統と捉えていいと思う。つまり、この楽曲群は名曲しかない。
*26:もっとも、『SKIRT』から『しとやかな獣』までは全部大名曲だけども。
*27:この4文字は「ヘロイン」が入る。歌詞カード上は消されているが、歌としてはピー音で消された『JUNKY'S LAST KISS』と違ってちゃんと歌われる。
*28:元々は2002年のシングル『魔9』のカップリング曲なので、2003年初出というわけではないけども。
*29:そういうのも観てるのか…と木下理樹の映画鑑賞の幅広さを思わせる。あらすじを読む限り、なかなかにイービルな内容だ。
*30:そういえば、このブログになる前のブログでその時のライブを観に行った記事を書いてた。その記事は一応このブログにインポートはできたけど、でも形式とか何とかは壊れてしまって読みにくいままになっている。
*31:以下のボートラ及びその前の無音込み
*32:筆者がDAWを使用して単体トラックとして『SONNET』から切り取った際の演奏時間なので、参考程度に。
*33:彼らの5枚目のアルバム『14SOULS』収録。